お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件
佐伯さん

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件
佐伯さん

本書に掲載されているコンテンツの著作権等の知的財産権およびその他すべての権利は、SBクリエイティブ株式会社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
本書の内容を権利者の許諾なく複製・複写・翻案・放送・出版・データ配信(送信可能化を含む)などすることはできません。
カバーイラスト
はねこと
口絵・本文イラスト
和武はざの

「……なにやってるんだ」
今年高校一年生となり一人暮らしを始めた周が住むマンションの部屋の右隣には、天使が住んでいる。
天使というのはもちろん比喩であるが、その比喩が冗談ではないほどに椎名真昼は美しく
手入れの行き届いた亜麻色のストレートヘアーはいつもさらさらとして光沢が見えるし、透けるような乳白色の肌は肌荒れを知らない滑らかさを保っている。整った
彼女と同じ高校、それも同学年に居る周は真昼の評判をよく聞くが、文武両道の美少女というものが大半だ。
実際彼女は定期考査でも常に一位を取っているし、体育の授業でもエース級の活躍をしているそうだ。周はクラスが違うので詳しくは知らないが、
欠点らしい欠点は見えず、容姿端麗で成績優秀、それでいて
そんな美少女が隣に住んでいるのだから、この環境は一部の男子からは
かといって、周には彼女とどうこうなるつもりもなれるつもりもなかった。
もちろん、周の目にも椎名真昼という少女は魅力的に映る。
けれど、立場としてはたかが隣人。そして彼女と話す機会もなければ、
関われば男子からのやっかみを買うだろうし、そもそも隣に住んでいるだけで仲良くなれるのであれば、彼女に恋をした男子達も苦労しないだろう。
ついでに言うならば、異性として魅力的な事と恋愛感情を持つ事は必ずしもイコールで結ばれる訳ではなく、周にとって真昼は眺めるのが一番いい鑑賞用の美少女といった認識だ。
そんな訳で、甘酸っぱい関係とやらを期待する気も更々なく関わる事もまずなく、ただ隣に住んでいるというだけで接触すらしていなかった。
なので、正直雨の中傘をささずに一人途方に暮れたようにしている姿を見かけた時は、何をやっているんだと不審者を見るような
皆が寄り道もせず自宅へと急ぐ程の雨だったというのに、彼女は学校とマンションの間にある公園で一人、ブランコに腰かけていた。
(雨の中なにやってるんだ)
濃い灰色の雲に覆われ光が差さない空のせいで薄暗く、朝から
下手すればあっという間に風邪を引きかねない状態で、それでも真昼は静かにそこに居た。
帰ろうとすらしていないのだから、本人が好んでそうしているのだろう。他人が口出しするものではないのかもしれない。
そう思って、公園の横をすり抜けようとして──最後に見た真昼の顔がどこか泣きそうに
別に、彼女と関わりたいとか、そういう動機は持ち合わせていない。
ただ、ああいった顔をした人間を放っておくのは、なんとなく良心が痛んだ。それだけだ。
「……なにやってるんだ」
他意はない、という意味を込めてなるべく素っ気なく声をかけると、水分でずっしりと重くなっていそうな長い髪を揺らして、こちらを向く。
相変わらず、
雨に濡れていてもその輝きはくすむ事もなく、むしろ雨すら彼女の顔を引き立たせるような小道具になっている。水も
ぱっちりとした二重の瞳が、こちらを見る。
一応、真昼は周を隣人だと認識してはいるだろう。たまに朝すれ違ったりはするのだから。
ただ急に話しかけられた事に、そして今までまったく関わりのなかった人間からの接触に、カラメル色の瞳にうっすらと警戒が
「藤宮さん。私に何かご用で?」
ああ名字は覚えられていたんだな、と妙な感慨を抱いたが、同時にこれは恐らく警戒を
流石に、見ず知らずとは言わないものの他人に声をかけられれば、ガードを固めるのも頷けた。
もしかしたら彼女はあまり異性と関わりたくないのかもしれない。彼女は学年問わず校内の男子生徒から告白やアプローチを受けているらしいし、下心を持っている、と思われたのかもしれない。

「別に、用はない。ただこの雨の中一人でこんなところに居たら気になるだろう」
「そうですか。お気遣いはありがたいですが、私はここに居たいから居るので。私の事はお気になさらず」
警戒心剝き出しの
(まあ、そうなるよな)
訳ありなのは明白で、関与してくるなという拒絶の表れに、周も深追いする気はなかった。
元々、気まぐれに話しかけにいったようなものだ。事情を聞こうとしたのも流れというだけで、さほど気になるものでもない。
彼女がここに居たいというなら、別にそれでもいいのだろう。
むしろ真昼としては何で話しかけてきたんだ、といった感情が
ここでまだ話しかけていけば確実に嫌がられるので、もう撤退するべきなのだろう。
幸いというか、別に真昼によく思われようが悪く思われようが関わりがないので、あっさりと放っておいて帰るという事を決断出来た。
ただまあ、ここで少女がずぶ濡れになって一人ぼっちで居る、というのも居心地が悪い。
「風邪引くし、さして帰れよ。返さなくていいから」
なので、最後にお節介を一つだけ落としていく。
風邪でも引かれると何となく寝覚めが悪い、そう思ったから今まで頭上を覆っていた傘を差し出す。
彼女に受け取らせた、正しく言えば押し付けた周は、彼女の唇が動く前に背を向けた。
足早に離れると、背後から真昼の声がする。
けれど雨音にほぼかき消されるくらいに小さな声で、周はそのままさっさと公園の横を抜けていく。
まあ風邪引かないといいな、程度に押し付けたせいなのか、最初に無視して通り過ぎようとした罪悪感が少しだけ軽くなった。
彼女が会話を拒んだのだから、周はもう関わるつもりはない。
どうせ縁もないし、これっきりだ。
改めて帰路に就いた周はそう思っていた。その時は。

「
「お前こそうるさい」
翌日、風邪を引いたのは周の方だった。
級友、というよりは悪友である
代わりに鼻呼吸をすればずず、と水音がしてある意味鼻が鳴っている。
体調は最悪で、鼻がつまっているせいなのか風邪そのもののせいなのか、頭の奥からずきずきと痛みを訴えられていた。
市販の薬は飲んできたものの、完全に症状が抑えられる訳もなくこの
あー、と鼻づまりに顔を
「昨日まで元気だったろお前」
「雨に
「ドンマイ。つーか昨日傘持ってなかったっけ」
「……人に渡した」
流石に学校で
ちなみに真昼の方は学校でちらっと見た感じ顔色も悪くなく元気そうだったので、傘を渡した自分だけが風邪を引いて笑うしかない状況だった。
しっかり
「あんな雨降ってたのに貸しちまうとか、お
「しゃーねえだろ、渡しちまったんだから」
「わざわざ風邪引くリスク背負ってまで
「……通りすがりの迷子の子供?」
子供と言うには随分と立派な体つきをしているが。というかそもそも同い年なのだが。
(……ああそうか、迷子みたいな顔だったのか)
自分で言って、ようやくしっくりきた。
あの時の真昼の表情は、迷子の子供が親を求めている時のものにそっくりだったのだ。
「お優しいこった」
昨日の真昼の事を思い出している周の心情は知らず、樹はからかうように笑った。
「でもまあ、傘貸したにせよ何にせよ、お前その後適当に体
「……何で分かるんだよ」
「お前の不摂生具合はお前んち行ったらすぐ分かるわ」
だから風邪引くんだよバーカ、とさりげなくけなされて、周は口をつぐむしかない。
樹の言う通り、基本的に周はあまり自身の事に
もっと言えば整理整頓が苦手で部屋はぐちゃぐちゃだし、食べるものもコンビニ弁当か栄養補助食品、それか外食となっている。
よくそれで一人暮らしすると言えたな、と樹に呆れられるほどだ。
そんな生活を見ている樹からしてみれば、周が適当に過ごして風邪を引くのも頷けるだろう。
「今日はさっさと家に帰って早く休むんだな。土日あるし、さっさと治してこい」
「そうするわ……」
「せめて看病してくれる彼女でも居たらよかったのになあ」
「うるせえ。彼女持ちは黙ってろ」
ちょっと誇らしげに唇を
時が
頭痛と鼻水だけで済んでいた風邪の症状は、
それでもようやくマンションのエントランスにたどり着き、重たい足を動かしてエレベーターに乗った所で、壁にもたれる。
はー、とこぼれる息は平常より荒く、熱い。
どうやら学校では耐えていたらしいが、もうすぐ家につくという事で油断したのか、体が一気に不調を訴えかけてきていた。
エレベーターの独特の浮遊感も、普段なら平気なのに今は地味な苦痛になっている。
それでも、もう家につく。
自分の住まう階にエレベーターが止まり、周は緩慢な動作でエレベーターから降り、自分の部屋に足を向けて──一度固まった。
視線の先には、もうろくに話す事もないだろうと思っていた、亜麻色の髪をなびかせた少女が居た。
見たところ、
どう考えても彼女の方が風邪を引きそうだったのに、ぴんぴんしていた。普段から体に気を付けているか、如実に差を見せつけられている。
真昼の手には、昨日押し付けた傘がきっちりと畳まれて握られている。
返さなくてもいいと言ったのに返しに来たのだろう。
「……返さなくても、よかったのに」
「借りたものは返すのが当たりま、……?」
途中で言葉を切った、というより切れたのは、周の顔を見てからだ。
「あの。熱、ありますよね……?」
「……あんたには関係ないだろ」
最悪のタイミングで出くわした、と周は
傘は極論、返却されようがされまいがどっちでもよかった。
しかし、今のタイミングで会うのはよくない。賢い彼女なら、すぐに周が風邪を引いた理由にたどり着くだろう。
「でも、それは私に傘を貸したせいで……」
「
「関係あります。私があそこに居たからあなたは風邪を引いてしまった訳で」
「いいんだよ別に。お前が気にする事じゃない」
周としては、こっちが自己満足でやった事なのに気にされるのは、嫌だった。
しかしながら、真昼にそのままはいそうですかと放ってくれそうな様子はない。端整な美貌には
「……もういいから。じゃあな」
問答している方が周としては辛いので、無理矢理にでも真昼の追及と心配から逃れる事にした。
ふらりとよろめきながら雑に傘を受け取り、ポケットから
周が若干もたつきながら自宅の扉を開けた瞬間、体から力が抜ける。
ようやく家に入れる、と安心してしまったのが悪かったのだろうか、ふらっと後ろの柵に向かって体がかしいだのだ。
やべ、とは思ったものの、柵は頑丈でぶつかった程度で壊れる心配はないし、高さもあるので落ちる事もない。多少打ち付けようが痛いで済むから、まあ仕方ない……と痛みを覚悟した。
ところが、ぎゅっと腕を引っ張られて無理に体勢が元に戻る。
「……さすがに放っておけません」
か細い声が、少しぼんやりした意識に届く。
「借りは、返します」
熱が上がってきたのかぼんやりとしだした頭で彼女の言う事を
理解する前に、真昼は力が抜けかけている周の体を支えて周の家の扉を開けたのだから。
「入りますけど、致し方なくなので許してくださいね」
静かな
風邪っぴきの周は抵抗する気力がなかったので、引っ張られるまま、初めて同年代の女性を伴って帰宅した。
看病してくれる彼女は持ち合わせていないが、どうやら看病してくれる天使は居たようだ。
入れなければよかったと後悔したのは、熱でゆだった頭で遅れて自宅の現状を思い出した、というよりは実態を見てからだった。
周が住むマンションは、1SLDK。
広々としたリビングに寝室、おまけの納戸まであり一人暮らしには随分と
一人暮らしをするならここ、と決めたのは親なので文句を言うつもりはないのだが、別にそんな金かけなくてもよかったのでは、と思ってはいる。一人で住むには持て余す広さだ。
さておき、周は一人暮らしであり、そして整理整頓が苦手な男だった。
当然、リビングはおろか寝室まで物が散乱していた。
「目も当てられませんね」
天使様改め救世主様は愛らしい見かけによらず大変素直な言葉を周に贈呈していた。
実際ひどいので、周も何も言えない。他人を家にあげると分かっていたら多少は物を
艶やかな唇からため息をこぼした真昼は、それでも帰る事はせず周を寝室に運ぶ。
途中二人して転びかけたので、そろそろ
「とりあえず、
「……帰ってくるのかよ」
「放って寝込まれても寝覚めが悪いので」
以前ずぶ濡れの真昼に思ったような事を周にも思ったらしい真昼が素っ気なく返すので、周もそれ以上は文句も言えなかった。
真昼が部屋から出た後、大人しく言いつけ通りに部屋着に着替える。
「ほんとにぐちゃぐちゃというか、足の踏み場が……なんでこれで生活出来るのですか……」
着替えの最中困惑の声が小さく聞こえて、かなり申し訳なくなった。
着替えた後横になったらいつの間にか眠っていたらしく、重たい
その髪を辿るように視線を上げれば、どうやら夢ではなかったらしく真昼が周を
「……今何時だ」
「午後七時ですね。数時間寝ていました」
淡々と答えた真昼は周が体を起こすのに合わせて、コップに
ありがたく受け取り口にしたところで、やっと周囲に目を向ける事が出来た。
寝たからか、ほんの少し体調はマシになっていた。
頭がひんやりしている事に気付いたので額を押さえてみれば、布のようなすこしごわついた感覚が指先に返ってくる。
この家にある筈のない冷感シートが
この家には冷感シートもないし、なんならスポーツドリンクすらない。スポーツドリンクも彼女が持参したものなのだろう。
「……わざわざどうも」
「いえ」
素っ気ない返事に苦笑するしかない。
罪悪感からか看病を申し出ただけで、周と話したい、という訳ではないだろう。そもそも、ほとんど顔見知り程度の男の家で二人きり、といった状態で親しげに話せるとも思わない。
「とりあえず、机の上にあった薬はこちらに持ってきました。お
「ん、まあそれなりに」
「そうですか。じゃあお
「……え、椎名の手作り?」
「私以外に誰が居るというのですか。嫌なら私が食べますけど」
「いや食べます食べさせてください」
まさか看病してもらった上に手作りのお粥を用意してもらえるなんて露とも思っておらず、一瞬
正直真昼の料理の腕は未知数なのだが、家庭科の授業で失敗しただのなんだのそういう
即座に頭を下げて食べると返事した周に真昼はやや呆れた目を向けたものの、
「持ってきますから、熱を測っておいてください」
「ん」
言われた通りにシャツの前を開けて体温計を取り出したところで、真昼がばっと顔を逸らす。
「私が部屋を出てからにしてくださいっ」
声をほんのりと荒げた真昼を見れば、うっすらと
別に女子と違って男の
白い頰を淡く
(……あ、なんか周りの男が
周にとって真昼は確かに美少女だと思っているが、別にそれ以上の感想は浮かばなかった。
作り物の美を見ている、といったらいいのか。芸術品に近しいようなイメージで
しかしながら、今こうして
「……じゃあさっさとお粥取りに行けばいいのでは?」
「い、言われなくてもそうします」
ただ、素直に可愛いと言う間柄でもなかったし、言ったら確実に変な目で見られそうなので感想は飲み込んだ。
興味なさそうにそう言えば真昼はぱたぱたと足早に部屋を出ていく。

多少もたついていたのは、動揺からか、部屋の乱雑具合からか。恐らく後者だろう。
ぼんやりとそれを見送ってから、周は改めて何でこんな事になったんだか、とそっとため息未満の息をこぼした。
(……まあ、責任感と罪悪感からだろうな)
普通、よく知らない男の家に上がり込んで看病なんてしようとは思わないだろう。もし襲われでもしたら大事なのだから。
そのリスクを負ってまで看病を選択したのだから、よほど気に病んだらしい。それにプラスして、周の態度が明らかに興味がなさそうだったから、というのが安心させる要因だったのかもしれない。
何にせよ、真昼は割と仕方なく看病してくれている、というのは間違いないだろう。
「……持ってきましたけど」
少し熱で浮かされた頭でそんな事を考えながら待っていたら、遠慮がちに扉がノックされる。
どうやら服を整えたか心配だったらしく入ろうとしない真昼に、今更そういえば服緩めたのは熱を測るためだったな、と思い出した。
「まだ熱測ってない」
「私が居ない間に測っておくようにと言ったつもりだったのですが……」
「ごめん、ぼーっとしてた」
素直に謝って体温計を
ひょい、と持ち上げて画面を見れば、三十八度三分と表示されている。病院に行くほどではないが、それなりに高い数字だった。
服を整えてから
目に見えて
「何度でしたか」
「三十八度三分。薬飲んで寝たら治る」
「……市販の薬はあくまで対症療法であって、ウィルスそのものを退治してくれる訳ではないですからね。ちゃんと体を休めて免疫機能に仕事してもらってくださいよ」
ちくりとお小言をもらったものの、心配からだと分かるのでなんとなくくすぐったかった。
まったく、とため息をついた真昼はサイドテーブルにお盆ごと土鍋を置き、
中には、梅が入ったお粥。胃の負担を考えてか全粥ではなく水分量多目のようで、七分粥くらいだろう。
梅が入っているのは、味というよりは風邪によいと聞くからだろうか。
湯気はたっていないがほんのりと温かさは伝わってくるので、作りたてというよりは意図的に冷まされた、といったものだろう。
粥をじっと見つめる周をよそに、真昼は手際よくお椀にお粥をよそっている。軽く実をほぐしてくれていたが、種はご丁寧に取り除いていたらしく、あっさりと赤い身が白に混じり込んでいった。
「どうぞ。多分熱くはないですから」
「ん、さんきゅ」
受け取ったものの、スプーンを握ったままじっと粥を見る周に、真昼も
「……何ですか、食べさせろと言うのですか。そんなサービス承っていませんけど」
「誰も言ってないから。……いや、料理も出来るんだな、と」
「一人暮らししているんですから当たり前です」
ちゃんと自活出来てない周には、割と痛い言葉だった。
「藤宮さんは料理の前にまず部屋を片付けた方がいいですよ」
「ごもっともで」
大体考えてる事が分かったらしい真昼がすかさず
舌に広がるとろみのついた粥の味は、やはりというか米の味を生かして塩は控えめだ。
ただ、ほぐされた梅干しのまろやかな酸味と塩味が味を引き締めて丁度よいバランスに仕上げてある。
あまり周は塩辛い梅干しは好きではなかったが、ほんのりと甘さを感じるマイルドな酸味は好みの味で、健康であればそのまま白米に載せたり茶漬けにしたりしたいところだった。
「うまい」
「それはどうも。お粥ですから誰が作ってもそう変わりませんけどね」
澄ました顔で返した真昼だったが、微かな笑みが浮かんでいる。
学校でたまに見かける、外行きの笑顔とはまた違った安堵の含まれた
「……藤宮さん?」
「いや、なんでもない」
一瞬だけ浮かんだ柔らかな笑みがすぐに消えてしまったのは、なんだか
そう思いはしたが口にせず、周はまたも誤魔化すようにお粥をちびちびと口に運ぶのだった。
「……とにかく、今日は安静にする事。水分補給はしっかりしてください。あと汗拭くならこっちを。洗面器にお水を入れてますから、濡らして絞って拭いてくださいね」
食後、真昼はせっせと未開封のスポーツドリンクや水を張った洗面器とタオル、予備の冷感シートを用意してサイドテーブルに置いていた。
流石に顔見知り程度の異性の家に泊まる訳にもいかないだろうし、周としてもそれは居たたまれないので、その行動はありがたかった。
じっと周が見つめる中、真昼は不備がないか確認している。
(……義務感でやってるわりにはまめまめしいよな)
口はシビアで淡々としているのに、やっている事は
(
恐らく、もう彼女と関わる事もないだろう。たまたま縁で看病してもらっただけなのだから。
そう、もう彼女と接触する事はないのだから、一つ、気になった事を聞いてもよいだろう。
薬も効いてきたのか、倦怠感はあまり薄れていないが熱はすこし引いたように思える。思考が寝る前より覚めていた。
「なあ、聞いてもいいか」
「なんですか」
必要なものをセッティングした真昼がこちらに顔を向ける。
「なんで雨の中ブランコ
気になっていたのは、そもそも看病してもらうきっかけになった、昨日の事だ。
雨の中ブランコでゆらゆらとしていた真昼は、どうしてあそこに居たのか。
どこか、迷子の子供のような
しかし、あんな表情をする理由が分からない。
誰かを待っていたようにも思えたから、当てずっぽうで付き合っている男がいて揉めたんじゃないか、という安直な予想だったのだが、真昼は呆れたようにこちらを見ている。
「生憎と、彼氏なんて居ませんし作る予定もありません」
「は? 何で?」
「逆に
「あれだけモテてればそりゃ一人や二人居るかと」
こうしてやり取りをしている周にとっては、割と人間味に
その上で成績は首席をキープ、スポーツも万能、おまけに今日知ったが料理も恐らく
言い寄られているのはチラッと見たことがあるし、級友の結構な数が真昼に好意を持っているのも知っている。
だからこそ、より取りみどりの状態で誰とも交際していないなんて、思わなかった。
そういった意味での一人や二人という表現なのだが、その言葉を聞いた瞬間、真昼の表情が
「居ませんし、何人もの男性と交際するほど節度のない人間になった覚えはありません。絶対に、ありえないです」
ゾッとするほど冷えた
風邪を引いているせいなのかもしれないが、一瞬悪寒がした。心なしか部屋が肌寒く感じる。
「ごめん、そういうつもりじゃなかった。謝る」
「……いえ、こちらこそ熱くなってすみません」
ただ、頭を下げればすぐに冷えた空気は霧散した。
熱くなったというよりは空気が
「とにかく、あの時のはそういった
「いいよ。別に、俺が勝手にした事だし。実際、俺が勝手にしただけだから、罪悪感とか抱かれても困る。
やはりというか罪悪感で看病したらしい真昼は、周の言葉の後半を聞くにしたがって
関わるのがこれっきり、というのが気になったのだろう。
「特に接点ないし当然だろ。いくらお前が学年一の美人だの才女だの天使だの言われてるからって、どうこうするつもりはないよ。恩に着させてあわよくば、とか考えてると思ったか?」
ちょっと気まずそうに目を逸らした真昼に、やっぱりかと苦笑が浮かぶ。
これは、本人が自意識過剰というよりは、実際にそういう事があったのだろう。
美少女に恩を売って関わりを持とうとする、というのはあり得る手法である。
そういう事を幾度か経験しているらしい真昼が、あの雨の日に警戒したのも頷ける話だ。自衛のためなのだから、責められた事ではない。
「めんどくさいだろ、お前だって。好きでもない男に構われるの」
「それはそうですが」
「やっぱりか」
本人が肯定した事が、ちょっと面白かった。
大人しく優等生で愛らしい天使と騒がれる彼女も、やはり好き嫌いはあるし
真昼としては失言だったようで、失言を引き出した周をほんのりと恨みがましげに見ていた。
それが何より、真昼がちゃんと感情のある人なのだと証明している。
「別にいいと思うぞ? むしろ安心した。天使も人並みにそういうのは迷惑なんだなって」
「……
どうやら天使と呼ばれているのは恥ずかしいらしく、不服そうな眼差しが継続している。
それも面白くて、周はまた笑った。
「まあ、だから用事もないのに、わざわざ関わる事はないよ」
そう言い切れば、真昼は少しだけ驚いたように目を丸くして、それからほんのりと苦笑を浮かべた。
ぺこりと頭を下げて帰っていった真昼の事を思い出しながら、周はベッドでぼんやりと
薬は効いていたものの、やはりというか体はまだだるいし気を抜けばすぐに睡魔に引きずられるだろう。
瞳を閉じて、今日あった事を思い返す。
天使(毒舌系)に看病されたなんて、誰に言っても信じないだろうし、言う事でもない。
今日あった事は、周と真昼だけの秘密だ。
秘密、というと妙にくすぐったく感じてしまう。ただ面倒だから他人に言わない方がいい、という判断なのに。
翌日からは、顔見知りの他人。
そう言い聞かせて、周はゆっくりと意識を沈めた。

宣言通り、
看病された翌日には元気になっていて、コンビニに買い出しに行く際にたまたま真昼と顔を合わせたが、特に話す事もなかった。ただ、真昼が元気そうな周の姿に少し
週明けで学校が始まっても、変わらない。他人のまま。
ただ、少しだけ変化があったとすれば、通学の時に出会えばぺこりと
「おー周元気になったか」
「お陰さまでな」
先週の帰り際は半分死んでいた周を
問題ないという旨のメッセージを送っても半信半疑だったようで、こうして実際会ってピンピンしている様子を見て樹はわざとらしく安堵した風に息を吐いた。
「いやー、あんだけ体調悪そうにしてたらそりゃオレだって心配になるわ。まあ治ったんならいいけどな、お前もう少しまともな生活しろよ。まず片付けろよ」
「どっかの
「ん?」
「いやなんでも。……この土日で思い知ったから、近々片付けるよ」
いや今すぐ片付けろよ、とすぐに突っ込まれたものの、
あれは恐らく、半日では片付かない。
ぷい、とそっぽを向いた周に樹も追及こそしなかったが、
「ま、お前んちだから好きにすればいいけどさ。今度行く時は足の踏み場ぐらい作ってくれよ」
「……善処する」
渋い顔をしつつ
窓から
話しかけられれば静かな
その様子を見た樹も同じように視線を滑らせて、真昼の姿を
「ああ
「何たって天使様だからな。……樹も椎名を
「そりゃまあな。ただ、オレにはちぃが居るから、単なる鑑賞用って感じだけど」
「のろけは結構ですー」
樹にはちぃ、正確には
これまた相思相愛の非常に仲むつまじいカップルで、一緒に居る姿は見ているこちらが胸焼けしてくるほどだ。
のろけはほかのところでやってくれ、とひらひら手を振った周に、樹は気分を害した様子はない。いつもの事なので「つれないやつめ」と笑っている。
「周こそ、椎名は可愛いとは思わないのか?」
「美人だな。それだけだ」
「淡白だな」
「
「違いない」
何の因果か先日は看病してもらうというハプニングがあったが、元々住む世界が違うのだ。
周が真昼と仲良くなる、なんて未来なんてありはしない。優秀な人間は優秀な人間と
自分でも駄目男の自覚がある周と、可愛らしく何でも出来る真昼がどうこうなる事なんてまずないのだ。
そう、関わる事自体もうないと思っていたのだ。
「……何食べてるんですか」
それが覆されたのは、ベランダでゼリー飲料を飲みながら外を眺めている時だった。
コンビニに寄るのも面倒で、家に常備しているゼリー飲料を吸いながら柵に体を預けて外の空気を吸っていたら、たまたま真昼がベランダに出てきた。
周の姿を見つけた真昼は同じようにベランダの柵から少し顔を出して、それから周が口にしているゼリー飲料を見て
周としては、まさか話しかけられるとは全く予想しておらず、しばらく
「見れば分かるだろ。僅か数十秒でエネルギー補給出来るゼリー」
「……まさか晩御飯だと言いませんよね?」
「そうに決まってるだろ」
「食べ盛りの男子高校生がたったそれだけ?」
「余計なお世話だ」
普段はコンビニ弁当やらスーパーの惣菜を食べているので、ここまで軽食ではない。今日は晩御飯の調達を怠ったしカップラーメンの気分でもなかったのでこうしたゼリー飲料を飲んでいるだけである。
恐らくこれでは足りないので、後にスナック菓子か何かをつまむ事になりそうだが。
「料理は……聞くまでもないですね。料理出来なさそうですし。料理も掃除も出来ないのによく一人暮らししてますね……」
「うるさい。関係ないだろ」
ちくりと刺された事は事実なので、やや眉が寄った状態で飲み残していたゼリーを吸いきる。
掃除云々については先日思い知らされたのでどうにかする予定なのだ。とやかく言われると逆にやる気が
「……待っていてください」
そう言うや
カラカラと窓が閉まる音を聞きながら、周は「一体何なんだ」とこぼす。
待っていろ、と言われても何を待てと言うのだろうか。
(そろそろ冷えてきたし中に入りたいんだが)
待てと言われて一応待機しているものの、秋の夜は思ったよりも冷えるのだ。スウェットでは肌寒いものがある。
そもそも何故律儀に待っているのか、自分でも分からなかった。
その内息が白くなりそうな気温の中深く息を吐くと、玄関の方から電子音が響く。
来客を知らせる音に振り返った。
来客の心当たりなんて、一人しかない。
本当に何故なのか分からず、散乱した服や雑誌を避けて歩きながら玄関に出る。
覗き窓から見ずとも誰か分かるので、サンダルを足に引っかけチェーンを外してドアを開ければ──予想通り、周の目線より低い位置に亜麻色の髪が揺れていた。
「……何してんのお前」
「あまりにもあなたが不摂生すぎて目に余ったんです。……残りですけどどうぞ」
つん、と素っ気ない声と共に、真昼は手を前に出す。
周よりも一回りは小さく
まだほんのりと温かいのか、僅かに蓋が曇っているため何となくでしか分からないが、おそらく煮物だろう。
ぱち、と瞬きを繰り返すと、何故だと問いたい周の眼差しを理解したらしい真昼からは深いため息が返ってきた。
「あなたがちゃんと食べないからです。栄養補助食品は補助であってそれを主食にしてはいけません」
「おかんか」
「私の主張は一般的だと思いますけど。あと、部屋は整理整頓しておくべきでは? 足の踏み場なかったんですけど」
ちら、と周の後ろを見て分かりやすく呆れたように
「……多少はある」
「ないです。普通床に服は落ちてません」
「落ちるものなんだよ」
「洗って干して畳んで仕舞えばなりません。雑誌は読まなくなったらまとめて縛る。踏んで滑って転んだら大事なんですからね」
言葉にはほんのりトゲがあるような気がしなくもないが、真昼は何故か純粋に心配してくれている、というのも分かるので、全部突っぱねる訳にもいかない。
そもそも、看病の時も部屋の雑多さに一緒に転びかけていたので、言われても仕方ない。
ぐぬぬ、と表情を
じわりと掌に伝わってくる
「で、これ食べていいのか」
「要らなければ処理しますけど」
「いやありがたくもらうよ。天使様の手料理なんて普通食えないだろうし」
「……それやめてください、本当に」
意趣返しとばかりにからかうように学校での通称を呼べば、分かりやすく白い
本人的には、天使と呼ばれる事は恥ずかしくて仕方ないらしい。周もその立場になれば間違いなく嫌なので、当たり前と言えば当たり前なのだが。
頰を紅潮させてちょっぴり涙目で恨みがましげに見上げてくる真昼の姿に、周はつい笑みをこぼした。
「ごめんって、もう言わないから」
これ以上は確実に機嫌を損ねるのが明白なため、あまりからかうのもよろしくない。そもそも、そこまで親しくないのだからやりすぎはよくないだろう。
真昼もこれ以上言われたくはないらしく、こほんと
微妙に頰は赤いので、あまり変わった風には見えなかった。
「まあ、これはありがたくもらうけどさ。別にあの時の事は気に病まなくていいんだぞ」
「別に、あれは看病で相殺しました。これは、私の自己満足というか……あまりにもあなたがロクな生活をしていないのが見えて、気になっただけです」
「さようで」
情けない姿しか見られていないので、そういう判断がなされるのはある意味当然なのかもしれない。
今も周の後ろでは色々と転がった廊下が見えているだろうし、看病でうちに上がった時に
「……ちゃんとご飯食べて、規則正しい生活をするのですよ?」
「おかんか」
大
もらったおすそわけを手に家に戻った周は、スーパーでもらった割りばしを用意してリビングのソファに腰かける。
真昼に押されてもらったが、果たして味はどうなのだろうか。
お粥は
恐らく、あれを食べた限り真昼は料理も
若干の期待と
幾つかの根菜と鶏肉が炊かれたものだ。煮汁の色はやや薄めで、鮮やかな人参の色や飾られたさやいんげんがよく映えていた。
一口大にサイズを合わせて切られた
早速と割りばしを手早く割って、まずは大根を口に運ぶ。
「うま」
味の是非は、すぐに出た。
健康志向な真昼らしく、味付けはやや薄めでだしを効かせた味付け。それも市販の顆粒だしではなく、きっちりと鰹節と昆布から取ったものだろう。旨味が全く違う。
野菜の旨味を生かしつつ味を整えてあり、しっかり中まで味の染みた煮物は、あまり好き好んで野菜を摂取しない周でも非常に美味しくいただけるものだった。
野菜をメインに食べなさい、と言わんばかりにやや控え目に入った鶏肉もぱさつきは一切なくふっくらとした仕上がり。量以外文句の付け所がない。
女子高生が作るには
料理を覚えたての人が作るものとはかけ離れた味と言えよう。
これに米と味噌汁かすまし汁があれば尚よかったのだが、
今更ながらに、レトルトのご飯パックでも買っておけばよかったと後悔していた。
「すげえな天使」
勉強も運動も家事全般も
「これ返す。うまかった」
翌日の夜、周は借りていたタッパーを持って真昼の家を訪問していた。
周は確かに家事が苦手ではあるが、洗い物が出来ないほどでもない。念入りに洗って乾かした上で返すのが礼儀だろう、ときっちり洗浄したものを携えている。
チャイムを鳴らされた時点で周だと予想していたらしい真昼は、誰かと
ボルドーのニットワンピース姿の彼女は周の姿を認め、
ちらりとタッパーを確認して「ちゃんと洗ったんですね、えらいです」と子供を褒めるように言われたので周は思わず眉をほんのり寄せた。
「わざわざありがとうございます。じゃあどうぞ」
真昼がタッパーを回収した、そこまではよかったのだが、今度はひょいと別のタッパーが周の手に載せられる。
やはりというかほんのりと温かい。
中身は恐らく豚と
色からして、炒めたタレは恐らく味噌味。ほんのり
美味しそうだとは思う。
思うが、何故また渡されたのかが分からない。
「いやあの、タッパー返したんだけど」
「今日の晩ご飯です」
「うん分かるけどな」
「一応聞きますが、アレルギーないですか? 好き嫌いは受け付けませんが」
「ないけどな? いやまたもらうのは」
二日連続晩ご飯をおすそわけしてもらうというのはどうなのだろうか。
栄養が片寄っている身としてはありがたいし、なにより真昼の料理の腕前は同年代の女子より
きっとこのタッパーの中身も美味しい筈だ。
ただ、これが同じ学校の人間に見られていたら大惨事になりそうだ。もちろん周の平穏な学生生活が、という意味で。
このマンションは一人暮らし向けではあるが、設備や立地的に家賃がお高め。真昼以外に同じ学校の生徒は見た事はないので目撃に関しては心配要らないだろうが、それでもこういった関わりを持つのはやはり少し躊躇われる。
「一人だと作りすぎますし、もらってくれたらありがたいです」
「……そういう事ならありがたくもらうけどさ。普通こんな事してたら、相手が好意持たれてるんじゃないかと勘違いするぞ」
「しますか?」
「いーや、ないな」
そもそも、真昼のような美貌の才女がだらしないと最近痛感してきた周のような男に好意を向ける事が想像出来なかった。
確かに、可愛い隣人からおすそわけしてもらう、なんてラブコメ漫画のような展開なのかもしれないが、互いにラブはないし、会話にコメディさの
あるのは、天使様の言葉のトゲと哀れみからの温情くらいだ。
「じゃあ問題ないでしょう。どうせあなたはコンビニ弁当とスーパーの惣菜で済ませてそうですからね」
「何故分かる」
「どう見てもキッチンがろくに使われた形跡がなかったですし、コンビニやスーパーの割りばしが机にたくさんありましたからね。あとあなたの様子で考えなくても分かります。それに不健康そうな顔ですし」
家に一度あがった時に見ただけでそれだけ見抜いてくる真昼には周も頰をひきつらせたが、本当に的確に当たっていたので何も言えなかった。
「……じゃあ、私はこれで」
ぺこ、と言うだけ言って渡すだけ渡し、真昼は家の中に戻っていく。
じゃらりと扉の内側でチェーンのかかる音を聞きながら、周は受け取ったタッパーを見る。
掌の中でほんのりと温もりを伝えてくるおすそわけに、そっとため息をこぼして周も自宅に戻った。
いただきものの茄子と豚肉の胡麻味噌炒めはやはり美味しくて、米が無性に欲しくなった。
結局のところ、毎日タッパーを引き換えるごとに中身の入ったタッパーが手に渡るため、周の食生活は劇的に改善されていた。
真昼の料理は、味付けは濃くはないがどれもこれもご飯が欲しくなるため、晩ご飯にはレトルトのご飯を用意して一緒に食べるようになっている。
料理自体は和洋中なんでもござれなのかジャンルは様々なものが毎日代わる代わる詰められていたが、どれもこれも美味しいので非常に食が進んで
毎日もらえると期待するのは悪いしおこがましいのだが、
天使の料理は依存性が高いのかもしれない。悪いと思いつつも素直にタッパーを受け取ってしまって、つい舌鼓を打ってしまう。
「……最近顔色いいな。食生活見直したか?」
晩ご飯でいくらか栄養を補給しているせいか、顔色もよくなったらしく、昼食時に樹がまじまじと見つめてきた。
学食で頼んだうどんをすすっていた周は、相変わらず鋭い樹に少し冷や汗をかく。
「樹、俺はお前が怖い」
「なんでだよ。つーか図星?」
「いや……まあ、見直さざるを得なかったというか」
真昼がマンションですれ違う度にちゃんとしなさいと軽くお説教をするし、晩ご飯のおすそわけがあるので、自然と生活自体の質が向上したのだ。
天使さまさまと言いたいところではあるが、ちょっぴり余計なお世話だという感情もあったりする。
若干口を濁しつつも肯定した周に、樹はさも愉快だとけらけらと笑っていた。
「そりゃそーだろな。お前不健康そうな面だし実際生活習慣くそみたいだからな」
「うるせえ」
「しかしまた、なんで見直そうと?」
「……強制的に?」
「ははあ、母親にでもばれたか」
「……当たらずも遠からずだな」
真昼のあの口ぶりはおかんといった表現に近い。
おかんというにはあまりにも若々しい上に可愛らしいが。何故かせっせと世話を焼いてくれる真昼の事を拒絶する気にはなれなかった。
「なあ樹。俺ってそんな不健康そうか?」
「おう。元々色白ってのがでかいな。あと背は高いがひょろいし、やる気無さそうな顔してるし、面構えが不健康って感じだ」
「顔は元からだ」
「知ってる。もっと生気に満ちた顔したらどうだ」
「無茶言うなよ。……そうか、死んだ顔してるのか……」
自分の顔なんてあまりまじまじと鏡では見ないものだから分からなかったが、他人にはあまり生気がないように映るらしい。
もしかしたら、周の普段の表情が死にかけに見えたから、真昼も心配したのかもしれない。
「周はもう少し周囲の見る目を気にするべきだろ。いつも視線が下がってるし雰囲気がとっつきにくいし、そもそも人寄せ付けようとしてないし。パッと見は根暗そのものだぞ」
「さりげなくけなしたなお前」
「いやー飾らないから
これを機に少しは健康と一緒に身だしなみに気を使えよ、と樹からもお節介の言葉をいただいたので「余計なお世話だ」と返して、周はそっぽを向いた。

「あ」
鈴を転がすような声が、背後から聞こえる。
最近は聞きなれてきた声ではあるものの、ここはマンションではない。近所のスーパーマーケット、その菓子売り場である。
一応人の目がある場所で彼女が
手にはスーパーのかごが
菓子売り場にふらりと立ち寄ったところで周と遭遇した、そんなところだろう。
「言っておくが、たまたまだ。尾行してる訳じゃないからな」
「知ってます。最寄りスーパーが互いにここな事くらい分かりますので」
先んじて言えば「むしろ何でそういう発想になったのか」と
きっちりと必要なものを書き留めているのは
しょうゆとみりん、と
「みりんはこっちだぞ。ほら」
「あ、そっちじゃなくてみりん風の方です。未成年じゃ買えないですから」
「これ酒扱いなのか」
「甘いお酒扱いですからね。料理酒は塩を添加して飲用ではなくしてるので未成年でも買えますけど」
みりんを渡そうとすればそう言って首を振り、みりん風調味料をかごに入れている。
「……大特価お一人様一本限り……」
予備も買おうとしていたらしい真昼が残念そうに
「買えばいいのか」
「話が分かる人で助かります」
彼女の言わんとする事は察したので苦笑しつつ醬油のボトルを手に取れば、満足げに唇がほんのりと弧を描いた。
「……案外節約するんだな」
「節約、というよりは安く済むなら済ませるだけです。無駄があれば省くでしょう」
「日本人らしい気質というかなんというか。……ま、親からの仕送り生活ならそうだわな」
周も一人暮らしといえど、親に養ってもらっている。
割と裕福な家庭に生まれたからこそああいう
学費もあるし仕送りもそれなりにかかるので、なるべくではあるが無駄遣いは避けていた。
「……そうですね。養ってもらっているのですから、節制は大切です」
真昼は淡々と返してかごの中身を整理している。熱を奪ったような冷えた声だった。
一気に
一瞬だけ
「……ところで、あなたそれ買うんですか」
話を変えるように、真昼は周の持っているかごに入っていた真空パックの米飯とポテトサラダを見て問いかける。
真昼から分けてもらう料理はもちろん
「晩飯だからな」
「不健康」
「やかましい。サラダ買ってるだろ」
「ポテトサラダですけどね。……どうしてその生活で体を壊さなかったのか……」
「大きなお世話だ」
もっと野菜を食べるべきでは、と瞳を
何だかんだちょこちょこ話しつつも会計が済んだのでレジ袋に買ったものを詰めるのだが、真昼は
実に環境的で庶民的な天使様である。
しかし、詰めるのはいいが、量が多すぎるのではないかと少し不安になった。
牛乳に醬油、みりん風調味料の時点で四リットルはあるので、水と比重は違うだろうが確実に四キログラムはあるだろう。その上で食材、それも大根一本丸々買っているのだから、まあ重い
綺麗に詰め込んでまとめているが、これを手にしてマンションまで帰るのは地味に重労働なのではないか。
(結果的に
恐らく、いつもより多目に作った上で分けているのだろう。いつも分けてもらう分は普通に一食分に近いので、多く作りすぎるからとは言っていたが、最近はわざと多く作っている筈である。
結果的にかなり世話を焼かれているので、さすがにここでなにもしないというのは男が
詰め終わったところでエコバッグの持ち手を
真昼も運動はかなり出来るようだが、純粋な腕力とはまた別だろう。服越しでも分かるほっそりとした二の腕に力を求めるのは無理な気がするのだ。
周の行動に、ぱち、とカラメル色の瞳が瞬く。
驚いたようにも、感心したようにも見えた。
「……別に奪おうってわけでは」
「それは心配してないです。……別に、それくらい持てますよ?」
「こういう時くらい素直に甘えといた方が可愛げがあるぞ」
「まるで可愛げがないという言い方」
「学校での態度と俺に対する態度を比べてから言え」
それは自覚しているのか、真昼がややたじろいだ。
学校で見せている、
正しく言えば、周にも優しくはあるが、言葉が端的と言えばいいのか。彼女の中では周用のオブラートの在庫はないらしい。いつだって
真昼が口をつぐんだのを好都合と見た周は、たくさんの食料品が詰まったエコバッグと自分の荷物を手に、すたすたと出口に向かう。
後ろで慌てたような気配がしたが、周は構わなかった。距離が空こうがお構いなしに進む。
彼女の歩幅に合わせて待ってやりはしない。
ただでさえスーパーでは
互いに、この距離が一番都合がいいのだ。
無関係を装って大きな荷物を携え先を急ぐ周の背中に、小さく「……ありがとうございます」と声がかけられた気がした。

料理は、
加熱して胃に収まればいいだろ、という考えの下、非常に見かけが悪く味も残念なものであれば、全く作れないという訳ではないのだ。
洗濯はそもそも出来なければ生活に困るので問題はない。いざとなればコインランドリーという手段もあるし、洗濯機に入れて洗剤と水と共に回すだけなので問題なくこなしている。
ただ、掃除だけは周にはどうしようもなかった。
「どうしようか」
休日、
自分が悪いとは分かっているのだが、
取り敢えずシーツは洗って
ここからどう掃除したらよいのか。
服やら雑誌やらが散らばっているので、割と足の踏み場がない。
不幸中の幸いで、食品関連のごみは流石に
その散らかりがひどいから困っているのだが。
そっとため息をついた時、玄関のチャイムが鳴った。
あ、と声がこぼれる。
もう慣れた来訪者、というよりは渡すだけ渡して帰っていく天からの恵みであり配達人のような存在だが、今この時は救世主のように思えた。
足早に玄関に向かおうとして、足場のなさにすっ転びそうになって壁に手をつきつつ、ドアを開ける。
「すみません、ちょっと先にタッパー回収し……なにやってるんですか」
「……掃除しようとしてた」
体勢を崩しつつ真昼に顔を見せれば、微妙に
「今すごい音したような」
「……転びかけた」
「でしょうね。掃除、始まってすらないですよね?」
「途方にくれてた」
「でしょうね」
これだけひどければそうもなります、と相変わらずの
それに、ここでふて腐れて彼女を突き返せば、掃除の取りかかりの相談すら出来なくなる。
しかしながら、どう聞いたらいいだろうか。
掃除のコツを聞くつもりではあったが、そもそもアドバイスをくれるだろうか……とやや躊躇いつつ真昼を見たら、真昼は周の背後、散らかった廊下を見ている。
後ろの惨状にうわぁ、と眼差しが語っているので、真昼からしてみれば余程ひどいのだろう。
「全く。……部屋、掃除させてください」
「は?」
周としては、手伝ってほしいとかそういった願いは厚かましすぎるので何か助言をもらうつもりだった、のだが。
まさか、真昼が直々に手伝うなんて申し出るとは思わなかった。
「隣が汚部屋だと思うと嫌です」
別に彼女の言動がやや
「家事が出来ないのに一人暮らしとか
ぐうの音も出ない。
母親にもこまめにしておけば楽だからね、と言われて放置した結果がこれである。完全に自業自得だとは自覚していた。
「大体ですね、普段からこまめに掃除していればこんな事にはならないのに。
「……
ここまで言われて怒りもしないのは、そもそも真昼には非常に世話になっていて頭が上がらない上に、的確に周の心情と過去の行動を当ててきたからだ。
何とかなるだろう、とたかをくくってこうなったのだから、最早周には彼女の言葉に
「掃除していいですか、この部屋」
「……お願いしてもいいですか」
「私が持ちかけてるんですから当たり前でしょう。あと、私は準備してきますから、その間に隠したいものや貴重品は納戸に持っていって
「そこは心配してない」
なにが悲しくて、言葉は鋭いものの親切心で手伝ってくれる人間に盗難の心配をしなくてはならないのか。
そもそも、これだけ常識的で世話焼きの真昼が他人に危害を加えるなんてまずないだろう。
「……あなたは心配してないんですか?」
「お前がそういう事するなんてまずないだろ」
「いえそうではなくて……ですから、男性的に隠しておきたいものが見られる心配はしてないので?」
「
「まあ、それならいいのですが。じゃあ、着替えて掃除道具持ってきますので。……徹底的にしますからね、掃除」
肩を
再び自宅を訪れた真昼は、先ほど会った時の服装とは違い、白のロングTシャツにカーキ色のカーゴパンツといった姿だ。
体にぴったりと沿うようなTシャツは、
長い髪は器用に真ん丸のお団子にしてまとめあげていて、白いうなじが見えているのが妙に居心地悪かった。
普段ワンピースやスカート姿ばかり見ている身としては、何だか新鮮に見える。
こういったボーイッシュな服装はあまり合わないんじゃないか、と思っていたが、それは間違いだった。美人は何でも着こなすし似合う、というのを痛感させられた。
ただ、確かに動きやすそうではあるが、普通に外を出歩ける格好だ。それが汚れていい服装なのかは分からない。
「汚れていいのかそれ」
「どうせ近々捨てる予定があったので、別に汚れてもいいものですよ」
と言いつつ真昼は、改めて周の部屋の惨状を眺め、そっと嘆息。
「言っておきますが、徹底的に、しますよ?」
「……分かってる」
「分かってるなら早速しましょうか。私は甘くないですよ、妥協なんてさせませんから」
いいですね、と有無を言わさぬ声で問いかけられたので、周は「ハイ」と従順に返事をするしかない。
こうして、天使によるお掃除大作戦が幕を開けた。
「取り敢えず服は洗濯かごに放り込んでおきましょう。本来掃除は上から下の順でするのですが、これは掃除機をかける以前の問題です、折角のフローリングが物で隠れていますし。服は洗うにしても小分けがいいですね、多すぎます。あとこれ着ているもの着ていないもの区別つくんですか。全部洗っていいですか」
「もう好きにしてくれ……」
当たり前と言えば当たり前だが、掃除機をかけようにも床の上が物だらけなので先にそれを片付けるところから始まった。
「……下着とか落ちてないですよね?」
「それは流石にタンスに入ってる」
「ならよろしい。取り敢えず服は後回しでいいでしょう、洗って干すにしても掃除で
「ハイ」
「……で、雑誌ですけど、基本的に処分です。集めているならまた別ですけど、この扱いだとそうでもないでしょうし。必要ならそのページをスクラップにしてあとは処理。
早速掃除に取りかかっている真昼は、周には落ちている服を洗濯かごに入れる事を指示しつつ、雑誌を片っ端から積み重ねている。
必要な雑誌があるなら今の内に申し出る事、と言われて特に必要としていないので首を振る。真昼はそれを見て持参したらしいビニール
「服を集め終わったら他の雑貨類の取捨選択お願いします。落ちている雑貨類も同様に必要なものとそうでないものは分別してゴミに。いいですね」
「……おう」
「
「いや、ないけど……テキパキしてるな、と」
「しないと時間ないでしょう。ぐちゃぐちゃなんですから」
「ごもっともです」
休日とはいえ時間は限られている。掃除機をかけるなら近所迷惑を考え日中にするしかない。
その掃除機をかける前段階でかなりの労力がかかると分かっているので、真昼はなるべく急いで片付けに取りかかっているようだ。
ここまでさせてしまって申し訳ない、と思う反面、真昼の采配によってみるみる内に足の踏み場が出来ていくのだから、本気で感心もしていた。
「
「師と
「イエッサー」
「私を男にしないでください」
さりげなく突っ込んだ天使様は、真顔のまま鮮やかな手さばきで出来うる範囲のものの分別
どうしても物を取っておく
他人の部屋ではあるが遠慮なく片付けていく真昼は、実に家庭的で最早主婦並みの動きをしている。
真昼一人でも余裕でこの部屋は片付けられそうなほどに手際がよい。
ただ、急いでいるが
これは間違いなく周のせいなのだが、置いてあった服を踏んでしまったらしく、そのまま真昼はバランスを崩した。
真昼の口から「あ」と声が
ふわりと香る甘い匂い。それに
「……
真昼が顔を上げて、微妙に呆れたような視線を向けてきた。怒ってはいないようだが、色々と物言いたげな様子だ。
「転んだ私が悪いのは認めますが、こういう事があるから片付けをするべきだと」
「誠に申し訳ありません、反省しております。……怪我はしてないな?」
「平気です。わざわざ受け止めてくれてありがとうございます。こちらこそすみません」
「いや
ただでさえご飯を分けてもらっていてあまつさえ掃除も手伝ってもらっているというのに、それが原因で怪我でもさせたら目も当てられない。
というか申し訳なさすぎて顔も合わせられなくなるだろう。
望むなら土下座まで視野に入れているのだが、真昼は転んだ事については責めるつもりはないらしい。
「こんな事がないように片付けるんですからね?」
「存じてます。本当に、申し訳ありません」
「……いやそこまで言わなくてもいいです。私が勝手に手伝ってるだけですし」
ちょっとだけ慌てるようにこちらを見上げてくる。
図らずももたれたような体勢から至近距離でのやや不安げな
ただでさえあまり女に縁がない周にはこういった距離は心臓に悪いというのに、美少女と密着しているのだ。
いくら双方に恋愛感情がないとはいえ、なんというかとてもよろしくない気がした。
真昼がこの体勢を意識していないようなので、周はそっと肩を
「……続き、するか」
「そうですね」
幸いな事に、真昼は周の動揺には気付かなかったらしく、周が差し出した手を素直に摑んで立ち上がる。
真昼はくっついていた事は全く意識していないようで、いつも通りの表情を見せていた。
周としては、まあ真昼のような数多の男に好意を寄せられている少女がこれくらいで動揺する筈もないか、という事で納得は出来たのだが。
平然としている真昼に苦笑して、周も真昼に任せきりでは悪いと気合いを入れて掃除を再開するのだった。
「……びっくりした」
周も慣れない掃除に四苦八苦していたからだろう。
小さく
「……ふぅ、
結局のところ、周の家を掃除するのに一日費やす羽目になった。
床の私物を片付けるのに数時間、それから服の洗濯や棚の上や照明の埃取りやら窓拭きやら掃除機をかけたりしていたらすっかり日も暮れていた。
真昼がやって来た時に見えた太陽はすっかりと姿を隠していて、二人の奮闘がどれ程の時間続いたのか証明している。
ただ、お陰で周の部屋は見違えるように綺麗になっていた。
床には余計なものは落ちておらずフローリングが露になっているし、窓ガラスやサッシには汚れ一つない。照明も埃が取り除かれ以前より明るさが増している。
周の部屋も掃除したが、床に物が落ちていないのでゆったりと
「ここまでまる一日かかるとは」
「そりゃああれだけぐちゃぐちゃならな……」
「あなたがした事ですけど」
「仰る通りです」
天使様兼救世主様には頭が上がらないので態度だけは平伏しつつ、ここまで尽くしてくれた真昼をちらりと見る。
わざわざ貴重な休日を費やしてくれた真昼は、まったく、とゴミ袋を縛っていた。
この後彼女に更に夕食を作らせる、というのは気が引けた。
こちらにおすそわけがあろうがなかろうが、疲れているのに更に動かさせるというのが申し訳なかった。
「夕食はもう買い物行く気にもならないし、ピザでも頼むか。さすがに今日は
「え、でも」
「俺と食うのが嫌なら一枚頼んで持って帰ってくれ」
一緒に食べたくない、というのならそれはそれで仕方ないので一枚持ち帰ってもらえばいい。
一緒に食べたいというよりは
「……そうではないですけど。ピザとか、頼んだ事ないから驚いただけで」
「え、ないのか」
「だって、一人なのにピザ頼む事なんてないですし……作る事はしますけど」
「作るという発想に至るのはすげえわ」
普通はピザ食べたい、と思ったら市販品を買うか出前を取るか、もしくは外食をするかの三択になる筈だ。わざわざ生地から作ろうなんて手間のかかる
「別に出前とるなんて変じゃないだろ、俺普通に一人で頼むし。あれか、ファミレスも一人で行くの無理系か」
「そもそも行った事ないです」
「そりゃ珍しいな。俺は普通に一人でも行くし、うちの親は手抜きしたい時はファミレス行くけど。お前の親は外食しない派だったのか」
「……うちは、お手伝いさんがご飯作ってたので」
「お手伝いって、結構な金持ちだな」
富裕層の人間と言われたら、納得する。
やけに所作が綺麗だったりしたし、服や持ち物も上等なもの。
品がある雰囲気や教養のあるところを見る限り、むしろそうであっておかしくないといった感じだ。
その本人は周の言葉にうっすらと
「そうですね、比較的裕福だと思いますよ」
余計な事を言ってしまった、と後悔したのは、真昼の笑みが喜びでも自慢でもなんでもなく、むしろその笑みは、
以前も親の話をしたらどこか冷えた声で返されたし、恐らく親との折り合いがよくないのだろう。
あまり触れてはいけない部分らしいし、これ以上周も知ろうとは思わなかった。
人間、知られたくない、触れられたくない事の一つや二つあるのだ。ノータッチでいるのが、さほど親しくもない相手に対する礼儀だろう。
「まあ、いい経験になるんじゃないのか。ほら、好きなの頼め」
親の話題には触れずに、しまってあったピザの広告を真昼に見せる。
周もちょくちょく頼んでいる店であり、宅配サービスをしている店の中では知る限り一番美味しい店だ。
ピザ
話題転換に乗っかってくれた真昼はメニュー表を受け取って、早速目を通している。
透明感のある
いつもはあまり感情を浮かべない瞳も、今はどこか生き生きとして輝いているように見える。
(……もしかして、結構楽しみにしてるのか)
心なしかそわそわしているような真昼は、少しの間メニューを見てから「じゃあこれがいいです」と控えめに四種類の味が楽しめるパーティー向けのピザを指差す。
ほんのりと表情も
約一時間後に届いたピザを、真昼は早速食べていた。
四種類の味が楽しめるものなのでどれから食べようかちょっぴりおろおろしていたものの、始めはベーコンやソーセージがたっぷり載せられた味に決めたらしい。
意外ではないが割とお嬢様と発覚した真昼は、小さな口でピザをかじっている。
手摑みであろうと食べる姿にどこか品があるように見えるのは、恐らく教育の
それでいて、小動物のような小さなものを見て感じる愛らしさにも似た感覚を抱かせた。
伸びるチーズにへにゃりと目を細め、ほんのりと頰を
普段は大人びて見えるし実際落ち着いた雰囲気があるが、今の真昼は年相応の雰囲気だ。
はむはむ、と小さな口でピザを堪能している真昼に、無性に頭を
「……なにか?」
「いや、美味しそうに食べるなって」
「あまりじろじろ見ないでください」
ただ、嫌そうに
「……なんというか、お前ってほんと可愛げない」
「なくて結構です。むしろ、今更普段の学校のように振る舞ってもあなたは気味悪がるだけかと」
「まあそうだな。学校のお前よりこっちのお前の方が見慣れてるし」
真昼とは学校ではほとんど接点がないし、話した事もない。
ただ、等しく皆に優しく一分の
代わりに、今目の前では愛想が悪い部分を見ている。
本来の真昼は恐らくこちらで、学校では外行きモードを発動しているのだろう。
「俺としては、こっちの方が疲れなくていいけどな」
「可愛げない方がですか」
「根に持つなお前。……なんというかさ、学校でのお前は何考えてるかちっとも分からんから」
「主に献立と授業内容でしょうか」
「そういうボケは出来るんだなお前」
腹に一物抱えてそう、という意味で言ったのだが、真昼はそのままの意味で
本人としてはボケたつもりはないらしく微妙に不服そうな目を向けてくる。
「そうじゃなくて、内心が見えないんだよ。だから、何考えてるか分からないよりは多少愛想が悪くても素直に感情表現してる方が接しやすいって事だ」
「……学校での振る舞いは、駄目なのですか?」
「処世術なんだろうから駄目とは思わん。ただ、疲れないのかとは思うがな」
「別に。小さい頃からこうでしたし」
「筋金入りか」
幼い頃からの癖ならばあの振る舞いが板につくのも頷けるが、意図的に『理想的ないい子』で居ようとした、せざるをえなかった、という事でもある。
ただ、ほんのりと察する事の出来る家庭環境には、追及などとても出来ない。
「ま、息抜きする場所があるんならいいんじゃないか? 結果的に俺が息抜き相手になってるしな」
「……あなたは見ていて色々はらはらするから息抜きになりません」
「それはすまんな」
大仰に肩を
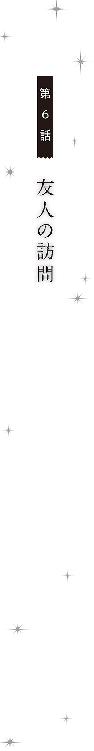
あの掃除以来ほんの少しだけ、
学校では全くの無関係だし、夕飯をおすそわけしてもらう時にたまに世間話をする程度。
先日も部屋の維持はきちんとしなさい、といった旨のお言葉をチクリといただいた。何だかんだ言葉はきついが、やはり面倒見はよい少女なのだと痛感する。
きっちり
「おお
綺麗になった、という事で休日に
「まさかここまで綺麗になるとは。あんな汚かったのにな。前も手伝って片付けたのにすぐ汚したし」
「やかましいわ」
「いやだってなあ。最長何日床にものが落ちてない状態が続いたよ」
「安心しろ新記録だ。二週間は続いている」
「新記録が二週間って事に恥を持とうな?」
普通は床にものを放置しない、と正論を言われて微妙にしかめっ面になるものの、樹は親切心と常識から言っているだけなのであまり拒絶も出来ない。
そもそも、真昼に手伝ってもらう前に樹にも世話をかけていたので、こういった所では強く出られないのだ。
ぐぬ、と押し黙った
「しっかしまあ、ここまで綺麗になったならちぃも連れてこれるなあ」
「やめろ、お前らのいちゃつきを
「遠慮すんなよ」
「
何が悲しくて友人カップルの仲むつまじげな様子を見せつけられなければならないのか。
バカップルとの呼び声高い二人のいちゃつく様を見せ続けられるこちらの身にもなって欲しかった。
樹が冗談で言っているのは分かっているものの、しょっちゅう二人の熱を見せつけられている身としてはあまり笑えない。
「まあ冗談として。こんだけ綺麗になってれば汚したりしないよな?」
「善処はしている」
「お前というやつは……まあいいけどな。出したらしまう
「おかんか……」
「もー周ったらぁ、ちゃんとお部屋はこまめに掃除しないとだめよー?」
「気味が悪いし地味にうちの母親と口調似てて怖いわ」
わざとらしくしなを作って裏声で注意してくる樹に、周は背筋を震わせる。
樹と母親は面識もない
そもそも男が女を強調した仕草をするのが気持ち悪いので即刻やめてほしい。
うぇ、と舌を出した周に樹がけたけたと愉快そうに笑う。
「周の母親はこんな感じなのか。うちはほんと素っ気ないからなー」
「むしろその方が
「息子
「あれ子離れ出来てないだけだと思うぞ……」
「いや確実に周がだらしないから構わざるを得ないんじゃ」
「やかましい。それ抜きにしても母さんは息子に構いすぎなんだよ」
一人っ子だからなのか、周の母親はしょっちゅう周に構ってくる。
甘やかすとは違うが、とにかくあれこれ世話を焼いたり変な気を回したりするので、嫌いではないもののちょっと相手に困るのだ。
高校に通うため地元から離れて一人暮らしする時にも色々と言われたりしたし、時折抜き打ちチェックにこようとするので結構大変だったりする。
「ま、それだけ周は大切にされてるって事なんじゃないのか?」
「愛が重い」
「
「経験則みたいに言ってるけど、お前現在進行形で反抗してないか」
「はっはっは。ちぃの事だからしゃーない」
父親と彼女の件で色々といざこざがある樹が言うとあまり説得力がないのだが、言っている事自体は一理あるため大人しく聞くだけ聞いておく。
こいつはこいつで問題抱えてるんだよなあ、とひっそりため息をつくが、肝心の樹は苦労を
「とにかく、親父はなんとかするからいいよ。とりあえず周は生活をきちんとしろよー?」
へらりと笑った樹に「言われなくても分かってる」と微妙に渋い顔を作って返して、どっかの
樹が周の家を訪れた理由は生活を見る……ためではなく、単純に遊びにきたからなので、部屋の話は早々に終わり二人でゲームをしていた。
当初の目的は一週間後に控えているテストの勉強だった筈が、いつの間にか遊びに変わっていた。
「お前無駄に回復アイテム使ってたら足りなくなるぞ」
「なんとかなるなんとかなる」
「いや何とかなるってレベル上がってないのにそれ大丈夫な訳……」
スリルを味わうのが好きらしい樹にどう突っ込もうか悩んでいた周だったが、部屋にチャイムの音が鳴ったためにすぐさま別の悩みが生まれてしまう。
「ん? 来客?」
樹もゲームをメニュー画面にしてから顔を上げる。
特に他人にこの家を教えている訳ではないと知っているし、家を訪れる友人もそう居ない。そもそも来客ならエントランスで足留めを食らうので呼び出しがくる筈なのだ。
「なんか分からんな、隣人辺りじゃないか? 回覧板とか」
「なるほどー」
「ちょっと出てくる」
ひきつりそうな顔を何とか隠しつつ適当に樹をごまかして急ぎ足で玄関に向かう。
呼び鈴を押した後に彼女が声を上げなかったのが幸いだった。
こちらも確認せずに手早く扉を開けて、姿が見えないようにするりと
案の定真昼が居たので、いつもと違う様子の周にぱちりと瞬きを繰り返している彼女に「しー」と人差し指を立てた。
「……小声で頼む。樹がきてる」
「樹?」
「友人だよ。遊びに来てる」
「ああなるほど」
周の隠密行動のような様子に得心したらしく
朝から仕込んでいたのだろう。中身がおでんという、寒くなってきた今の季節にぴったりの品だ。
ありがたく受け取った周は、渡す事に疑問を抱いていない真昼にそっと吐息をこぼす。
「いやほんと、お前の事はいつもありがたいと思ってるが、それを言うには時間が足りない。ごめん」
「別に礼を求めてる訳ではありませんので。……よかったですね、友人を招く事が出来るくらいに片付いて」
「土下座の感謝をした方がいいか」
「違いますやめてください」
私が嫌な女みたいじゃないですか、と呆れた風な
微妙に本気が混ざってしまったのは、彼女には本当に頭が上がらないからだろう。土下座してもよいレベルで世話になっていた。
流石にこの量を無償でもらい続けるのは色々と悪いので、今度改めて食事代金の話をしたいところである。
「じゃあ、お友達さんが来てるなら、あまり話してもいられないでしょうし。失礼します」
「……いつも助かってる。樹には相手を伏せとくから」
「そうしてください」
「まあ、仮に言ったとしても信じてもらえないだろうな」
「でしょうね」
素直に肯定されるとそれはそれで複雑ではあるものの、周が樹の立場なら、実は俺
それだけ天使様は
イケメンで優秀な男相手ならともかく、自分のようなぱっとしないだらしない男に手料理を振る舞うなんて、普通天地がひっくり返ってもあり得ないだろう。
「……一つ聞いてもいいか?」
「何ですか?」
「俺にこうしてご飯分け続ける利点ってなんだ」
普通、労力もお金もかけるのに、無償で料理を渡すなんて、しない。周が逆の立場でもしないだろう。好意を抱いているなんて万が一にもない確率を期待するつもりはないが、不思議で仕方なかった。
周の疑問に、真昼は少し考えるように視線を上に向けて、それから表情も変えずに「私の自己満足です」と返した。
「何て事はないのですよ。私は一人分作るより二人分作る方が楽ですし、単純に人に振る舞うのが好きみたいなので」
「料理好きって事か?」
「まあそれもありますね。あなたは厄介な勘違いしないでただ
「……そういうもんか?」
「そういうものですね。ですので、気を病まなくても降って
「へいへい」
これ以上は真昼も問答するつもりはないらしく、折り目正しく腰を折った後「失礼しますね」と自分の家に戻っていった。
(……そういうもんなのかなあ)
無償で与えるには
「誰だった?」
「お隣さん。おすそわけだってさ。冷蔵庫入れてくるからゲーム先進めんなよ」
「あごめんボス戦終わらせた」
「おいこらふざけんな」

周の住むマンションは家族用というよりは少人数で住むようなマンションなので子供は少ないし、周辺のマンションも似たり寄ったり。
そこからそう遠くない場所に作られた公園はこじんまりとしていて、どこか
子供達が遊んでいる訳でもなく、閑散としたその場所に──学校からの帰宅途中と思わしき真昼を見つけた。
「お前こんなところでなにしてんの」
「……何でもないです」
ベンチに姿勢よく座ったまま微動だにしない真昼は、周の姿を認めて
今回は前と違い顔見知りであり話せる間柄なためにあっさりと声をかけたものの、彼女の声は硬い。警戒されている、といった風ではなく、何かを表に出さないように気を付けている、といったように受け取れる。
「いや何でもないなら途方に暮れたような顔で座ってるなよ。どうかしたか」
「……別に……」
困り果てたような顔をしていたのが気になったが、真昼からその理由を口にする事はない。
外で
真昼としては、あまり関わってほしくないのかもしれない。
まあ言いたくないならいいか、と地味に表情を
「てか制服に毛が付いてるけど、犬か猫と遊んでたのか」
「遊んでません。ただ、木の上で立ち往生していた猫を下ろしてあげただけです」
「なんてベタな事を。……あーそういう事か」
「え?」
「そこで待ってろ。絶対動くなよ」
真昼が言った事で
真昼は、言い付け通り確実にあそこから動かないだろう。
というより、動けない、というのが正しいだろう。
変なところで強がりなやつめ、と一人こぼしながら近場にあったドラッグストアで湿布とテープ、コンビニでコーヒー用のカップ氷を購入して真昼のところに戻ると、やはりそのまま彼女はじっとしていた。
「
「は?」
端的に口にすれば、真昼が極寒の声を出す。
「いやそんな声されても……ほら、ブレザーかけるし後ろ向いてるからタイツ脱げ。とりあえず患部冷やして湿布
流石にタイツを脱がせて喜ぶ趣味はないので弁明もかねて購入品の入ったレジ袋を揺らすと、真昼の顔が分かりやすく強張った。
「……何で分かったのですか」
「ローファー片足だけ脱ぎかけだし微妙に足首の太さ違う。あとそこから立とうとしないからな。猫助けて足くじくとか本当にベタな事を」
「うるさいです」
「はいはい。ほらタイツ脱いで足だせ」
ちょっと見れば分かる事なのだが気付かれたのは想定外なのか、渋い顔をしている。
ただ、素直にブレザーを受け取って

周はそのまま真昼に背を向けて、コンビニで買ったカップ氷をビニール袋に入れて水を
こぼれないように口を縛りつつ、軽くリュックに入っていたタオルでくるんで即席の
真昼は、言われた通りにタイツを脱いで素足になっていた。
無駄な脂肪のない、引き締まりつつも柔らかさを感じさせる滑らかな脚のラインも、足首の不自然な膨らみも、露になっている。
「まあ
「……ありがとうございます」
「今度からは最初から素直に頼ってくれ。別に恩を売りたい訳じゃないから」
むしろこっちとしては散々
脚をベンチの上に乗せて足首を冷やしている真昼は相変わらずの表情だったが、周の気遣いを拒む事はなく、大人しいものである。
「痛み、引いたか?」
「……まあ、ある程度は」
「じゃあ湿布するから、……変態とか痴漢とか怒るなよ?」
「恩人にそんな失礼な事言いません」
「そりゃよかった」
やましい思いは
一応痛みの程度を聞いたところ立てるし歩けるけれど悪化しそうだから大人しくしていた、との事なので、ひとまず軽傷の
湿布を貼って一緒に買ったテープで固定すると、じっと周を見下ろす真昼に気付く。
「案外器用なのですね」
「まあ、
少しおどけたように肩を
先程から硬い表情をさせていたので、少しでもリラックス出来たならよかっただろう。
ほんのり態度が和らいだ真昼に内心
「ん」
「はい?」
「いやだからそんな顔するな。足見えるだろ。湿布貼ったままタイツはく訳にはいかないだろうし。着用してないから安心しろ」
テーピングで一回り大きくなっている足首回りのままタイツをはかせるのも悪いし、違和感があるだろうから防寒と下着が見える事を防止するためにはいてもらうのがいいだろう。
特に他意はないと分かっているらしく、実に素直にジャージをはいてくれた。
はいた事を確認してから、貸していたブレザーを
「ほいこっち着る」
「いやだからなんで」
「背負われてる姿見られたいのか」
流石に、怪我人を歩かせるつもりはないし最初からこうするつもりだったのだ。
どうせ帰る場所はほぼ一緒なのだから、周が連れて帰った方が効率がいいし怪我にもいい。
「あ、悪いけど
「背負わないという選択肢は?」
「あのなあ、足
「足ですか」
「なんだ、腕がいいのか。横抱きをご所望か」
「私を抱えて家まで帰れる筋力あるんですか」
「
真昼を横抱きにする事自体は出来るが、流石にマンションまで運ぶのは結構大変だろう。あと、人からの注目が大変そうなので出来ればやりたくない。
真昼も軽い冗談で言ったのは分かっているので
「ほら、着たならフードかぶってリュック背負ってくれ。あと、ついでに自分の
「……すみません」
「別にいいから。怪我人放って帰ったり歩かせたりするほど男は
パーカーまで着させたので着込んでいる筈なのに、それでも触れた体は細くて頼りなかった。
首に回された手がぎゅっと絞めない程度に自分を捕まえるのを確認してから、周はゆっくりと真昼を背負って立ち上がる。
やはりというか、軽い。
周に口うるさく言う割に本人は食べているのかと心配になる程度には
ほんのりと甘い
背負っているという事で多少人から視線は浴びるものの、真昼が顔を隠すように
「じゃ、これで」
真昼の自宅の玄関前まで運んで下ろして、周はこれ以上の干渉はすまいとあっさりと離れる。
壁を支えにしつつもきっちり自立出来ているので、怪我の具合もそうひどくはないだろう。幸いな事に明日から休日なので、数日安静にしていれば歩行に支障ない程度までは治る筈だ。
「今日は俺のご飯とかいいから安静にしてろ。なんなら栄養補助食品でもやろうか」
「結構です。作りおきありますので」
「そりゃよかった。じゃあな」
ご飯に心配ないのなら何よりだった。動かないで済むに越した事はない。
真昼が玄関の
「……あの」
「ん?」
声をかけられて顔を真昼に向けると、自分の鞄を抱き締めた彼女がおずおずとこちらを見上げている。
ほんのりと揺れる瞳に首をかしげると、少し困ったように視線をさ迷わせて、それでも意を決したのか周を
「……今日は、ありがとうございました。とても助かりました」
「いいよ別に、俺が勝手にした事だし。じゃ、お大事に」
あまり気に病まれても困るのでさらっと流して、真昼がぺこりと頭を下げたのを見てから自宅の鍵を開ける。
そういえばパーカーとジャージを貸したままだった事に気付いたが、また後日返却されるだろうと予想をつけて、周はそのまま玄関の向こうに身を滑らせた。
「なに、お前年中短パンな元気系だったっけ」
月曜の体育が
この季節になるともう
「ちげえよ。忘れただけだ」
「ばかでー」
「うっせ」
土日は真昼と会っていないのでまだ返却されていないからこんな事になっているのだが、
からかわれるのは甘んじて受け入れるが、けたけたと笑いながら背中をばしばし
樹が地味に
ただいまグラウンドで走り高跳びをしているのだが、女子も体育でグラウンドを使っての授業らしくグラウンドには女子の姿もあった。おまけに二クラス合同なため、結構な人数がグラウンドに居る。
あちらはあちらで陸上競技をしているので、待ち時間でこちらの体育を眺めている、といった感じだ。
「門脇くんがんばってー!」
基本は男女別の場所で授業があるので、女子が居ると男子達がざわめいていたものの……女子達の視線の先には、周のクラスメイトでありイケメンと名高い男子、
周はまず話す事なんてほとんどないのだが、人当たりがよく勉強も出来て
周としては、天は二物も三物も与えるんだな、という感想なのだが、他の男子的には面白くないらしく微妙に渋い顔をしている男子も多い。
「おーおー相変わらず大人気だなあ優太は」
「そうだな」
「興味なさそうだな」
「いや実際関係ない相手だぞ、クラスメイトでもろくに話した事ないし。どうでもいいわ」
別に向こうが害してくる訳でもないし、関わりがないので正直どうでもよい。
それが少数派なのだとは理解しつつも、やはり他の男子達と同じように
というか向こうの出来が良すぎて
「妬まないのは周らしいよなあ」
「なんだ、モテモテで
「キャラじゃねえ」
げらげら笑っている樹を半眼で見つつ、女子からの声援を浴びて
男から見ても均整の取れた体つきに甘いフェイスは、まさに王子様といったところだろう。実際あだ名に王子というものもある男であり、パッと見欠点らしい欠点が見当たらない男だ。
女子からの熱い
「なんというか、ほんと人気だな」
「だな。男子達が嫉妬待ったなしだ」
「はは。しっかし、女子達も元気だなー」
樹にとっては
千歳も優太にはこれっぽっちも興味がないので、樹が彼にどうこう思う事はないだろう。
(王子様やら天使やら、うちの学校は恥ずかしいあだ名付けられてるやつ多いよな)
そういえば天使様こと真昼は結局安静にしていただろうか。
休日出掛けた様子はなかったので大人しくしていたと思うが、
丁度真昼のクラスとの合同だったのでこっそりと辺りに視線を巡らせて見れば、人が沢山居ても
体操服に着替えず、授業の輪にも入っていないという事は見学だろう。
ちょこんと静かに
遠目ながらぱちりと目が合って、気まずげに視線をさ迷わせれば彼女の
その向きが周、というか男子達の集団に向いていたため、笑顔を向けられたクラスメイト達が「今俺に微笑んだ!?」「いや俺だろ」とざわついている。
「これはチャンスだ、いいところを見せて椎名さんにアピールせねば」
「王子にいいところばっか取られててたまるか」
ささやかな笑顔一つでこうも沸きたたせるのは、すごいと言えばいいのか彼らが単純と言えばいいのか。
「……単純だなあ」
同様の事を思ったらしい樹がこぼすので、周もつい笑った。
「まあ内申点もあるしそれなりに俺らも頑張らないとだめなんだよな」
「なんだ、周も天使様に見られてはりきってるのか?」
「いや違うけど。興味ないって言ったろ」
「ま、そりゃそうか。お前ほんとに興味ないからな」
彼女はいいぞ? と彼女持ちの自慢が始まりそうだったので「ハイハイ」と流した周は、もう一度真昼の方を見て苦笑した。
「先日はありがとうございました。お借りしていたパーカーとジャージです」
その日いつものようにおすそわけに来てくれた真昼は、タッパーの他に紙袋を持っていた。
ちらりと見えるのは周が金曜日に貸したままのパーカーとジャージだろう。きっちりと折り畳まれて入れられている。
「ん。具合はどうだ?」
「もう痛みはほとんどありませんよ。完治するまで運動はしないようにします」
「それならいい。体育も見学してたみたいだし」
「ええ」
念のために体育は見学にしたらしい真昼だが、それで正解だろう。痛そうにはもう見えないが、ほんのりと
賢明な判断だ、と
「しかしまあ、天使様すごい人気だな。微笑み一つで男子達のやる気みなぎってたからな」
「だからその呼び方はやめてくださいと……。私も困惑するのですけど、そんなに
「まあ美人から笑顔を向けられたらやる気が出るんじゃねえのか。女子も今日ほら、門脇に手を振られてきゃーきゃーしてたし」
「……門脇……ああ、あのすごくモテてる人ですか」
真昼はあまり興味がなさそう、というよりは実際ないのか名前だけではしっくりこず周の説明でようやく見当がついたといった感じである。
天使様ほどではないものの、優太もそれなりに学年では有名な男なので、名前だけで思い当たらないというのは意外だった。
「お前は興味ないのか?」
「特に。クラス違いますし、特に関わる事はないですから」
「ふーん。他の女子は結構騒いでるけどなあ。カッコいいって」
「まあ
「そういうところ淡白だよなお前」
「美醜だけで好意を抱くならあなたが私に抱いてないとおかしいでしょう?」
「お、自分
真昼の言う事はごもっともである。
「あれだけ騒がれていたら嫌でも分かります。それに、客観的に見て自分は整っているのは分かりますし、努力を怠った事はありません」
それが当然だ、という真昼は自慢げな様子など一切見られない。
実際、真昼は恐らく美貌を保つのにも手間を惜しまないだろう。
元々端正な顔立ちなのだが、それにあぐらをかいていない。
髪はあだ名の天使に
「左様で。淡々と事実を言ってるから鼻につく事はないけど、こう、
「あんまりにしつこく言われると
「大変だな美人は」
「その分得もしてますから一概に悪いとは言えませんけどね」
「ほんと他人事のような……」
「なんですか、照れて『そんな事ないですよ』と言えばいいのですか」
「いやお前の素を知っている身としてはそれをされても違和感が」
「そうでしょうね。私としても、あなたにそういう振る舞いをしても無意味だと思いますので」
「そうだな」
真昼が取り繕わないのは今更なので変えられても困るし、学校の真昼のように接してこられると微妙に鳥肌が立ちそうなので、是非このままでいてほしかった。
慣れとは怖いもので、学園の天使様が天使様らしく振る舞っていると違和感を覚えてしまう。
周にとっての真昼は今の真昼であり、学校での真昼ではないのだ。
結論としてはそのまま、という事が二人の間で決まったところで、周は渡されたタッパーを見る。
いつもより大きめのそれにはいくつかのおかずが詰められており、品目も多目。おすそわけというか最早弁当を渡されているようだった。
「今日は豪華だな」
「お世話になったので」
「気にしなくてもいいっつーか……おお、コロッケもある」
たかがコロッケと侮るなかれ。
コロッケは惣菜でよく売られているが、自分で作るとなると面倒くさい家庭料理筆頭である。
じゃがいもを蒸かして
料理をほぼしない周でも母親が作るのを見て面倒くさいし絶対作らないと思ったほどだ。
「まあ作り置きで冷凍していたものを揚げただけですけど」
「だからついでに唐揚げがあるのか」
「そうですね」
一人暮らしだと揚げ物なんて惣菜でしか手を出さないので、手作りはありがたい。
欲を言うならば、揚げたての衣サクサクの状態でご飯と共に食べたいが。
「……たまには出来たて食べてみたいよなあ」
彼女は衛生上なのかある程度冷ましてからタッパーに詰めているので、どうしても一度温め直す必要がある。揚げ物もトースターで衣のカラッと感は復活出来るものの、揚げたてには
無論それでも非常に
特に他意はなく単なる願望が口から
「家に入れろと?」
「んな事言ってねえよ、流石に分けてもらってる身でおこがましすぎるわ」
あらぬ疑いをかけられたので肩を
何か考えているらしく周と目が合う事はない。
「……
「ん?」
「食費折半で、あなたの家で作るなら考えます」
ようやく口を開いた真昼が放った言葉は、周の口を開けっぱなしにする程度の威力はあった。
冗談というか思わずこぼれた思い付きだったのだが、
普通、さほど仲良くない男の家に上がって作ろうと思うだろうか。
そちらの方が効率はいいとはいえ、相手は異性であり気心の知れた仲という訳でもない。不安になったりするものではないのか。
「折半はむしろ望むところというかもらいすぎてたから全然いいんだが……お前身の危険感じないの?」
「何かするなら
「やだこわ。ヒュンってしたわ」
「そもそも、そんな事しなくても、あなたはリスク考えてなにもしないと思うので。私の学校での立ち位置をよく分かってらっしゃるでしょう?」
「仮になんかしたら俺が破滅だわな」
周と真昼では圧倒的に人望の差がある上にか弱い女性という事で、彼女が周に乱暴されそうになったとこぼせば確実に周は学校に行けなくなる。
社会的な死を迎えるのを分かっていて何かするほど、周も馬鹿でも節操なしでもない。
というよりしたいという気にならないのが本音だ。
「それに」
「それに?」
「あなた、私みたいなのタイプじゃないと思うので」
真顔で言い切られて、つい苦笑してしまう。
「もしタイプだったとしたら?」
「そもそもしつこく話しかけてくるでしょうに。そうしたら私は関わらなかったんですけどね」
「お
「まあ、安全な人だとは認識してます」
「それはどうも」
それでいいのか、とは思いつつも、真昼になにかするつもりは更々ないので否定はしない。
それに、極上の晩ご飯が出来たてで食べられるという折角の機会を逃すつもりもなく、周は無害な男という称号を受け入れてお

・費用は材料費折半に加えて人件費という事で+α周が払う。
・用事があり食事を共に取らない場合は前日までに連絡。
・買い出しと後片付けは分担して行う。
最初の人件費については、時間を奪う事に対して申し訳なさが勝った周が言った事で真昼に譲歩してもらった形だが、その他は特に
作ってもらうにあたって当然の事だったので悩む事はなかった。
という訳で取り決めを行った翌日、早速真昼がスーパーの袋片手、
「……本当にろくに使った形跡ない新品ですね……」
「うるせえ」
家にエプロン姿の女子が居る、という男のロマンが具現化したような状況の中、周はなんともいたたまれない気分を味わっていた。
見慣れない、というのもあるが、キッチンがほぼ未使用に近い事を改めて指摘されて気まずいというのが大きい。
「いいもの
「お前が使うから腐らないだろ」
「結果論ですね。折角の調理器具が泣いてますよ」
「じゃあお得意の料理で泣き
「で、作りますけど調味料あるんですか」
「あるぞ、
「あら意外」
「封を開けていないからな」
「威張る事ではないですからね。まあ、足りなければうちから
「助かる」
「ひとまずは基本的な調味料があればなんとかなるでしょう。あと、今日の献立は独断で決めましたがいいですか」
「俺はあんまり詳しくないし食えればいいからなんでも。好き嫌いないし」
「そうですか。じゃあ早速作りますけど……調味料の場所とか教えてください」
「このかごに入ってる」
「本当に未開封ですね……」
調味料をまとめていたかごを眺めて呆れたように
「じゃあ作り始めますので、あなたはリビングで待つなり部屋で待つなりしていてください」
「そうする。手伝える事ないし」
「本当に潔いですね。まあ、料理出来ないのにうろちょろされても困りますし」
「お前も明け透けだな」
「事実ですから。取り繕う必要もないでしょう」
真昼の言う通り明らかに邪魔になるので、周は素直にリビングに戻って真昼の背中を観察する事にした。
手を洗い終えた真昼が早速調理に取りかかっている。
何を作るのかは知らないが、用意されていた材料的には和食だろう。
あんなに
(……なんつーか、奥さん持った気分)
そういった感情は互いに持ってないのだが、あまりにもこの状況が家庭を持っているような風に見えて、つい想像してしまった。
別に真昼とどうこうなりたいとは小指の
やはり、好意があるないとはまた別に、
「……何か変な事考えてません?」
「妙な憶測はやめろ」
振り返らずに指摘してきた真昼に顔がひきつりかけたが、真昼が振り返る事はなかったのでばれはしない。
妙に鋭いなこいつ、と感心したりひやひやしたりしつつ、周はほんのり
一時間ほどすれば、食卓には料理が並び始めた。
今日は真昼が選んだとの事だが、健康志向の真昼らしく和食で統一されている。
「割と調理道具や調味料はあったので、うちから持ってくる必要はなさそうです。明日からはもう少し

「いやもう作ってくれるだけでありがたいです」
調理道具や調味料がどれだけ揃っているか分からなかったせいか凝ったものというよりはシンプルなものが多かったが、
周がまず作ろうとすら思わないだろう煮魚や青菜の和え物、卵焼きに味噌汁などなどこれぞ和食といった風なものが並べられている。
好き嫌いはないが基本的に和食が好きな周としては、ほんのり申し訳なさそうな真昼にこういうものを求めていたと言ってやりたい程だ。
「……すげえうまそう」
「そう言っていただけるとありがたいです。冷めない内にどうぞ」
真昼がそう言って椅子に座るので、周も向かい側の椅子に座る。
一人暮らしでダイニングテーブルが小さめなため、どうしても距離はそれなりに近い。
一応の来客用として椅子が二つあった事が幸いだが、目の前に美少女が居るという状況はなんとも言えない感覚を呼び起こした。
ただ、料理に手をつけてしまえば真昼の美貌
いただきますもそこそこに、まずは味噌汁に口をつける。
お椀に口をつけた瞬間に香る味噌とだしの香りを堪能しながらゆっくりと口に含めば、香り通りに広がる味噌の風味と、だしの風味。
インスタントの味噌汁とは全く違う柔らかな味わいは計算し尽くされたものだろう。
味噌の味は濃すぎず、だしの風味を感じさせるほどよい塩梅。
一口目は少しだけ薄いと感じてしまうのは、他の料理と一緒に口にする事を考えて、飲みきったくらいでちょうどよく濃さを感じるといった味付けにしたからだと思う。
物足りない、というよりはほっとする味であり、ご飯や他のおかずを食べるように促してくる味だ。
「うまい」
「どうもありがとうございます」
素直な感想を口にすれば、真昼の
普段から美味しいとは伝えていたのだが、目の前で言われるのはまた緊張があったのだろう。
こちらを様子見していた真昼も食事に手を付けだしたのを見て、周もおかずに
並べられたものを一通り口にして思ったのが、やはり真昼は料理が非常にうまいという事だ。
煮魚はしっかり味を含みながら身の水分は保たれたまま。
味を
卵焼きに至っては非常に周好みの味付けだ。
表面の鮮やかな黄色に
卵焼きにも砂糖を入れる派、塩のみ派やら色々居るが、こちらはだし巻き玉子となっていてだしの味に加えてほんのりとした甘味。
微かに、それでいて柔らかく感じるこの甘味ははちみつだろうか。
量はそんなに入っていないだろうが、コクのある甘味が味の深みを出していた。
甘い卵焼きもしょっぱい卵焼きも嫌いではないが、一番はだしのきいたほんのりと甘さを感じる上品な味付けだと思っている周は、この理想型のだし巻き玉子に感動すら覚えていた。
うまい、と
火の通り具合も完璧。だしを含んでいるので
うちの母親より確実にうまい、とここには居ない母親に失礼な事をこっそり思いながら幸福に
「……美味しそうに食べますね」
「実際うまいからな。うまいものには敬意を表すべきだろ」
「ええ、それはまあ」
「それに、無表情で食べてるより素直にうまいって言った方がどっちも気分もいいだろ?」
美味しいと思っていても顔に出さなければ作り手は不安になるだろうし気になる筈だ。無表情で美味しいと言われても本当に美味しいのか疑念が湧く事もある。
それよりは、素直に感じているものを顔に出して言葉にした方が、双方のためになるだろう。感謝するのもされるのも、気持ちがよい方がいいのだから。
「……そうですね」
周の言に納得したらしい真昼が、少しだけ
気の抜けたような、安堵の含まれた柔和な笑みは、一瞬周の思考
「
「あ……いやなんでもない」
見とれていた、なんて言える筈もなく、周はじわっと浮かぶ
「……ごちそうさま」
「お粗末様でした」
並べられた料理を
しかし、表情は穏やかなもので、こうして米粒ひとつ残さず胃に納めた事を喜んでいるようであった。
「うまかった」
「見てれば分かりますよ」
「うちの母さんよりうまいわ」
「女性の手料理を母と比べるのはタブーらしいですよ」
「それけなす場合じゃないか? つーか気にする?」
「気にはしてませんけどね」
「じゃあいいだろ。うまいって事実には変わらないし」
真昼の料理はちょっとやそっとの料理経験では培えないほどの腕前だ。
恐らく周の母親の方が料理経験としては年季が入っているのだが、味付けの好みが違ったり
そもそも母親よりもむしろ父親の方が料理が
「……いやなんか俺幸せもんすぎないか。毎日食えるんだよな」
「双方に用事がない限りはそうですね」
「……これ、ほんとに毎日お
「嫌なら提案してません」
「まあそうなんだろうけどさ」
材料費折半に加えて人件費も払っているのだが、それでも真昼の負担が大きすぎる気がしてならなかった。
「……普通さ、好きでもない男に作るか?」
「あなたがあまりにも不摂生だからなんですが。それに、私は作ること自体は好きですし、あなたが美味しそうに食べるのを見るのは嫌いではありません」
「でもさ」
「そこまで気にするなら、別に私としては作らなくてもいいのですよ?」
「いや作ってくださいお願いします」
つい即答してしまったのは、それだけ真昼の料理が周には必要であり好みだからだ。
今の周から真昼の料理を奪われると割と死活問題に発展する。
胃袋を握られているのは自覚していたが、真昼の料理が美味しすぎるのが問題なのである。これでは惣菜に戻った瞬間味気ない毎日になりそうで怖かった。
周の分かりやすい返答に呆れたような顔を見せた真昼は、苦笑にも似た表情を浮かべる。
「じゃあ素直に受け取っておいてください」
「……おう」
なんとも慈悲深い天使様のご相伴に預かる日々はまだまだ続きそうで、

「周~、どうだった?」
期末考査の日程がようやく終了して地獄のテストから解放された学生達はいつもより活気づいた様子で教室にたむろしている。
「ん? 普通。よくもなく悪くもなく」
聞かれて答えはするものの、特に何か言う事はない。出題範囲をそのまま出されているので、
今回も手応えは今まで通りだったので、周としてはあまり感想がなかったりする。
周は面倒くさがりではあるものの、基本的に復習を欠かす事はない。大体授業で習った事は頭に入っているし、満点こそ無理ではあるが八割九割は固かったりする。
「そういうお前は大概するっと三十番内に入ってるんだよな……インテリめ」
「日頃の行いだな」
「お前の日頃の行いがいいというのか!」
「少なくともいちゃつくのにかまけて勉強をおろそかにしてるやつが
周と樹の差は、頭の出来というよりは彼女である
樹も物分かりはよく
「……彼女はいいぞ?」
「ハイハイ」
「周もさー、彼女作れよ」
「欲しいからって作れるなら世の男は血の涙を流したりしないぞ」
欲しくても与えられない人間は山ほど居るので、樹の
周は別に目くじら立てるつもりはないし、そもそも今のところ恋人がほしいといった欲求はないため、さらっと流すのだが。
「大体作ってどうすんだよ」
「ダブルデートを」
「それ俺と架空の彼女が胸焼けして終わるだけだろ」
「オレ達にも見せ付けろよ!」
「俺の性格で出来ると思ってんのか」
「……無理だなあ」
「だろ」
周も自覚しているが、淡白な性格をしている。
人によっては冷たいと取られる面倒くさがりな性格
万が一彼女が出来たとしても、非常にあっさりとした関係になるだろう。少なくとも樹のような人目をはばからずいちゃつくような関係にはまずならない。
「いやでも周も好きなやつくらい見付けろよ。お前、前髪もう少し切ってさっぱりして髪セットしてしゃっきりしたら絶対女子の見る目変わるから」
周は自己評価というものは正確にしているつもりで、
ちゃんとそれなりに
ただ、着飾って寄ってくる相手に愛想を振りまけるほど周は器用ではない。
「見た目によってくるやつにロクなのは居ないぞ」
「そう言うが、まずは興味を持ってもらわないと人柄に触れる事すら出来ないだろ?」
「……そうだとしても、別に今のところ彼女作りたいとかはない」
仮に彼女を作ったところで、素の周を見れば確実に幻滅するだろう。
周はズボラであり生活能力がない人間で、その上愛想もない。むしろ
周としても、いちいち他人に構うのは面倒くさいという人付き合いに向いてない性格なため、彼女は欲しいとは思っていない。
それに、今は
周の中では「真昼の料理>まだ見ぬ彼女」の優先度であり、恐らくそう
「淡白なやつめ……ちぃの友達紹介してもらうとかもあるんだぞ?」
「余計なお世話だばか。大体千歳の友人って確実にハイテンションなやつらだろうが、俺には友達付き合いすらきついぞ」
「周は陰キャだからな」
「やかましい」
「まあ、周が言うんだったら今のところは言わないけどさ。でも、華の高校生活で彼女も作らずに一人むなしく過ごすのは辛くないか?」
「要らんしめんどくさい」
学校生活をなんだと思っている、という真面目な思考ではないものの、別に必要に駆られる事はないから作りたいとも思わない。
そもそも、好きな相手はそう易々と作れるものではないし、
「……もったいねえなあ」
「はいはい」
「でもまあ、周も好きなやつ作ったら変わるぞ?」
「何で断言してるんだ」
「お前みたいなやつに限って彼女は
「勝手に言っててくれ」
自分がそんな甘ったるい人間になるなんて想像出来ないしあり得ないとふんでいる周は、樹の言葉を適当に流す。
そんな周を樹は
「いっくーん、帰ろー?」
「おっ、ちぃか」
ちょうど、千歳が来たらしい。帰宅の約束をしていたようで、周はそれまでの話し相手になっていたのだ。
振り返れば、赤みがかった明るい茶髪をミディアムショートにしたボーイッシュな少女が満面の笑みでこちら、正しく言うと樹に手を振っている。
真昼とは違ったタイプの美人である千歳は、こちらに駆け寄ってきてにこにことしている。
そのまま黙っていてほしいと思ったのは、千歳がしゃべると大概周がいじられるからである。
「ちぃも思うだろ、周みたいなタイプが実は恋人
「余計な話を振るな」
「え、何、周に恋人居るの!?」
「いねえよ」
「えー、なんだー。居たらなかよくしたかったのにぃ」
ちぇー、と唇を
「お前の仲良くは過激なスキンシップだから架空の彼女が
「え、イマジナリーガールフレンドいたの?」
「今もし居たらって話の流れだっただろうが!?」
「じょーだんじょーだん」
「お前の相手してると疲れる……」
「周の体力ないだけでしょ」
「気力ごとごっそり持っていかれるんだよ……」
体力
多少邪険に扱われても全く気にしていない千歳は、
同じように樹も笑っていて「はやく慣れろ」と適当なアドバイスを投げてくるので、周はもう疲れて深く息を落とすしかなかった。
「……何してるんだ?」
帰宅して真昼手製の料理を平らげた後、周が洗い物から戻れば真昼がリビングで問題用紙を広げていた。
洗い物は交代制、というよりはなるべく負担をかけまいと周が率先してやっているため、その最中は真昼はリビングに居る。なんでもさせるだけさせてさっさと帰るのは申し訳ないとの事。
「採点です」
「まあ見りゃ分かるけど」
見直しをしているのか、教科書を出して間違いがないか確認しているようだ。
「ちなみに結果は」
「解答用紙の方に私が記述を間違っていなければ満点ですね」
「流石としか言えんな」
あまりにあっさりと満点と告げられたため、周も特に大仰な反応はしなかった。
驚かなかったのは、常に定期考査では一番に名前が書かれていない事がなかったからである。
真昼ならやりかねないと思っていたため、満点と聞いてもやはりという感情しか浮かばない。
「勉強は嫌いではないので。そもそも、先に一年先まで丸々履修内容先取りしてますから復習で充分です」
「うわこわ。よくやるよ……」
「
「俺の成績知ってたっけ」
「
どうやら話す前からある程度の存在は知られていたらしい。
てっきり上位一
周がそれなりに勉強するのは、学生は勉強が本分である……という
「ま、一人暮らしの条件だからな、成績の維持は」
一人暮らしをするにあたって、成績は維持する事、と決められている。
他にも半年に一度は顔を見せるとか条件があるが、そちらは長期休暇を使えばどうとでもなるので基本は成績さえ保っていればとやかくは言われないのだ。
「困らない程度には勉強してるけどお前ほどじゃない。よく頑張るよなあ」
「……頑張らないと、いけませんので」
小さく
その表情は前髪に隠れて
しかし、すぐに顔を上げていつもの表情に戻っていたため、指摘する事は出来なかった。
出来ていたとしても、しなかっただろう。痛みに耐えるような、そんな雰囲気だったから。
時折、真昼はそういった面を見せる。
何が苦しいとか何が嫌だとかそういった事は決して口にはしないが、何かに
それが家庭環境に起因するものだというのは、想像に難くない。
他人の自分が踏み込んでいい領域ではないと分かっているからこそ、周はそこには触れずにあくまで隣人のほどよい距離感を保つようにしていた。
周にも、触れられたくないものはある。土足で踏み込む事の方が失礼であり、何も知らない振りをしてくれる方が
先程の雰囲気を隠した真昼は「そろそろおいとまします」といつもの涼やかな声で告げて、
それを止める気もないので「そうか」とだけ返して、
真昼が全部出したものを仕舞い終わって席を立ったところで、空のコップの影に周のものではないものがある事に気付く。
ふと手に取れば、学生なら
恐らく、教科書を出した際に一緒に出してしまって仕舞い忘れたのだろう。
顔写真に加えて氏名、学籍番号、生年月日血液型といった簡単な情報が書かれたそれを眺めてから、帰ろうと玄関で靴を
「落としてるぞ」
「ああ、すみませんわざわざ。ではおやすみなさい」
「おやすみ」
ぺこ、と丁寧に腰を折って周宅を後にした真昼に、周は見送りながらそっとため息をつく。
先程見た学生証に書かれていた生年月日……特に月日の部分を思い出して、額を押さえた。
「……四日後じゃねえか」
学生証を見なければ知らないままであっただろう真昼の誕生日に、周はもっと早く知りたかったと再び深いため息をついた。
「そういやお前、何か欲しいものはあるか」
翌日、善は急げと夕食時に真昼に切り出してみた。
別に誕生日に贈り物を渡すのは、なにか他意があるという訳ではない。日頃から世話になっている彼女にお礼も兼ねて渡しておいた方がいいだろう、という判断のもとプレゼントをする事に決めたのだ。
ただ、聞き方は間違いなくあやしかっただろう。
我ながら隠す気もひねりもない聞き方をしてしまったと後悔したが、真昼は
「いきなりなんですか」
「お前、あんま物欲なさそうだし好奇心で聞いてみた」
「また唐突な……」
自分でももう少し
幸いと言っていいのか、誕生日の事については気付いた様子を見せなかった。
真昼にとっては周が自身の誕生日を知る
「そうですね、必要なもの。今欲しているのは」
「欲しているのは」
「
「……砥石?」
思わず聞き返してしまったのは、周が全く予想していなかった返答だからである。
というより、恐らく女子高生に欲しいものを聞いてこんな答えが返ってくるなんて誰も想像出来ないだろう。
普通はコスメやらアクセサリーやらバッグあたりを欲しいというものだ。まさか金属を研磨するための道具を欲しがるなんて、周には予想も出来なかったのだ。
「そう、砥石。幾つか持ってますけど、もっと目の細かい仕上げ砥が欲しいんですよね」
「おい現役女子高生」
「私に一般的な女子高生を求めないでください」
それを言われると周も反論しにくい。
お世辞にも、真昼は一般的な女子高生とは言えない。
天使というあだ名がついている時点で相当なのだが、文武両道の才女、その上料理上手で家事も
(だからって砥石なんて想像つくかよ)
欲しいものが砥石の女子高生なんて真昼以外居ない気がする。
「自分で買わないのか」
「別に買えなくはないですよ。ただ、あまり使用機会がないし、その上高いしで手を出さないだけです。元々仕上げが出来るものは持ってますから、別にいいかなって」
さらりといくつか所持していると言っている辺り、末恐ろしい。
「……包丁研いでる女子高生とはこれ
「割と居ますよ」
「居たとしても俺の知り合いにはお前だけだし、砥石を欲しがるのもお前だけだ」
「レアという事でよかったですね」
「何が良いんだよ……」
レアすぎて彼女の
当てがなくなり途方に暮れるしかない周に、真昼は不思議そうに首をかしげていた。
「なあ
真昼の欲しいものの傾向が全く分からないので、苦肉の策で樹に参考に聞いてみる事にした。
果たして真昼を普通に当てはめていいのかは分からないが、女子が喜ぶものはいやがりはしないだろうという予想である。
「なんだ」
「樹は千歳にプレゼントとか何渡してるんだ」
一番は彼女に渡しているものを聞いてみるのがいいだろう、と聞いてみたのだが、きょとんとした眼差しを返される。
「え、お前誰か意中の女の子にプレゼント渡すの」
「俺がそんなことする柄だと思うか」
「思わん」
「だろう」
「じゃあ何で聞いたんだよ」
「知り合いが誕生日だから参考程度にな」
参考程度にどころかがっつりそれから選ぶつもりであるが、そこまで言うつもりはない。
「ふーん。そりゃ欲しがってるものをやるのが一番だな。つーか普段からそういうリサーチをしておくのが大事だし円満の
「別に彼女じゃねえっての」
真昼が彼女とか色々と身の危険を感じるし(主に周囲の殺気が)、そもそも恐れ多すぎる。
確かに
可愛いと思う事は当然あるが、どうこうしたいまでは発展しない、そんな感情だ。
「欲しいものなあ……もし分からなければ?」
「仲のよさによる。親しいならアクセサリーとかでもいいが、親しくないなら雑貨や消えものが無難だな。花とかは
「……詳しいな」
「まあそれなりに勉強したからな」
樹と千歳は最初から相思相愛という訳ではなく、中学生の頃からゆっくり距離を詰めてきたらしい。中学は別だった周には分からないが、色々と乗り越えて交際に発展したらしく、今でものろけと共に聞かされる。
千歳にプレゼントを贈る時にも相当悩んだらしいので、彼の選んだチョイスが色々考えてのものだと分かる。
「あと、ハンドクリームはいやがられないな」
「ハンドクリーム?」
意外な選択肢に周が
「どの年代でも比較的使うだろ。学生なら授業でノートや教科書触ってたら乾燥するし、社会人なら打鍵や空調で乾燥しがち、主婦は家事で水仕事するから荒れやすいし。プレゼントとしては腐らないよ」
「ふーん。詳しすぎてドン引き」
「お前が聞いてきたんだろうが」
べし、と背中を
(ハンドクリームか)
確かに、それならあっても困らないだろう。
晩ご飯後の食器洗いは周が自主的にしているものの、真昼も自宅でするであろうから手が荒れないとも限らない。
というより普段から手入れしているからあんななめらかな手をしているのだろうし、荒れ予防の品を贈るのは悪くない筈だ。
「まあ、参考になった」
「あとはちぃに聞いてみろ。同性ならではの着眼点があるだろうし」
「……えー」
「いい加減慣れろ」
もちろん嫌いではないが苦手なタイプの千歳に会いに行くのは微妙に気が引けるのでしぶれば、樹が愉快そうに笑いながら今度は優しく背中を叩いた。
「えー? 周が女の子への誕生日プレゼント?」
また珍しい、とにこにこ、いや、にまにまと笑みを浮かべていて、周の
放課後に千歳の教室に寄って話しかけたのだが、案の定高いテンションで返される。ちなみに樹は周なら心配する必要は何らないと千歳にメッセージを入れて先に帰っていた。
上機嫌そうな笑みを浮かべた千歳に、周はそっとため息をつく。
(だから嫌なんだよ、千歳に頼るのは)
確実に
「だからいっくんが『周がちぃを頼りたがってる』って書いてたのかーなるほど。私の力を借りたいって事だね」
「頼れる女子が千歳しか居ない」
「それを言い切るのはちょっとどうかと思うんだけどね」
若干呆れた、というか同情するような眼差しを向けられたが、周は流しておく。
実際、周には女子の友人など千歳以外存在しない。クラスの女子はあくまで顔見知りであるし、頼み事を出来るような仲でもない。
そもそも、クラスの女子達が日頃目立たず大人しい人間だと思われている周に話しかけられても困るだけだろう。
「まあ周に女心が分かるとは思えないし、よかろう。この千歳さんが相談に乗ってあげようじゃないの」
「……一応頼りにしてる」
「一応って何よ一応って。こう見えて女心はばっちりだよ!」
「そりゃ女だからな、一応」
「そこ一応つけたら駄目でしょ! 私のどこが男に見えるって言うの」
えへんと胸を張った千歳だが、悲しい事に真昼を毎日見ている身としては大変控えめなものに見える。すとん、と視線が落ちてしまうほどだ。
ただ、男子からの人気は高い。
性格的に明るく
中学では陸上部に所属していたらしくスレンダーな体つきと引き締まった脚が見せる脚線美が中々の人気だそうだ。樹が「あんま人の彼女の体をじろじろ見てたら怒るぞ」と男子に忠告するくらいには
「あーはいはい可愛い女の子ですねー」
実際性格が微妙にフレンドリーすぎるところがあるだけで、可愛いのは確かだ。人気があるのも分かるのだ。
「……そういう態度取るから人に誤解されるんだからね、もう」
「余計なお世話だ」
「はいはい。で、女の子にあげるんだよね? で、どんな子?」
それを聞かなければ始まらない、と言わんばかりに問う千歳に、周は迂闊な事を話せば最後、からかわれると分かっているので慎重に言葉を選ぶ。
「知り合いの女性で比較的若い。それ以上は黙秘権を行使する」
「あのねえ……人柄とか好みとか分からないと私も提案しようがないんだけど」
「千歳の感性でもらったら嬉しそうなものを言ってくれないか。その中から選ぶ」
「話す気がないって事は分かった。しょーがないなあ」
千歳が言う事もごもっともなのだが、話せば周が年若い女性と親しくしている、という事なら変な方向に話がずれて大変な事になりかねないし、下手すれば真相を確かめようとしてくるだろう。
なるべく避けたいので余計な事を言わないようにしていたら、千歳もこれ以上は口を割らないと分かっているらしく引き下がってくれた。
「んー、そうだなあ……どんな間柄なのか分からないけどそれなりに話す知人……まあこの場合私が周くらいの仲の人にもらって嬉しいものだと仮定するけどさ。それなら、基本的にはあんまり高くない消耗品か日用品かなあ」
「樹もおんなじような事言ってたわ」
「流石いっくん乙女心の分かる男。んで、気兼ねなく渡すって事ならお菓子とかハンカチやポーチみたいな小物くらいかなあ。アクセサリーは私周からもらったら『どうしたの!? 賄賂!?』ってなるし」
「お前に賄賂渡しても仕方ないだろうが」
何の
「だから小物類が無難かなあ」
「……そうか」
「それじゃ不満?」
「不満って訳じゃないけど」
もちろん不満ではないのだが、本当に喜んでもらえるかが心配だった。
小物を渡すという事はセンスが問われるだろう。真昼は恐らくかなり趣味がいいし、質と機能性を両立したものを選んで使うタイプだ。周のチョイスが真昼のお
微妙に周が納得してなさそうな気配を感じたらしい千歳が「うーん」と
「……そうだなあ、あとは、可愛いものとか」
「……可愛いもの?」
「その人の趣味によるけど、可愛いもの……たとえばぬいぐるみとかマスコットキーホルダーとか、そういうもの渡すのもありだと思うなあ」
周からすれば意外な提案に瞬きを繰り返せば、千歳が意味ありげに笑う。
「女の子は大概いつになっても可愛いものが好きだからね。ぬいぐるみは大人になっても集めてる人も居るし、好きな女の子も多いんじゃないかなあ」
「……ぬいぐるみ、か」
真昼が少女趣味かは分からないが、可愛らしいフリルのあしらわれた服やいかにも女の子らしいひらひらの服を着ている事もあるので、可愛いものが嫌いという訳ではないだろう。
もし周がぬいぐるみをあげたら、真昼は喜ぶだろうか。
「お、乗り気になりましたな?」
周の変化を機敏に悟ったらしい千歳がにやっと笑うので、微妙に複雑な気持ちを覚えつつも
「……でも俺がぬいぐるみを買うのってシュールすぎだろ」
「プレゼントなのにそこ
「流石にこの
「意気地なし」
「うっ」
全くもってその通りなのだが、指摘されると余計に刺さる。
恥なんてかき捨てていくべきなのだが、そもそも一人でぬいぐるみを取り扱う店に足を向ける事自体気恥ずかしさがあった。
幸いここには千歳が居るし、帰りがけについてきてもらう事自体は可能だろう。
可能では、あるが。
「……千歳、一緒に」
「一緒に?」
「……買い物を付き合ってください」
「どうしよっかなー」
こうして焦らしてくるのが千歳という少女だ。
もちろん本当に拒むつもりはないのだろうが、わざとらしく悩んだ振りをするのは周をからかうためと、決心をつけさせるために違いない。
「頼むから。本当に頼む」
「んー、行ってもいいんだけどね? ……ところで周くん、私甘いもの食べたいなー。駅前のクレープ屋さんに期間限定のすっごく
「……
「わーい!」
おねだりしてくるちゃっかりな千歳に
たかがクレープ一人前、一人でファンシーショップに寄るよりはずっとましだろう。
にこにこ笑って上機嫌も露な千歳に盛大なため息をついて、周はとりあえず財布の中に入ってある予算を頭の中で思い浮かべた。
樹と千歳のアドバイスを経て贈り物を選択した周は、誕生日当日地味に緊張した面持ちで真昼の背中を見ていた。
駅前のクレープ屋の特製クレープ(冬季限定ベリーベリースペシャル)を代償に千歳にわざわざ一つ頼んだものがあるので、それもプレゼントに加えたのだが……いつ渡せばいいのか悩んでいた。
誕生日の本人はというと、普段と変わらずに夕食を作っている。
献立は知らないが和食のような雰囲気であり、やはり特別といった感じはない。あくまで自然体に過ごしていた。
本人からは全く誕生日という気配すら感じさせない。というか頭にないのではないか、と思うくらいにはいつも通りだった。
それは食事が出てからも変わらず、会話こそすれど普段通りに食事をとっていた。
真面目にどのタイミングで渡せばいいのか分からず、ソファの陰に隠したプレゼントを入れた紙袋の方向を見て
ひとまず、後片付けを終えてリビングに戻れば、真昼が丁度二人がけのソファに腰かけて持参したらしい本に目を通しているところだった。
読書している様も絵になるのは、流石天使といったところか。
なんとなく、隣に座るのは微妙に躊躇いがあるのだが……遠慮していても仕方ないと、置いてあった紙袋の
ふっと顔が上がる。
気配と紙が
不思議そうにしている真昼は、ここまできても誕生日の事だと気付かないようだ。
「ん。やる」
突き出すように真昼の
「なんですかこれ」
「誕生日なんだろ」
「そうですけど……逆に何で知ってるのですか。私、誰にも言った覚えないんですけど」
さっと警戒の色が
「別に、気にしなくてもよかったのに。私、誕生日なんて祝わないですし」
どこかそっけなく突き放すような声に聞こえたのは、聞き間違いではないだろう。
誕生日という言葉自体にどこか
なるほど、と思った。
彼女が
誕生日が
でなければ、あんな言い方はしないだろう。
「あっそ。じゃあ日頃の感謝の印でいいよ。俺が勝手に恩を感じて渡すだけだから」
だが、誕生日を祝わなくてもいいというものと日頃のお礼はまた別で、誕生日プレゼントとしてではなく感謝の気持ちという事で彼女に押し付ける。
毎日毎日美味しい料理をごちそうになって、たまに掃除も手伝ってもらって、地味に世話されている状態なのだ。恩を小出しにでも返しておきたかった。
あっさり引き下がりつつも贈り物だけは手渡してくる周に真昼は混乱していたようだが、プレゼント自体は渡すつもりの周に困ったように眉尻を下げて受け取る。
視線が、紙袋の中身、更に袋で包装されたものに集まっている。
「……開けてもいいのですか?」
「ん」
頷くと、真昼はおずおずと紙袋に入っていた箱を手に取り、丁寧に包装紙を開けてリボンをほどく。
なんというか、贈り物を目の前でゆっくりと開けられるというのは、やけに緊張した。
中に入っているのは、樹におすすめされたハンドクリームだ。大きめな箱でささやかにお菓子がついているのはセットで売っていたからである。
ちなみにいい
ネットで評判も確認しているので、効果に心配はないだろう。
「まあ大したもんでなくて悪いけどな。家事させてるし、乾燥するだろ。匂いがついたやつもあったけど、お前持ってそうだったし。肌に優しくて効き目があるらしい」
「実用的ですね」
「お前はどちらかと言えば実用性に重きを置いてるだろ」
「そうですね。ありがとうございます」
よく分かってらっしゃる、と小さく笑った真昼に、周も少し口許が緩んだ。
印象としては悪くなさそうである
あとはもう一つ、あるのだが……なんというか、目の前で開けられるのが気恥ずかしいため、出来れば家に帰った後に気付いてほしかった。
しかしながら、紙袋の中にもう一つものが入れられている事には気付いていたらしく、真昼は紙袋の中を見る。
「……何で二つも?」
「あー。いや、その、なんだ。独断と偏見によるおまけだ」
「おまけ?」
「……おまけだ」
視線を逸らしてそれだけ返すと、真昼は訳が分からなそうに一度首をかしげていたものの、開けてみれば早いと紙袋からそれを取り出す。
なるべく目立たないように紙袋の内側と同色の包装をしてもらい、底に寝かせておいたのだが、やはり目立つ大きさのものだ。気付かない訳がない。
箱ではなくポリエステルの袋に入った、それ。大きさは、丁度真昼に腕に収まる程度。
紺のリボンで縛られていて、真昼がこれまた丁寧に外すのを眺めながら(俺席立っていいかな)なんて考えていたら──真昼が、入っていたものを丁度取り出していた。
両手で丁寧に中身を持ち上げた真昼は、本当に意外そうにぱちりと大粒の
「……くま?」
真昼が
あまり大きすぎない、小学生くらいが抱き締めて丁度よいくらいの、ぬいぐるみ。
真昼の髪のような淡い色の柔らかな毛並みが特徴で、首元には首輪よろしく水色のリボンが結ばれている。
どこかあどけない顔に縫い付けられた、ボタン製の光沢のある黒くつぶらな瞳が真昼を映している。
高校生にもなってぬいぐるみか、と思ったかもしれない。
しかしながら、女の子はいくつになっても可愛いものは好きなもの、という千歳のアドバイスのもと、これを選択した。
流石に男一人で買うのは非常に恥ずかしかったため、駅前のクレープという代償を払い千歳と共に買ってきたのだ。
結局選んでいる時間からラッピングしてもらっている時間まで終始千歳ににやにや笑いで見守られたため、一人の方が恥ずかしさが少なかった気がしなくもない。過ぎた事なのでもう仕方ないのだが。
「……女が好きそうだと思って」
誰に言い訳するでもなく呟いて、頭を
こういうのは、苦手だった。
そもそも異性にプレゼントするなんて幼い頃母親にした以来で、まさかする事になるなんて思っていなかったのだ。
こんな可愛らしいぬいぐるみを男から贈られて引かないか……とちらりと真昼を
表情からは嬉しいとも、嬉しくないとも読めず、ただひたすらにくまを眺めている。
「ま、気に入らないなら捨ててくれ」
気にくわないのなら仕方ない、と判断しての軽い冗談のような言葉を贈ると、真昼がぱっと顔をこちらに向けてきゅっと眉を寄せた。
「そんな事しませんっ!」
「お、おう、椎名の性格的にはしないとは思ってるが」
思ったより強く否定されたためたじろぎながら頷くと、真昼はもう一度手にしていたくまを見つめる。
「……そんなひどい事、しません。大切にします」
細い腕が、包み込むようにくまのぬいぐるみを抱き締めた。
幼子がお気に入りのおもちゃを取られまいとする仕草にも、母親が慈しむように包み込む仕草にも、見える。
ただ言えるのはひたすらに大切そうにそれを抱き締めた、という事だ。
ぎゅう、といった効果音が似合いそうな抱き締め方をした真昼は、少し瞳を伏せながら腕の中にあるくまを見下ろしている。
浮かんだ表情は、いつもの素っ気ない表情や呆れたときに見せる表情でもなく、穏やかで柔らかく、どこか慈しむような、
それでいてあどけなさすら感じる、
(──見るんじゃなかった)
こんな表情をされると、否応なしに意識してしまう。
恋愛的な好きとかではなくとも、極上の美少女にあのような表情をさせた、あんな表情を見てしまった、という事が心臓を高鳴らせる。
ぬいぐるみを大切そうに抱き締めて淡く微笑んだ姿は、恐らく誰が見ても見とれてしまいそうなくらいに、可愛らしい。淡白だと自覚している周ですら
顔にどれだけ熱が
あまりに自分が分かりやすく照れていて、真昼に聞こえない程度の声で「……くそ」と悪態づいてしまった。
幸いな事に、真昼はこちらに気付いた様子はなく、大切そうに抱き締めたくまのぬいぐるみに半分顔を
その様子がまた非常に愛らしくて、周は思わず変な声が口からこぼれそうになるのをこらえる羽目になっていた。
「……そんなに喜んでもらえたなら本望だな」
なんとかそれだけ切り出すと、ちらりとこちらに視線を向けてくる。
「こういったものをもらうの、初めてです」
「え、お前の人気なら普通に貢がれてるのかと……」
「私をなんだと……」
少し呆れた風な声と表情になって安堵してしまったのは、あの表情を直視しないで済むからだろう。
「……人に誕生日を教えた事はありません。誕生日嫌いなので、言わないようにしてましたし」
嫌い、と言い切った真昼がくまに視線を移す。
くまに向けられた眼差しは言葉とは裏腹に穏やかなもので、なんだか周の居心地が悪かった。
「普段も、知らない人とかそう
「これは受け取るんだな」
「……
小さな声でそっと告げてくまに顔を埋めながらこちらを見上げてくる真昼に、直視した事を後悔した。
図らずも
思わず衝動的に頭を
(……危なかった)
気を抜いていたら、このまま真昼の頭を撫でていただろう。そんな事をしてしまえば、せっかく喜んでもらった事が水の泡になってしまう。
「……なんですか?」
「いや、別に」
一瞬動いた腕に気付いたのか、周のもどかしいといった感情が
それだけで目を奪われそうになるのだから、美少女というものは恐ろしい。
流石に正面から可愛いから見とれていた、と言うのは気恥ずかしいし、言っても「は?」と言われるしかない自信がある。
それに、周が色んな意味で死にそうなので、この衝動は内側に隠しておこうと決めた。
「……ありがとうございます、藤宮さん」
そっぽを向いた周に、もう一度真昼のか細い声が、届いた。
「ねえねえ周、プレゼントの相手とは上手くいった?」
買い物に付き合ってもらったから当然と言えば当然なのだが、翌日千歳のにやにや笑いと詮索に出迎えられた。
他クラスである千歳が放課後クラスにやってきた、のはいいのだが、相手にしたくない類いの笑みだったため今から即彼らと別れたい気分だった。
「断じてお前の想像しているような間柄でも展開でもなかった」
少なくとも恋愛感情を抱いていた訳ではないし、どうこうなりたいつもりで渡してはいない。
喜んでもらえた、というのには間違いないが、千歳が期待しているような展開ではまずなかった。
「いやでもさあ、お前が気にかけるって事自体珍しいんだよなあ。余程関わりのある知り合いって事だし。んで女。そりゃ勘繰られるわ」
「なんのやましい関係でもない」
樹も千歳の援護に回っているが、周はばっさり切るしかない。
真昼が喜んだのはよいが、こういった面倒があるからなるべく他人には相談したくなかったのだ。
彼らの好奇心の糧にされるのはごめんなので素っ気なく返すと、樹が少し考え込むように口許に手を当てる。
「……うーん。なあ周」
「何だよ」
「もしかして、送った相手ってお隣さん?」
本当に、樹は勘がよく働く上に
「……どうしてそう思った」
「お前が関わる範囲で知り合い、世話になる範囲って言ったら隣人だろ。お前ここ地元じゃないし、女とつるむことないし。こないだおすそわけもらってたし、それで恩義感じたんじゃねえかなと」
「さあな」
「ふーん。……周、最近顔色すこぶるいいよなあ」
「あ、それ私も思った」
「おすそわけ、結構頻繁なんじゃないか。だから感謝として誕生日に贈り物したとか?」
本当に、的確に当てすぎていて周は
まるで現場を見ていたんじゃないかと思うくらいには言い当てていて、たまに樹が怖くなる。チャラいようでまめで思慮深い樹は実は割とモテるのだが、そういう部分は千歳だけに発揮していてほしい。
「憶測でよくそこまで勝手な事言えるな」
「事実が分からんから想像するしかないんだよなー。で、本当は?」
「さあな」
「ケチなやつめ」
「けーち」
「うるさい」
彼らが何といっても、口を割るつもりはない。
ぽろっと口に出したが最後、こっちが全部吐き出すまで追及をやめないだろう。樹はともかく、コイバナというのが大好きな生き物である現役女子高生は。
恋が
まったく、とため息をつきながら帰り支度を済ませ、リュックを背負う。
戦略的撤退であり、彼らの胸焼け攻撃を回避するためでもある。
「じゃあな。お前らは人の事情に口突っ込んでないでいちゃいちゃしとけ」
「言われなくてもするけどな?」
「……いっくん、尾行して
「それターゲットが居る前で言う事ではないし、お前が思っているような事は一切ないし、したところでエントランスで止まるぞ」
「ちぇっ」
可愛く唇を尖らせているが、目は割と本気だった。
冗談抜きで真面目にやりそうな千歳に
「……危なかった」
「何がですか?」
家に帰って思わずこぼすと、不思議そうに真昼が問う。
夕食を作るのにもまだ早いという時間に買い出しをしてこの家に来てしまったため、一緒に少しゆっくりしていたのだが、独り言を聞かれていたらしい。
ちなみに、今日の彼女はいつも通りだ。
昨日のあの笑顔は
「いや、まあ、プレゼントについて樹達が勘ぐってたから」
樹達に相談したからな、と付け足してため息をつくと、樹の名前は覚えていたらしい真昼が「ああなるほど」と得心したように息を吐く。
「まあ、藤宮さんがまず買わなそうなものですからね」
「そういう意味じゃないんだがな」
周が女性にプレゼントを贈りたがっている、という事自体が彼らの周像では有り得ないらしく、非常に恋愛云々を疑っているのだろう。
実際は、別に双方甘いとか酸っぱいとか苦いとか、そういった恋に伴う感覚も感情も抱いていないのだ。
「こっちの話だ。ったく、変に邪推しやがって」
たしかに、真昼は可愛いしあの時は触りたいという欲求もあった。それは否定しない。
だがそういった欲求は青少年なら誰でも起こりうるものだと思っているし、そもそも真昼がとんでもない美少女だと改めて実感してどきどきしただけで、これが恋愛感情な訳がない。
人として好ましいと思えど、彼女とどうこうなりたいなんて大それた事は思っていないのだ。
ちらりと見れば、相変わらずの整った美貌。
しかし、昨夜のような
見ていたなんて知られたら何を言われるか分からないのでスマホに視線を戻したら、ふとチャットアプリのアイコンに未読の数字が幾つか溜まっていた。
恐らく樹だろうとアプリを開いてみれば、新着欄に来ていた名前は周が想像していないものだった。
周の数少ない女性の連絡先三人、その内の一人だ。
内訳は千歳、真昼、そして──母親。
なんなんだ、と彼女専用の会話画面を開くと、周が苦手としているハイテンションな文面で考査はどうだっただの生活に不自由はないかだのそういった事が書かれている。
千歳が苦手なのは、身内にも千歳に似た……というか千歳が年を重ねればこうなるんだろうなという人間がいるからだ。嫌いではないし憎めないが、実の母親でも性格は苦手というものがあったりする。
『お
「勝手に俺の予定決められてるし……」
土曜日は特に予定がないのでいいのだが、もう少し早めに連絡しておくべきではなかろうか。
「どうかしましたか?」
呟いた言葉が聞こえたらしく、真昼がいつもの表情でこちらを見る。
「母さんが土曜の昼過ぎにじいさんのところで取れた果物送るだって。多分りんごとかかな」
「皮
「……ピーラーでいけるかな」
「そりゃ剝けますけど……厚めに剝いてしまいますから栄養分が少しもったいないですね」
うちの母親も言いそうな事だ、という感想は飲み込んでおく。
「いざとなったら丸かじりするから」
「ワイルドですね」
「めんどくさいからな」
「ずぼらですね」
相変わらず意見は
真昼は呆れたような様子を見せていたものの「まあ胃に入ってしまえばそう変わりないですからね」と納得の姿勢を見せた。
「そうだ、傷む前に全部食いきれるか分からんから椎名も要るか?」
「じゃあいただきます。果物って単価高いですからね」
なんだか
「土曜日ですよね。でしたらお礼も兼ねて先に昼食でも作りますよ」
「いっつも俺が世話になってるんだけどな」
「別に、藤宮さんに作るのは嫌いではないので構いませんよ」
くす、と本当に小さく微笑んだ真昼。
それが昨日の事を思い出させてなんだか気まずく、周は微妙に目を逸らしながら「……じゃあ頼む」と素っ気なく返すのだった。

贈り物を受け取った
インターホンの音と「あーまね」と茶目っ気たっぷりの高い声が聞こえた時、
実際作ってもらったカルボナーラは
別に、真昼が悪い訳ではない。そう、真昼が悪い訳ではない。
悪いのは事前にしつこく家に居るように言われて気付かなかった自分と──このサプライズ大好きで突拍子もない事をする、血の
「……あの、
「ない。
思えば、何とかして視察に来ようとしていた母親の言う事を真に受けたのが悪いのだ。
あの母親が、いたずらをしかけない訳がないのだ。
「……え、お母様?」
「多分うちの母親が生活出来てるのか見に来たんだろ……事前に言わなかったのは、言ったら
「ああ……」
「そこで納得されるのは複雑だが今はどうでもいい」
問題は、今ここに居る真昼をどうするかだ。
エントランスならすぐに家に帰せばいいのだが、既に扉の前に居るために家に帰す事は出来ない。かといってそのまま母親を自宅に招けば真昼と出くわし、あらぬ勘違いをするだろう。それは真昼も望むところではない
どうしようか、と悩むが、インターホンの音の間隔は
(──ああもう)
「……ごめん椎名、ちょっと俺の部屋に入っていてくれ。頼む」
「え、は、はい?」
「これ渡しとくから、俺が何とか母さんを外に引きずり出した後家に帰ってくれ。本当に悪いんだが、たのむ」
本当に致し方なく、周は
昼食を作ってもらったが後片付けは終えているので問題ない。
靴は靴箱に隠せば見つかりはしないし、今持ち込まれてるブランケット等彼女の私物は彼女と共に部屋にいれてしまえばよい。
部屋に居てその間に周が
もうそうするしかない、と真昼に余ってる合鍵を手渡して大
周の部屋ならば暖房はあるしやわらかいクッションがある。何もない床に座って腰を痛めたり体を冷やしたりなんて事にはならないだろう。
「……じゃあ、頼んだぞ。俺は今から母親の相手するから……」
顔を合わせる前に既にげっそりとしている周が玄関に向かえば、真昼も静かに周の部屋に入る。
それを見届けてから、周は渋々玄関を開けた。
「あらー周、遅かったわね。元気そうでよかったわ、寝てるのかと思ったのに」
すぐに視界に入ったのは、夏休みぶりに見た母親の顔だ。
自分の母親ながら年齢を感じさせない容貌は、家に居た頃よく見ていたにこやかな表情を浮かべている。その年齢を感じさせない、というのは顔だけではなく言動もなのだが。
「おうおう元気だから帰ってもらってもいいか?」
「まっ、親に向かってそういう事を。わざわざ数時間かけてここに来たのよ?
「遠くからお越しいただき誠にありがとうございます、帰ってくれ」
「んまーそういう事を言うのね。そういう
「可愛げなんか男に要らないだろ」
けっ、と吐き捨てるものの、母──
「じゃあお邪魔するわね?」
「待ってくれ、
「ここ、私と修斗さんの稼ぎで借りてるのだけど?」
それを言われると反論も拒絶もしようがなくて、周は本当に渋々ながらドアを大きく開けて志保子を招き入れる。
もちろん、寝室に行かないようにさりげなく寝室側を歩いてリビングに誘導するが。
「あのな母さん、くるならくると連絡寄越せ。大人だろうが」
「あら、我が息子が不摂生してないか抜き打ちじゃないと見れないじゃない?」
「ぐ。……でも、問題ないだろ。片付けてるし」
「そうね、びっくり。周ったら家では何にも出来なかったのに、案外出来てるわね。意外だわ」
リビングにたどり着いてぐるりと辺りを見回した志保子は、感心したように染々と頷いている。
もちろん片付けたのは真昼との共同作業のお陰であるし、保っているのは真昼のアドバイスと注意のお陰なので、ほぼ真昼の功績なのだが、それを今志保子に言う訳にはいかない。
「
「……おう」
若干視線が
「ちゃんと料理もしてるのね。……あら、でも二人前みたいだけど?」
マニキュアの施された指が、食器置きの部分を示している。
昼食は二人で取ったため、当然皿も二人分なのだ。そこに周が気付かなかったのは
「友人が来ていたからな」
恐らく、ではあるが友人関係に似た仲を築いているので、間違いではないだろう。性別を隠している、という点があるが。
なるべく動揺をこらえて淡々と答えた周に志保子は「ふぅん」とあまり納得のいってなさそうな声で返事をし、またリビングに視線を散らし出す。
なんとか、ぎりぎりで
「まあ、及第点……っていうか男の一人暮らしとは思えないくらいに良く出来てるわ」
志保子はしばらく観察して質疑応答を繰り返したのち、総評を述べた。
ある意味で当然だろう。真昼の手が大概加わっているのだから。
「母さんが心配する事はなかっただろ」
「ええ、びっくりしちゃったわ。家では大して何も出来なかったのに、成長したのね」
「……俺だって成長くらいする」
どの口が言ってるのか、と内心で
それがやはり自分の功績ではないため、地味に居心地が悪い。
しかしながら真実はまず口には出来ないので、このまま耐えきってお帰り願う。
一応生活チェックは出来ただろう。
もしかしたら手料理を食べたいなんて言わずともこの家を後にしてくれるのではないか──そんな事すら思った周だったが。
「あとは部屋チェックかしら」
最後に落とされた爆弾に、周は思わず目を
部屋チェック。つまり私室……寝室のチェックという事だ。
中には、当然真昼が居る。見付かれば、当初想定していた接触よりはるかに大惨事になる事が簡単に予想がつく。
「おいふざけんな。自室は母親といえど入れたくない」
「あら、何かやましいものでもあるの?」
「普通に考えて男子高校生の部屋にやましいものの一つや二つあるだろうが」
「そこは認めるのね」
「ああ認めるから入るな」
ここは、全力で阻止しなければならない。多少の恥は被ってでも、真昼の存在は隠しきらないとならない。
今、周の部屋に居る真昼を見てしまえば、志保子は間違いなくとても自分に都合のよく楽しい方向に妄想を走らせてしまう。それは何としても避けたい。
意地でも通すまいと志保子の視線を
いざとなったら申し訳ないが多少力ずくでも拒否するつもりで志保子と
とすん、と部屋の中から音がした。
「周」
「ハイ」
「何を隠しているのかしら」
「……母さんには関係ない」
「そういう事言うのね、分かったわ」
にっこり、と笑みが濃くなる。
それは、拒否を許さない圧力の笑みで、毎回この笑顔を浮かべられると周は非常に居心地が悪くなるし逆らう気力が大分
最早
ぐ、と
しまった、と後悔しても後の祭り。
物音を確かめるべく、周の横をすり抜けてドアを開けた志保子。
扉の向こうに広がっていたのは──ベッドの縁に背中を預け、クッションを
それも、
うたた寝をする事自体は、よくある事だ。
暖房が効いた暖かい部屋、昼食後の満腹時、これだけでもうたた寝するには十分な環境だ。
普通男の部屋で寝るか、という疑問は
それは、責められないものだろう。音も立てないようにじっとしておけというのは退屈だろうし、仕方ないものはある。
こちらが頭を抱える原因は、母親である志保子が来ていたタイミングで、しかもこの状態を目撃された、という事だ。
確実に、誤解される。
周が他人だったら周も勘違いするだろう。部屋に招き入れる程度に、そしてうたた寝のような油断をする程度には親しいのだ、と。
ひきつった顔で母親をちらりと見れば、真昼を見たその目が輝いていた。あらあらまあまあ、といった心の声が聞こえてくるのは気のせいか。
「あらやだ周ったら、こんな可愛い彼女作っちゃって! 隅に置けない子ね!」
きゃあ、と黄色い声を年

完全に誤解された。おまけに興奮状態。
息子が彼女を連れていると仮定しても、普通ここまで喜ぶ事はないだろう。
なのにこんなに喜んでいるのは、志保子が可愛らしいものが好きだからに違いない。
確かに、真昼は美少女と誰もが認める美貌を持っている。
寝ている時は無防備で仮面も
ひたすらに端整な顔立ちは、今は安らかに緩んでいる。
見慣れてはいたが、やはりというか改めてみれば真昼は極上の美貌を持った非常に魅力的な少女なのだ。寝顔はあどけなく、思わず触れたくなるような無防備さと愛らしさがある。
周のクッションを抱き締めてすやすやと寝ている姿は、大っぴらにはあまり言いたくない
そんな、見慣れた周でも認める美少女が、志保子から見れば息子の彼女(仮)。
興奮せずにはいられないだろう。
「もしかしてお母さん寄り付かせないのは彼女が居たから? もう、いつの間にかすっかり男の子になっちゃって」
「ちげえよ! 全体的に色々ちがう! 彼女でも何でもないから!」
「あら、言い訳しなくてもいいのよ? お母さん、周が選んだ人なら反対するつもりないし」
「いやだからそういう問題じゃなくてだな! 交際関係ではないから! 断じて違う!」
「違うもなにも部屋に入れてる時点でねえ」
「アンタが急に来たからだろうが! 普通にリビングに居ただけでも誤解するだろうが!」
「そもそもの問題として、周は好意がないとまず女の子を家にあげないだろうし、女の子は好意がない相手の家には入らないものよ?」
それを言われると、否定の材料をどうにかして持ってこようにも探しにくい。
志保子の言う通り、周は基本的に家は自分の領域であり、他人は入れたがらない。
真昼を最初に入れたのは勢いに押されたからであるが、そのあとからは料理の事抜きにしてもそもそも真昼の性格を好ましいと思っているからこうして家に入れている。
(そりゃ、好きと言えば好きだが)
周にとって、真昼という少女は見た目抜きにしても好ましかった。
学校では見せない
それが恋愛感情なのかと言えば違うと言えるが、少なくとも魅力的な少女だ。
「友人として好意はあるが、異性への好意を全部恋愛感情にするなよ。大体、こいつだってそんな意図なんてない」
素直に志保子の言葉を肯定するほど甘ったるい感情は持っていない。そもそも、真昼からしてみれば周に好意を抱いていると勘違いされても嫌だろう。
「あら、分からないものよ? 周の方こそ女の子の複雑な気持ちを理解出来るようになったと
「どう言ったら母さんはそういう関係じゃないと分かってくれるんだ……
言葉を尽くしても恋愛方向に持っていこうとする志保子に、周は
早く起きてほしい。切実に。
「ん……」
祈りが通じたのか、はたまた騒がしさに意識が浮上したのか。
真昼は、ゆるりと閉じていた
さら、と亜麻色の髪が肩から滑り落ちる。
カラメルのような色合いの瞳がとろりと潤んで揺らいでいる姿は、何というか直視するのが悪い気がするほどに無防備だ。
微妙にまだ意識が
「椎名、寝たことについてはまだいいが、誤解されてるから解くの手伝ってくれ」
「誤解……?」
「ねえねえ彼女さん、お名前は?」
ふやふやとしたまま
こうした
「え、あ、あの」
「やっぱり初対面では名乗り合うのって大事よね!」
「え、し、椎名真昼です……」
「あら真昼ちゃん、可愛い名前ね! 私は志保子、遠慮なく名前で呼んでね」
押されて思わず名乗った真昼が「助けて
自分の母だから分かるが、一度暴走を始めると止まらない。
真昼に対する興味が
肝心の真昼が困惑しているのに気付いているのかいないのか。
「あ、あの、お母様」
「あら! もうお母様と認めてくれるのね!」
「藤宮さん!」
「藤宮じゃ私も周もよ。ねえ周」
「母さん椎名が困ってる」
「周、彼女さんくらいちゃんと名前で呼んであげなきゃダメよ?」
あまりにも話を聞こうとしない志保子に周の眉間に
「あ、あの、志保子さん」
「なぁに?」
「わ、私と、藤宮さ、」
「どっちか分からないわぁ」
「……あ、周くんはそういう関係ではなくてですね」
わざとらしい志保子の言葉に、真昼が分かりやすくうろたえつつもなんとか否定している。
志保子に
「あら、じゃあこれからそうなるのかしら」
「え、あ、あの、そうじゃなくて」
「やだ、私ったらいい雰囲気をお邪魔しちゃったのかしら」
「あ、あの、ちゃんと説明させてほしいです! 周、くんとは、そういう間柄ではなくて、ご飯を一緒に食べていただけというか、周くんがご飯作れないから」
「いいお嫁さんになれるわね、真昼ちゃん。うちの周ったら家事なんにも出来ないのに一人暮らしする事になっちゃってね。そういう事なら是非支えてあげて欲しいのよ」
「や、あの」
真昼は、頑張っていたと思う。
しかし、志保子の勢いを押し
定期的に家を訪ねている、手料理を振る舞っている、共に食卓を囲んでいる、という時点で志保子の瞳の輝きが変わって更に勢いがついてしまった。
こうなれば志保子を止める事なんて周には出来ない。出来たとしても父親の修斗くらいなものだ。
「……椎名、
「そんなぁ……」
最早達観の領域に達している周は、 早々に釈明を諦めて母親の暴走を見守るしかない。
「それにしても、よく周はこんな美人さん捕まえたわねえ。お母さんびっくり」
否定するのに疲れている周と、どうしていいのか分からない真昼は共に黙る。
それを肯定と見なした……というよりは何を言っても照れ隠しで肯定と見なす志保子は、好奇心を隠そうとしない瞳で真昼を見つめている。
「どう、真昼ちゃんから見て周はちゃんと生活出来てる?」
「え。……それはその……死なない程度には……」
「そこは出来てるって言えよ」
「だって、最初部屋汚かったし」
「やかましいわ。今は保ってるだろ」
「私が掃除手伝ってるじゃないですか」
「それはその、感謝してるけど。ご飯とか、掃除とか、その辺りは本当に」
そういった点で真昼には頭が上がらない。
彼女が居てこそ今の快適な暮らしが出来ているので、土下座の感謝くらいなら躊躇いなく出来る。真昼が嫌がるのでしないが、なるべく真昼をいたわるように
ただ、この発言をあまりよろしくない方向に
「まあ、周ったら今回だけじゃなくていつも真昼ちゃんにしてもらってたのね、仕方のない子だこと。……その言い方は
「違う! なんでそうなるんだ! 隣に住んでるんだよ!」
「あら、じゃあ運命の出会いね! よかったわねえ周、こんな美人で出来た娘さんに尽くしてもらえて」
「美人で器量がいい事は否定しないが運命の出会い
「ロマンチックでいいじゃない」
「そういう意味で言ってねえ! 交際関係は全くないって言ってるんだ!」
「あらあら」
間違いなく照れ隠しだと認識している志保子に、周の
都合のよい、というより自分にとって素敵な妄想の糧になるような解釈をする母親に何度悩まされたか分からない息子は、ここ数ヵ月で一番重いため息をついた。
あまりの勢いに押されている真昼はというと、周と志保子を交互に見てはおろおろと見るからにうろたえている。
「真昼ちゃん真昼ちゃん、これは親目線の
「何言ってやがる母さんほんと黙れ」
後半がかなりの余計なお世話である。
「だってそうじゃない。むしろなんで彼女とか作らなかったのかしら。修斗さんに似て見てくれはそれなりにいいと思うのだけど。まあ
「余計なお世話だ」
「真昼ちゃんにカッコいいところ見せてあげたら?」
「やらんしこいつも見たい訳じゃない」
「またまたー。あ、なんなら真昼ちゃんが自分好みに仕立ててもいいのよ? 着飾れば周はそれなりに映えるし」
にこにこ笑いながら推してくる志保子に、真昼は困り果てて
あの冷静沈着な天使様をここまでたじろがせている志保子の存在は、ある意味すごいのかもしれない。
「母さん、本当に椎名困ってるから。つーか帰ってくれ」
「母親に帰れって偉くなったものねえ」
「本当に頼むから。どう見ても椎名が困ってるだろ」
「そう? 真昼ちゃん」
「椎名に聞くな絶対気を使うから。今回ばかりは帰ってくれ、また来てくれたらいいから」
「まあそこまでいうなら分かったわよ。彼女さんとの甘い時間を邪魔したのは事実だもの。……そんなに二人きりの時間邪魔されるのが嫌なのね」
「もう好きに解釈すればいいから早急に帰ってくれ」
強く否定するのも疲れたし、真昼もこのテンションに付き合わされて苦労しているだろう。
真昼をみれば微妙にぐったりとしている。
あとで
「あ、真昼ちゃん連絡先交換しましょうか。うちの周の生活態度とかももろもろ後で聞かせてちょうだい」
「え、は、はい……?」
最後に勘弁してほしい繫がりを作っていく志保子に、周は額を押さえた。
真昼はもうどうしようもなく流されていて、促されるままにスマホで連絡先を交換している。
これで間違いなく真昼のもとにもちょっかいをかけるようになるだろう。
満面の笑顔で真昼の手を握って「周をよろしくね」と念押ししている志保子に、周はあとで父親に「頼むから手綱握っといてくれ」と送っておく事を決めた。
「疲れた……」
「すまん台風が来て」
滞在時間はそう長くなかったのに既に二人は
どっかりと腰かけた周は顔を押さえながら深くため息をつく。真昼は遠慮がちにちょこんと座りつつも、普段ならぴんと伸びた背筋がいつもより曲がっている。
あの誰にでもそつなく対応する真昼を疲弊させた志保子に
「ほんと、勘違いさせたまま帰らせてすまん」
「いえ、まあ、実害ないですし……」
「いや割と実害は……あの様子だと椎名気に入ったみたいだし……何かと構ってくるかと……」
その点は真昼に苦労をかける事になるので本当に申し訳ない。
息子の彼女(誤解)に加えて志保子の可愛いもの好きも相まって、恐らくめちゃくちゃ気に入っているだろうし何かと世話を焼こうとしてくるだろう。お節介、というレベルで。
「志保子さんは本当に藤宮さんの事大切にしてるのですね」
「聞こえをよくしたらそうだがしつこいぞあれ……」
恐らく周がだらしないせいもあるのであまり大きく文句は言えないのだが、それでも周としては構いすぎだと思っていた。
母親については恩義を感じているし大切ではあるが、面倒くさいタイプで距離を置いておきたい人間、というのが
「……いいなあ」
小さく
「なにがだよ」
「お母様、
「あれはうるさいし過干渉気味だぞ」
「……それでも、いいなあって」
お
どこか憂いと影のある表情なのが見てとれる。触れれば崩れてしまいそうで、弱々しいと誰が見ても思う
疲労だけには決して見えないようなか弱さと
何でもない、と言わんばかりにいつもの表情に戻した真昼は、珍しくソファの背もたれに体を預けた。
「真昼ちゃん、か」
「……なんだよ急に」
「いえ。……久々に、人に名前呼ばれたなあって。いつも名字でしたから」
あの人気者の天使様が名前で呼ばれない、というのは意外だったが、逆に真昼を名前呼びするのはおそれ多くて気が引けた人間だらけなのだろう。
学校では
あと、あだ名で呼ぶ人も少なからずいる。本人は非常に嫌がっているが。
「まあ仲良い友人が居なければ親くらいだろうな」
「親には呼ばれませんよ、絶対に」
冷えた声の即答が来た。
思わず真昼の顔を見ると、何の色も表情には浮かんでいない。
まるで全て抜けきったような、無機質とすら取れる無表情。端整な美貌のせいか、まるで人形を相手にしているような錯覚すらある。
ただそれも一瞬で、周の視線に気付いた真昼は無表情を消し、どこか困ったように
「……とにかく、珍しいなって」
そう呟いて、そっと吐息をこぼした。
真昼の親との折り合いが悪いのは、察していた。
親について触れてしまった時にたまに見せる冷たい表情や、親と外食をする事はない、誕生日が嫌い、といった発言から、家庭環境に問題があるのだと容易に想像出来たのだが──親から名前すら呼ばれない、とまでは思う筈がない。
『……いいなあ』
先程呟かれた言葉は、どんな気持ちで
「真昼」
自然と、呼ぶ事のなかった名前を、口にしていた。
ぱちりとカラメル色の瞳が瞬く。
不意をつかれたのか、どこか
「名前くらい誰だって呼んでくれるだろ」
「……それもそうですね」
ぶっきらぼうに付け足せば、遅れて淡い笑みが浮かぶ。
ほんのりと
「……周くん」
小さな声で自分の名を呼ばれて、胸のざわつきが大きさを増す。
先程までは、母親に対してしか使っていなかったからか、あまり気にもとめなかったのだが……こうして面と向かって呼ばれると、むず
「外では呼ばないでくださいね」
「……んな事分かってるよ。そっちこそ外で口滑らせるなよ」
「分かってます。秘密、ですもんね」
周は「おう」とだけ素っ気なく返して、体勢を変える振りをして彼女の笑みから逃れるようにそっぽをむいた。
土曜日の母親襲来で、周と真昼の互いの呼び方は変わったものの、それ以外には特に変わった事はなかった。
急に仲良くなる訳でもない。ただ、呼び方が少しフランクになって、多少真昼の態度が軟化した、くらいだろうか。
「……あの、周くん」
日曜日の夕方、いつもより早くやってきた彼女は微妙に気まずそうというか、困った風な顔でやってきた。
招き入れたのはよいものの、よく分からない態度に周は困惑していた。
名前を呼ぶ事に抵抗があるのかと思ったが、名前を呼ぶ時には
とりあえず互いにソファーに座って、真昼の様子を見ていたら、スカートのポケットからハンカチを取り出した。
いきなりなんなのかと思えば、丁寧に隅を合わせて畳んでいたハンカチを開いて、包まれていた鈍く光を反射する
見覚えがあるのは、つい昨日彼女に手渡したままのものだったからだろう。
「鍵、お返しします。結局あの時出られなかったですし。その、忘れてて返しそびれていて……申し訳ないな、と」
「なるほど」
どうやらそのまま鍵を持って帰っていた事が居心地悪かったらしい。
妙な様子の真昼に得心した周は、ハンカチに載っている鍵を見つめる。
よく考えてみれば、真昼はほぼ確実に毎日夕ご飯をこの家で作っている。その度に周が玄関に出ているのだが、寄り道をして家に居なかったり少し待たせたりしてしまう事があった。
今の季節玄関の前で突っ立たせているのは、女性にはきついのではないだろうか。
女性が体を冷やすのは大敵だと聞くし、周としてもしばらく自分が棒立ちになると考えたらあまり
ほぼ毎日ここに来るのだから、彼女が鍵を持っていた方が楽なのではないだろうか。
「別にそのまま持っててもいいけどな」
「え?」
「
まあ言ってしまえば渡したからにはしばらくはお世話になるという事なのだが、真昼は鍵を受け取らなかった周を不安げに見ている。
「で、でも」
「というかいちいち玄関に出向くのめんどくさいし」
「本音
「お前、悪用したりしないだろ」
「それはそうですけど……」
一応一ヶ月以上、ご飯をおすそわけしてもらったりここで作ってもらったりして、真昼の人柄は理解しているつもりだ。
彼女は、まず常識的で良識的、悪事なんて出来っこない性格だ。
この鍵を得たところで、誰かに渡したり周が居ない間になにかするという事はほぼ確実にないだろう。信用してもいい相手だ。
「お前だって毎回インターホン鳴らして待つの面倒だろ」
「そうだとしても、あなたには警戒というものが足りない気がします」
「お前を信用して渡してるつもりなんだが」
その一言に目を丸くした真昼は、なんとも言えなそうに
戸惑いと、他によく分からない何かが表情に浮かんでいる。
まあこちらとしては手間を省くために渡したままにしたいだけで、彼女が嫌だというのなら素直に引き下がるつもりだった。
真昼はというと、しばらくじっと周と鍵を交互に見て──そっと、ため息をついた。
「……分かりました。お借りします」
「ん」
「周くんって、大物なのか無頓着なのか分かりません」
まったく、と
「俺らしいだろ」
「そういう事を自分で言うものではありません」
ツン、とそっけない声で注意されて、余計に周の笑みが深まる。
こういった
そもそも名前呼びを許してくれたのだから、慣れていなくてはおかしいのだが。
仕方ない人ですね、と言わんばかりの呆れを多分に含んだ眼差しで見られるものの、冷たいというよりはほんのりと温かみがあるものだ。
周のおちゃらけが冗談と分かっているのだろう。
「では遠慮なく使わせていただきますけど、家に何かされても知りませんからね」
「何かって?」
「……いつの間にかお掃除してびっくりとか」
「そりゃありがたいな」
「冷蔵庫に作り置き沢山放り込んで冷蔵庫圧迫するとか」
「朝ご飯が幸せになって晩ご飯の品目が増えるな」
真昼のいたずらが平和すぎて、というかむしろありがたすぎてこちらとしてはウェルカムなのだが、あっさり流された真昼としては微妙に不服そうだ。
脅しにならない脅ししか出来ないのは真昼の善性が如実に表れているので、微笑ましいものである。
「何か
「してないが」
流石に笑っていると

廊下の壁に
先週行われたテストの順位が出ていたので、周は同級生と同じように見に来たのだ。
結果としてまあいつも通り二十一位、割とよいがさほど目立たない順位に居た。手応えとしても今までと変わらないとは思っていたので、予想通りの順位に居て少し
ちなみに、
本当に才女なのだが、努力を欠かしていない事もよく知っているので、流石としか言えない。
夕食後に勉強しているのもよく見る。
元々の頭の出来がよいのもあるだろうが、本人のたゆまぬ努力が真昼を一位の座に置いているのだろう。
「
「流石天使様、頭の出来が違う」
「……どうしたんだ周、そんな顔して。順位悪かったのか?」
一緒についてきた
ちなみに五十位までしか貼り出されないため、樹は自分のではなくあくまで周の付き添いといった形だ。
「なんでもねえ。二十一位だった」
「おお、今回は前よりよかったんだな」
「多少な。誤差範囲だろ」
「おうおう賢い人は言う事が違いますなあ」
嫌みを笑いながらわざとらしく言ってくる樹には「はいはい」と軽く流すだけにしておき、改めて順位表を見る。
本当に、よく頑張っていると思う。
あまり見せたがらないが、隠れたところで努力をする彼女は、こんなの当たり前のように見せているが相当に頑張っているだろう。
周りはすごい、と
それは、とても真昼にとって息苦しいのではないだろうか。
「……せめて、
「ん? なんか言ったか?」
「別に。ほら教室に戻るぞ」
「ういっす」
「あれ、周くんこれ何ですか?」
一度着替えてからスーパーで買った食材を携えてやってきた真昼が食材を冷蔵庫に入れようとして、どうやら見慣れぬ白い箱に気付いたらしい。
「ん? ああ、ケーキ」
白い箱の中身は、ケーキだ。恐らく真昼も箱の形状で薄々察していたとは思うが、一応聞いてみたのだろう。ちなみに、
「……ケーキ好きなのですか?」
「いや別に。お前に買ってきた」
「なんでまた」
「お前学年一位だったからささやかなお祝いくらい、いいだろ。一位おめでとう」
自分に、というところで目をしばたかせている真昼。
本当に、想定外だったのだろう。
「い、一位は毎回取ってますし、そこまでめでたい事でも」
「それでもいつも頑張ってるし、たまにはご褒美って形もいいんじゃないか。ショートケーキだけど嫌いじゃないか?」
「え? き、嫌いではないですけど……」
「ん、ならよかった。食後に食ってくれ」
真昼は気を使われすぎると困る様子を見せてくるので、あっさりとした態度の方がいい。
彼女は他人には割と尽くすタイプの人間だが、自分の事となると非常にストイックで
キッチンでまだ固まってる真昼に苦笑した周は、ゆっくりと息を吐いて彼女の再起動まで彼女を眺める事にした。
食後、やや緊張した面持ちでケーキを皿に乗せて持ってきた真昼に、周は思わず吹き出した。
「な、なんで笑うのですか」
「いや、なんでもない」
「なんでもなくない気がします」
「気にすんな」
ただ、真昼が妙にカチコチと
ただあまり笑いすぎると不機嫌になりかねないし労うという目的が果たせなくなりそうなので、ほどほどのところでやめておく。
一緒にコーヒーを持ってきてケーキと共にテーブルに置いた真昼が、ソファに腰かけてくる。
そこでも微妙にぎこちない動きだったので笑いそうになったものの、隣にいるので流石に控えておいた。
ちら、と真昼が遠慮がちに周を見上げてくる。
「ん、おめでとさん」
「……ありがとうございます。でも……」
「いいから素直に受け取っとけ。頑張ったのは事実だろ」
「そう、ですけど」
「ほら、さっさと食べとけ。たまにはお前も自分甘やかしとけ」
もう買ってきてお前にやったんだから、と付け足すと、真昼も少し申し訳なさそうにしつつも小さく
「ありがたくいただきます」
「どーぞ」
手をひらりと振っておいたら、真昼は何だか慎重な手つきでケーキをフォークで一口大に切って口に運んだ。
女子は甘いものにうるさいというイメージがあるが、千歳もよく食べている店のなら問題ないだろう。
その証拠に、口にした真昼が目を少し丸くして、それから
あまり表情が変わる事のない真昼だが、最近は少しずつ分かりやすく喜怒哀楽を表現してくれるようになっている。
ゆっくり食べながら浮かぶ柔らかな表情は、食べているだけで絵になっていた。
「……? どうかしましたか」
「いや、なんでも」
つい凝視してしまった事に気付いたらしい真昼が、不思議そうに首をかしげている。
いつもより少しだけ幼さの見える表情に、周は先程まで見つめていたのに視線をさまよわせてしまう。
入れ代わりにじっと周を見ていた真昼は、ふと思い付いたようにフォークを使ってケーキを一口分取って、周の方に向けた。
いわゆる、あーんという体勢に入っている。
「え、い、いや食べたかった訳じゃないというか」
「違いましたか?」
「……いや、まあ、その……もらえるなら、もらうけど、さ」
流石にこれは想像していなくて見るからにうろたえてしまった挙げ句、うっかり承諾してしまった。
この年にもなって、それも異性に、その上とんでもない美少女に食べさせてもらうなんて、ある意味幸運なのかもしれないが──素直に喜べるほど、周は
「元々周くんが買ってきたものですので、周くんにも食べる権利はありますし」
提案した真昼はというと全く意識していなさそうで、普段の表情のまま周の口許にケーキを差し出している。
普通異性にあーんをするなら多少なりと意識しそうなものなのだが、真昼を見ても不思議そうにしてるだけ。
この純粋な厚意によるあーんを拒む訳にもいかず、周はええいと思いきってケーキに
口に広がるのは、とても甘い味だった。
「……あめえ」
「そりゃケーキですし」
確実にそれだけではないのだが、真昼は気付かないだろう。
もぐ、と嚙んでもとにかく甘い。精神状態の影響がかなり大きい。
「……何とも思ってなさそうなんだよなあ」
こちらはこんなにも甘さと恥ずかしさとむず
それが地味に悔しくて、周は「ちょっと貸せ」と真昼の手からフォーク奪って同じようにケーキを差し出す。
やられたらやり返しておくべきだろう。
「ん」
「……あの」
「食べろ」
いささか強めな口調で言ったせいか、真昼は困惑を強めていた。
ただ、自分もやったからなのか、拒む様子は見せず、おずおずと同じように
もぐ、と口が
じーっとその様子を見ていると、段々と真昼の様子が変化してきた。
最初は困惑が感情の大半を占めていたのだが、口を動かす度に微妙に真昼の
ケーキを飲み込む頃には、すっかり恥じらいを表に出して隠せていない真昼が出来上がっていた。
女子
「で、感想は」
「お、
「ちがう。食べさせられた気分は」
今なら先ほどの周の気持ちがよく分かるだろうと問いかければ、瞳を伏せて僅かに体を震わせる。
「……非常に居たたまれなくなりました」
「だろうな。こういうの、人にすると勘違いされるぞ。やるなら女子同士でやっとけ」
俺の気持ちが分かったか、とぷい、とそっぽ向いた周に、真昼は消え入りそうな声で「はい」と返した。
安全な人間だと認識しているからあんな
意識せずにやった真昼には困ったが、まあ悪い気分でもないのであまり責められたものでもない。
ただ、ひたすらに口の中に残る味が甘いだけで。
(油断されるのもこまったもんだ)
信用してくれるのは
そう結論付けて、周は隣で少し照れた風に縮こまってる真昼に小さくため息をついた。

平日の昼食は学食でどうとでもなるのだが、休日だけはそうはいかない。互いにそれぞれ用事があったりするので昼食まで一緒なんて無理だし、そもそも食べたいなんておこがましすぎる。
夕食をわざわざ作ってもらっているのだから、たかが休日の昼食くらい自分で用意するべきだ。
ただ、あまりコンビニを多用していると真昼が「ちゃんとバランスよく食べるんですよ」とちくっと刺してくるし、外食は費用がかさむため毎回外で食べるのも気が引ける。
なので、休日の昼食が一番困っていた。
「……料理するべきだろうか」
どこに行く用事がある訳でもないので家に居たのだが、あと一時間で正午を迎える辺りで本日の昼食に悩み出した。
これが真昼なら何の
別に、周は料理が壊滅的に出来ない、という訳ではない。
漫画でよくあるダークマターを製造とかはしない。見かけと味を犠牲にしてよいのなら、食べられるものは作る事が出来る。料理というより料理らしきものといった感じに近いが、それでも食べる事には問題ない。
ただ、真昼という極上の料理に慣れてきている今、自分の料理を完食出来るかが危うい。好き好んで
(……あー、ほんと真昼に駄目人間にされてる)
完全に真昼の料理の
ただ、また外食をするのは気が引ける。コンビニ弁当も飽きてきた。
あまりにも真昼に頼りきりで自炊なんてする意味すら見いだせなかったのだが、流石にそろそろチャレンジした方がいいのではないだろうか。
いつまでも真昼が居る訳ではない。今はこの仲に落ち着いているが、高校はあと二年は残っているのでその間に何かあってこの関係が壊れるかもしれないし、そもそも大学に行ってしまえば別々になる。今までの関係を続けるのは無理だろう。
(この際少しは頑張ってみるべきなんだろうな)
先を考えて多少なり努力してみようと思い立った周は、ソファから立ち上がって財布を手に取った。
「あれ、スーパーに行ってきたのですか?」
スーパーからの帰りがけ、丁度いいのか悪いのか、エントランスで真昼と鉢合わせた。
彼女も出かけてきたらしく、近くにある文房具店の袋を携えている。
隠す必要もないと「おう」と返事してスーパーの袋を揺らして見せると、真昼は不思議そうな表情を浮かべている。
「あれ、昨日の買い出しでは量足りなかったのですか? メモの通りに買ってきてもらっていたとばかり……」
「い、いや、そうではなくて……その、昼くらい自分で作ってみようかと思って」
「……周くんが?」
一応説明したのだが、真昼の
当然だろう。真昼に頼りきりであるし真昼と会う前は惣菜やコンビニ弁当に頼ってきた周が自炊するなんて、到底信じられないだろう。
「悪い事言いませんので止めておいた方が無難ですよ。
「……別に、出来なくはないんだぞ?」
「
的確に指摘した真昼にぐうの音も出ない。
まさに自分でもそう思っていたので、反論が出来なかった。
「するというなら止めませんけど、下手に理想を知っている分現実との格差を思い知ると思いますが」
「……ごもっともで」
理想、というのは真昼の料理だろう。真昼は自分の腕に割と自信を持っているし、周が毎日美味しいと言いながら食べているので、真昼の料理を好んでいる事も知っている。
「でもさあ、その、真昼が栄養とか言ってるし、もし今後大学とかで本当に一人で生活する事になったら、真昼を頼れないだろ」
あまりに真昼に頼りすぎていると、真昼が居なくなった時のショックが大きすぎる。ただでさえ真昼に駄目人間にされているのだから、最低限の事くらいは出来るようになりたい。
周の言葉に真昼は目を丸くして、それから少し感心したように吐息をこぼす。
「……将来を見据えて行動しているのはよい事だと思いますけど、なら
「え?」
「監督が居ないで何かしらやらかすより監督して事故を防止した方が余程いいです。周くん、キッチンぐちゃぐちゃにしない自信ありますか?」
「……ないです」
料理が下手な人間はそもそもキッチンを
周が控えめに
「ですので、私が居た方がいいでしょう」
「お願いしてもよろしいでしょうか」
「嫌なら提案していません」
ややツンとした声で返されたが、周を思って言ってくれた事なので全く気にならなかった。
頭を下げると「別にそんなかしこまらなくてもいいです」と慌てたように返されたので小さく笑い、真昼と一緒にエレベーターに乗って自宅のある階に向かう。
「……ちなみにエプロンはあるので?」
「そこは抜かりない。調理実習の時に使うために買った」
「使用したのですか?」
「あんま意味なかったな。計量と皿洗いばっかやったから」
「でしょうね」
想定内だと言わんばかりに息を吐いた真昼を伴って、周の自宅に入る。真昼のエプロンは周の家に置かれている。自分の家にも置いているらしいので、
エプロンを身に付けいつものように髪を一つにまとめた真昼は、周がタンスの奥から引っ張り出してきた濃茶のエプロンを身につけた姿を見て目を細める。
「こう、周くんって普段身に付けないからエプロンに着られている感がしますね」
「うっせ、悪かったな」
「まあしかたないですね。……で、メニュー決まってるんですよね、材料買ってきたという事は」
棚に置いた材料の入った買い物袋を見た真昼に、周も頷く。
「野菜炒めとオムレツ」
「……私が注意してるから野菜摂取するのと卵が好きだからオムレツですね」
「よくお分かりで」
「ちょっと考えればわかります。野菜炒めの味付けは?」
「こう、焼肉のたれをがばっと」
「男らしい豪快な味付けですね……美味しいのもわかりますけど……」
「調理しようとするだけましだろ」
焼肉のたれがなければ塩胡椒と
使えるものはなんでも使うつもりなので焼肉のたれに感謝しつつ、真昼にならって手を洗う。
その間に真昼は周が調理しやすいように器具を用意したり材料を使いやすいように並べたりしている。手際がいいのは流石としか言いようがない。
「野菜炒めは火の通りが均一になるように野菜を切って炒めるだけですからね。……切り方分かります?」
「
流石にそれくらいは分かる。
きっぱり言い切って真昼が見守る中キャベツを刻む事になったのだが……それが
真昼はアドバイスをしたり手本を見せたりはするが、本人の自主性に任せる形で見守っている。一応危なげな時は手を軽く添えて修正してもらったりはしていて、ちょっとずつ慣れてきて補助が外れた頃にやらかしたのだ。
「……いってえ」
「……薄々こんな事になるだろうと思ってました。ほら、貸してください」
エプロンのポケットから
「用意周到な事で」
「料理が下手な人間が怪我しない方が珍しいですから」
「信頼されてねえ」
まあ早速指を切っているので信頼される訳がないな、と自分でも分かっていたので笑う。
「でもまあ、周くんが頑張ろうとしているところは認めます。えらいですね」
「そりゃどうも」
「まあ先に呼んでほしいものですが」
「流石に休日まで作らせるのは悪いし」
「作る努力は認めますが、何かやらかして対処に困って結局私を呼ぶくらいならまだ最初から呼ばれた方がマシです」
「ハイ」
今回は軽い怪我だけで済んでいたからよいのだが、キッチンが大惨事になったり変な使い方をして電子調理機器が稼働しなくなったりした場合周では対処しようがない。
真昼が言う事はごもっともなので、何も言い返せなかった。
「……揚げ物とか絶対にしないでくださいよ。火事起こしそうです」
「揚げ物を作れるほどレベルが高くない」
「揚げ物はそこまで難しくないのですが……よくそれで一人暮らし出来ますね」
「すみませんね」
どうせ
べつにへこんだ訳でも怒った訳でもないので心配しなくてもいいのだが、真昼はちょっと気に病んだのか
「……その、周くんに揚げ物をさせるのは怖いですから、もし揚げ物が食べたくなったなら早めに言ってくださいね」
「じゃあ明日メンチカツ食べたい」
あっさり機嫌を直したように声を明るくして言うと、真昼は
「付け合わせの千切りキャベツもたっぷり食べるのですよ。あとお野菜たっぷりのお味噌汁にしますからね」
「はいはい。……ありがとな」
「何がですか」
「色々だよ」
日頃から真昼にはお世話になっているし、彼女も彼女で心配から色々言っているので、周もたまに憎まれ口を
微妙に照れくささを感じたので本当に小さく「助かってる」と続けて、周は再び野菜に向き直った。
「いただきます」
「おう」
野菜達と格闘する事小一時間、食卓には不格好に切られた野菜を炒めたものと、形の
当然、綺麗なオムレツはお手本で真昼が作ったものだ。周が作ったのはオムレツもどき、もといスクランブルエッグである。
ちなみに味見をするという事で周のオムレツ(仮)は真昼の手元にある。周にはオムレツといったらこれという綺麗な形のオムレツが用意されていた。
手を合わせて食材に感謝をしてからいただくのだが、真昼はボロボロになった卵を
「……味のないスクランブルエッグですね。塩コショウ入れてないですね?」
「忘れてたんだよ。あと、オムレツを作るはずだったんだ」
「かき混ぜすぎですね。そぼろになるまで箸で混ぜてどうするんですか……と注意したのに」
「すんません」
味を付け忘れたのは真昼がオムレツを作っている間に周が卵を混ぜたからで、他はちゃんと指示されていた。味も形も明らかに周のミスである。
ちなみに真昼手製のオムレツはふわふわとろとろで非常に美味なので、格の違いを見せつけられた。
「……でも、周くんにしては頑張ったと思いますよ。作ろうとする気が見えたのが大事な事です。ただ、まだ私の目がないところで料理させたら後片付けが大変になりそうなのでゆっくり練習していってほしいですね」
「……お前に頼りっぱなしになるだろ」
「何を今更」
「うっ」
「まあ冗談……ではないですが、私は料理を食べてもらう事が好きですし、料理教えるのも嫌いではないから構いませんよ」
「……ありがとうな、いつも」
真昼の厚意で現状に至っている訳なので、本当に頭が上がらない。
ただあまりへこへこしても真昼が嫌がるのでほどほどで顔を上げ、真昼を
真昼は
「もし周くんがちゃんと料理作れるようになったら、お役御免ですかね」
周がご飯を作れるようになったら、真昼は周にご飯を作る必要はない。
それを感じて、周は首を振った。
「や、それはその……まだまだ真昼の料理が食べたいというか……真昼の料理が一番うまいから、出来れば食べていたいというか。情けなくておこがましい事を言ってるけどさ」
作ってもらう立場なのにわがままだと自覚はしているが、やはり自分の料理よりも真昼の料理を食べていたい。
真昼の料理にすっかり夢中になっている身としては、それがなくなると精神的に割と死活問題なのだ。
懇願するように控えめに願うと、真昼は目を丸くして、それから小さく笑った。
うっすら浮かんだ
「ふふ。仕方ない人ですね。当分はやめるつもりはないから安心してもいいですよ」
「……さんきゅ」
「たまにお手伝いくらいはしてもらいましょうかね。ピーラーで皮
「子供のお手伝いみたいだな」
「周くんはそこからスタートですよ?」
実際子供並みの腕前なので拒めず口をつぐんだ周に、真昼はまたおかしそうに笑った。

「ねえ
「駄目」
唐突な提案をきっぱりと断れば、分かりやすく
すこし先に控えた聖夜……家族と離れている上ぼっちである周には特に縁のないイベントではある。ただ、千歳と
わざわざ昼休みにこうして周と樹の教室に押し掛けて提案してきた千歳は、周の即答に頰を膨らませている。
「いーじゃん周どうせ一人で……あっ、もしかして彼女」
「出来てないし居ない」
「ならいいじゃん。それとも嫌だった?」
「まあ周が嫌ならオレらは別にいいけどさ」
彼らなりに友達を気遣ってくれたのだろう。
あと、のんびりいちゃつく場所を求めていたというのもあるだろうが。
そんな申し訳なさそうな顔をされても悪い気分になるし、嫌という訳ではない。
渋るのは、彼らが私的な場では尋常でなくスキンシップが激しいところを見せられるのが恥ずかしいのと、真昼に色々と説明する手間がかかるからだ。
極論言えば、真昼に先んじて彼らが帰るまでこちらにこないように言っておいて、普段真昼が居る痕跡を消しておけばいいのである。
「嫌じゃないけどさ……分かった分かった。二十四日だろ? どうせ夜前には解散だろうしそのあとお前ら二人でいちゃついて熱を抜いて行けよ。くれぐれもうちで過度にいちゃつくなよ」
まあそこまで拒む事でもないか、と承諾すると、千歳の顔がにっこりと笑みを浮かべる。
「仕方ないなあ、それで妥協しよう」
「何様だ」
口ではちょっぴり小生意気な事を言ってるので遠慮なく頰をつねると「いひゃーい。いっくーん、あまねがいじめへくるー」と若干
「こーら周、ちぃをいじめるなよ?
「はいはい俺の代わりにしっかりとつねっておいてくれ」
「任された」
「任されたらだめなのにー!」
これもいちゃつく口実になるだろうなあと思いながら樹につねるのを譲れば、案の定二人はうにうにと頰をつねったりしながら戯れている。
つねられている千歳が実に
「……俺帰っていい?」
帰るも何もここが自分の教室なのだが、当てられる前に彼らから少し距離を取りたかった。
「だめー。ちゃんと予定立てなきゃだめでしょ。ケーキとかご飯の手配しなきゃね!」
「俺は作れんぞ」
さすがに周にはクリスマス用のご飯なんて作れっこない。
真昼なら恐らく普通に作れるだろうが、彼女の手を借りる訳にはいかないだろう。
ひらりと手を振って無理だと主張する周を、
「なんだよ」
「作れないのに、そんなに健康そうになったんだなーって」
「どうでもいいだろ別に」
「まあまあちぃ、周にも事情があるんだろう」
「えー、いっくんも知りたがってたじゃん」
「俺は後で教えてもらうから」
「教えない」
勝手に約束すんな、とジロりと
しつこくは食い下がらないのが彼のよいところではあるのだが、たまに思い出したようにつついてくるのはいただけないところでもある。
「まったく。……まあ、ご飯は出前とかでいいんじゃないか。ケーキは予約しとかないといけないけどさ」
周への
当然と言えば当然だが、ケーキを自前で用意するのは無理だし、食事も用意出来ない。なら出来合いの物を用意するのが流れだろう。
「あ、じゃあピザがいー! ケーキはいつもの店で予約しとくね、まだ受け付けてたし!」
「そこはチキンじゃないのかー」
「いっくんもピザの方が好きじゃん」
「まあなー。さすがちぃ、分かってる」
「えへへー」
勝手にピザにされているが、周としてもピザは嫌いではないしパーティーらしさが出ていいのではないかと思った。
この調子なら、ご飯は周や樹がよく頼む店の宅配ピザに決定するであろう。
ピザと聞いてふと、真昼を思い出す。
はむはむと小動物のように食べていた真昼。妙に愛らしいと思ってしまったのは、普段お上品に食べているところを見ていたからだろう。
ケーキも真昼に先日食べさせたな、と思い出していると、自然と頰がうっすらと熱を帯びてきた気がする。
(もうあんな事はすまい)
食べさせ合うなんて恥ずかしい事、もう出来ないだろう。樹と千歳のような仲むつまじいカップルでもあるまいし、機会も訪れない
「……周、どうしたの?」
「あ、いやなんでもない。じゃあケーキの予約はお前に頼むわ」
一瞬思い出してしまってぼーっとしていた周を
「はーい! ピザも予約しとこうねー!」
テンションの上がった千歳の声を聞きながら、周は家に帰ったら真昼にクリスマスの予定について聞く事に決めた。
「クリスマスの予定ですか? 特にありませんけど」
洗い物が終わった後にソファに腰かけていた真昼に問いかければ、実にあっさりとした返答があった。
てっきり女子会をしたりするのかと思っていたのだが、予定はなかったらしい。
意外だと顔に出ていたらしく、真昼は周を見てほんのりと
「基本的に、私と交友のある同性の級友は大体彼氏が居ますよ。男性から誘われてもお断りしていますから、予定はどうしても空きますね」
「男子涙目だな」
外行きの際の真昼は非常にガードが固く、淡い期待を込めて真昼を誘った男子達は堅牢な守備に涙を飲んだ事だろう。
周からしてみたらよく誘えたな、という感想である。自分に自信がなければあの天使様を誘えないだろうし、陽キャはすごいなと感心すらしていた。
「……そんなに私と過ごしたいものなのですかね」
「あわよくばお近づきになりたいんだろ」
「なんのために?」
「そりゃ、お付き合いしたいからでは?」
「
「……付き合ってあれこれしたいんじゃないのかね」
「不純ですね」
ばっさり切り捨てられている男子諸君に内心合掌しつつ「まあでも」と付け足す。
「そういうやつばっかりじゃないと思うから、あんま疑ってやるな。お前なら、男が向けてくる視線の質くらい分かるだろ」
「そうですね。全員が全員
「俺がお前を不埒な目でいつ見たんだ」
そもそもそんな事を考えていたら真昼が気付いて離れていただろう。
無害な男だから彼女の隣に居座れるのであって、仮に
「そうでしょうね。周くん最初から私に興味なさそうでしたし」
「まあ」
「ですので、信頼してます」
「そりゃどうも」
男としてそれでいいのかという信頼のされ方をされている気がしなくもないが、ひとまず安全な男の立ち位置に不満はない。
「……で、私のクリスマスの予定を聞いてきた周くんは何か予定が?」
「ん? ああ、俺、二十四日は昼に樹達がここにくるから、まあいつも通りだが晩ご飯が遅くなるかもしれんっていう連絡しようと思ってな」
ようやく話が本筋に戻ってきたので改めて説明する、真昼は納得したように
「分かりました。そのクリスマスパーティーが終わったら呼んでください、そこからご飯作りますので。用意だけはしておきますね」
「おう、なんかすまん」
「いえ。楽しんでください」
「……
「慣れてますし、一人は」
何て事のないように告げられて、少しだけ胸が痛んだ。
彼女の脳内でも親の事が一瞬よぎったのかもしれない、どこか
「……あー、その、非常におこがましい申し出ですが、イブは無理でもクリスマス一緒に居る、というのは」
なんというか、こういった提案をするのは、非常に気恥ずかしい。
特に他意はないのだが、クリスマスを共に過ごそうと誘うのは、普通特別な意味を持つのだ。
決して、他意はない。
ただ、真昼がどこか寂しそうな眼差しで
提案に、真昼は目をぱちりと瞬かせていた。
「一緒にって、何するのですか?」
「え? あー、別にする事ないよな。ごめん」
そこを指摘されると、周としてはそれ以上は強く押せない。
他人に見かけられた場合の面倒を考えれば一緒に出かける事はまずない。
では家で過ごすという事になるが、この家には真昼の興味を引くようなものはほとんどないだろう。となると何もせずに二人で
それくらいなら、別々に過ごした方がいいのかもしれない──そういう考えで撤回しようとしたのだが、真昼は周を静かに見つめていた。
「……じゃあ、あれ、してみたいです」
予想外だったのは、真昼が存外乗り気だった事だろうか。
か細い指が、テレビの方を示す。
正しくいうと、テレビボードの中に格納されているゲーム機だろう。
最近夕方は真昼が居るのであまり起動しなくなったそれに興味を示したらしい真昼は「ああいうの、した事ないですし……」と小さく希望を示している。
別に真昼がしたいというなら拒む理由はないのだが、クリスマスに特に交際している訳でもない男女がゲームして過ごすというのは何だかシュールな気もする。
色気は全く求めていないにしても、やや複雑な気分になってしまうのは仕方ない。
「いや、まあ、それでもいいけど……いいのか? ゲームとかで」
「駄目なのですか?」
「駄目ではないが」
「じゃあ、それでいいです」
「お、おう」
それでいいんだ……とは思ったものの、真昼の希望なので出来うる限り
ささやかな楽しみくらい、あげたい。いつもお世話になっているしあまり何かを希望する事のない真昼なので、持っているものなら何でもプレイしてもらおう。
特にクリスマスに予定を入れている訳でもないし、真昼と食事が出来るだけでももうけものだ。
「ま、クリスマスとか関係なしにまったり過ごせばいいだろ」
「そうですね」
小さく笑った真昼が何だか直視しにくくて、周は頷いてさりげなく顔を
「メリークリスマス!」
そしてやってきたクリスマスイブ。
学校は既に冬期休暇に入っており、恐らくみな思い思いの過ごし方をしているであろうこの日、樹と千歳は荷物を抱えて周の家に集合していた。
時刻は十三時頃。
テーブルの上には既に宅配を頼んだピザやジュースが並んでいる。こんな時間になったのは、予約していたといえどクリスマスの混雑には
昼食にするには問題ない時間であるし、二人も昼を過ぎてからやってきたためそう待ってもいないので、皆気にした様子はなかった。
「はいはいメリークリスマス」
「周ノリがわるい! もう一度」
「Merry Christmas」
「発音よく言ってるけどやっぱりノリ悪いね?」
元々テンションが高い千歳と一緒にしないで欲しかった。
樹はこれでもテンションはあげている方だと気付いているので千歳をなだめつつ、いつものややチャラいながらも
「まあまあ。そんな事はいいだろ、とにかく食って遊んで寝ようぜ」
「うちで寝んな
「冗談だよ。寝るならちぃんちで寝るし」
「親が居ない内にしとけよ」
「えー、周ったら何すけべな事考えてるのー?」
にやにや笑いの千歳はスルーしておき、周は食器とコップを取りにキッチンに向かった。
千歳はつまらなそうに唇を
キッチンは、当然ながら
「意外なまでに綺麗だね」
「そりゃどーも」
適当に流して食器棚から小分け用の小皿やらコップやらを取り出して千歳に半分ほど渡していると、千歳は食器棚をじーっと見つめていた。
「……なんだよ」
「べつにー?」
にまー、という笑みに何だかねっとりとしたものを感じたので背筋を震わせつつ、あくまで無視の方向を決め込む。
彼女の中で多大なる誤解的な何かをされている気がものすごくしたが、口にはされていないのでそれが何かまでは分からないのだ。
ほんのり上機嫌になっている千歳に
「しかしまー綺麗だねえ部屋。広くてゼータク」
部屋に置いたオーディオから流れるクリスマスっぽい音楽を聴きながら食事をあらかた摂り終えたあと、一息ついた千歳は三人しか居ないリビングをぐるりと見回して
広いのはここを借りている両親のお陰であるし、綺麗なのは真昼が掃除を手伝ってくれたからなのであまりコメント出来ず「そりゃどーも」とだけ返すに
「まあ一時期すごかったよなー。よく綺麗になったもんだ」
「うっせ」
「うんうん、女の
「何でそうなる」
部屋が綺麗になった、から
「んー? 何となくかなあ。周の性格的にちょっと掃除の仕方が違うかなって。本の並べ方とかコードとか傷まないようにまとめてたりとかもあるんだけどさー。周の趣味じゃなさそうな食器幾つかあったんだよねー」
「……母さんのだし」
「ふーん?」
一応奥の方に仕舞っておいたものの、食器を取り出す時に千歳に見られていたらしい。
周の食器だけでは足りないので真昼がいくつか自宅から持ってきていたのだが、まさかそういった細かいところによくもわるくも大雑把な千歳が気付くとは思わなかった。
「ま、別にいいんだけどー? ねーいっくーん」
微妙に反応が遅れた周を意味深に見た千歳は、にっこりと笑って樹にもたれかかる。
こうしてくるのはいつもの事らしく、特に驚いた様子もなく千歳に手を伸ばして
「人んちであんまいちゃつくな」
「うらやましいー?」
「別に」
樹とくっついてご満悦そうな千歳は樹の胸に体を預けつつ、
「……
「血涙を流すやつらが居るのも忘れないでやってくれ」
みんなこうしている、なんて事ありはしないだろう。家族と過ごす人間も居れば友達と過ごす人間も居る。一人の人間だって居るだろう。
独り身を屈辱だと
「男子ってそんなに恋人欲しいものなの?」
「そうなんじゃないのか。
「そりゃ周が変わり者だからな気がするけどな」
「うっせ」
「まあクリスマス前ってみんな浮き足立ってるよねえ。特に独身男子。この間天使様のところに押し掛けてクリスマスの予約とろうとしてみんなばっさり切られてて、
「へえ」
その約束の相手は、自分なような気がする。
「その時の男子の絶望の顔がやばかった。失礼ながら笑った」
「笑ってやるなよ」
「だってさ、普段から
そんなのについてく
千歳も真昼とは違ったベクトルでの美人なため、色々とあったのだろう。もてる女は人間関係に悩まされるのだな、とちょっと
「まあ椎名も大変だな、色々誘われて」
「……周ってほんとに天使様に興味ないよね」
「まあな」
「お隣さんが周にとっての天使様だもんねえ」
「追い出すぞ」
「いやん」
しつこい、とほんのり強めに
「でもお隣さんにお世話になってる事は否定しないんだね」
ぐ、と言葉をつまらせると、千歳は満足したように笑った。
「睨まないでよー。ごめんって」
あまり反省していなさそうな
そちらを見て固まったので何事かと周もつられて窓を見て、青空の背景にふわりと白いものが落ちていくのが見えた。
「……あ、いっくん見て! 雪だ!」
「おー、ホワイトクリスマスってやつかー」
十二月後半ともなれば、雪が降ってもおかしくはない。
晴れているのに雪が舞い降りるというのはやや珍しいが、恋人達にとっては
まだ夜ではないが、気温的に恐らく夜までちらちらと降っていそうで、聖夜を雪化粧してくれるにちがいない。
さぞカップルが喜ぶんだろうなあ、と思いながら、身近なカップルが窓を開けてベランダに出るのを見守った周は「どうせしばらくそこでいちゃつくだろうし、温かいものでも準備しとくか」と立ち上がったところで──ベランダから、すっとんきょうな声が聞こえてきた。
「へ? な、何でここに」
「え、え?」
「あっ」
最後に聞こえてきた声は、最近聞きなれてきた、どこか甘さを感じる涼やかな声だった。
猛烈に、嫌な予感がする。
ベランダで二人が固まる気配を感じながら慌てて駆けつければ、ベランダでは丁度雪を見に出たらしい真昼が、柵越しに二人と出食わしているところだった。
最悪だ、と隣に姿勢よく座る真昼を見ながら、周はため息をついた。
ベランダで遭遇するという大惨事を迎えた周は、仕方なく真昼を
どうせ
それに、しっかりと口止めをしておかなければあとが怖い。
「……あの、本当にすみません」
「お前が悪い訳じゃない」
非常に申し訳なさそうなか細い声で謝られるものの、こればかりは真昼も悪くない。
ホワイトクリスマス、それも初雪だったので、ついベランダに見に行ってしまったのだろう。
周も窓を開ける音が聞こえていたなら恐らく止めただろうが、部屋に音楽をかけていたせいで聞こえなかったのだ。

それに、真昼もなるべく音をたてないようにしていたのだろう。全く気付かなかった。
反省しあう二人を見ながら、千歳が目を輝かせながらぐいっと顔を近付けてくる。
「で、周のお隣さんって天使様だったの!?」
「あの、天使というのはやめていただけると……」
流石に天使様と目の前で呼ばれるのは嫌だったらしく控えめに拒んでいるのだが、千歳はにこにこにしながら聞いているのかいないのか分からない。
樹はというと、頰をかきながら周と真昼の姿を交互に見ながら
「えー。じゃあ……今までの流れでいくと、椎名さんは周の隣に住んでいて、よく周にご飯を作ってると。この見解はあってるか?」
「……おう」
「ま、まあ……その、恩がありましたし、藤宮さんが見るからに不健康な食生活を送っていたのが気になったので……」
関わるきっかけもさらっと話してどうして交流が続いているのかも説明すると、樹は「なるほど」と言いつつも微妙に納得していなさそうな表情でもある。
周が樹の立場でも、納得出来ないだろう。
周のような一般男子が、真昼のような優秀な女性に世話を焼かれているなんて。
「うーん、事情は把握したんだけどさあ。
「ぶっ」
普段全く聞きなれない単語を使われて、思わず吹き出した。
通い妻。
言われてみれば、状況だけならそう見えるのかもしれない。夕食を毎日作ってくれて、たまに休日の昼ご飯もご馳走になっている。その上たまにお掃除も手伝ってくれているのだ。聞いた感じそう聞こえてしまうのかもしれない。
違うのは、互いに愛情というものは持ち合わせていないというところだろう。
真昼も樹の言葉に
樹や千歳には普段の学校と同じように接するんだな、と思うと、何だかややくすぐったいものを感じる。
「こっちにやましい思いは
「周がそういうなら良いんだけどさ。ほんと、
「……まあ」
「へえー」
「うるさい」
「まだ何も言ってないよ?」
「顔がうるさかった」
「ひどい!」
千歳のにこにこ……というかにやにや笑いは、非常にささくれだっている心に悪い。
今のところ事実確認だけでさほどからかわれてはいないが、からかわれるのは御免なのだ。真昼にも影響が出るので、出来れば千歳は無視したいところである。
「まあまあ落ち着け二人とも」
最初から周の様子が変わった事を気付いていた樹は、千歳のようにからかう様子ではない。
本気でいやがる前にやめてくれるので、何だかんだ空気が読めて気遣いも出来る男なのだ。出来れば
微妙に睨む周と
「……えーと椎名さん、うちの周がお世話になってます」
「いつからお前んちの子になった」
「こちらこそ
「そこ
「実際駄目なやつだし」
「このやろ」
確かに、散々樹にも言われていたし、自覚もしていたが……指摘されるというのは、ものすごく複雑なものである。
こういう冗談には乗れるらしくちゃっかりボケた真昼は、周と樹のやり取りを見てくすりと
周だけに見せる素、というほどではないが、少しだけ被った猫がお出かけした笑顔であり、樹もどこか
彼女持ちがみとれてんな、と樹を小突いたら、不機嫌な千歳が同じように……いや、ちょっと強めに小突いたのが何だか面白かった。
ただ、真昼が不思議そうに小首をかしげたので、周は何でもないように元の体勢に戻る。
「……で、だ。別に、俺らはお前らみたいな甘ったるい関係ではないが、他の連中に
「分かってるよ、人に言ったりはしない」
暗にしゃべったらどうなるか分かるよな、と脅しをかけているのだが、樹があっさりと
「千歳もだぞ」
「私もそこまでおしゃべりじゃないよー。それに、こんな可愛い子が周にご飯作ってるとかって信じてもらえなさそうだし」
「不相応ですまんな」
「そこまで言ってないのにー」
千歳の言う通りだしそれは自覚している。
普通の男子生徒が、学園のアイドルと言ってもいい天使様にお世話をしてもらっているなんて、
仮に信じられたとしても
別にそれは予想出来るし、だからこそ外にはこの事実を漏らしたくない。面倒事はごめんだった。
卑屈だねぇ、と笑った千歳は周を見ていたものの、途中から吸い寄せられるように真昼に視線が移っている。
じい、と熱心に見つめたかと思えば、ほう、とため息をこぼしてはまた見つめたり。
真昼も居心地が悪そうにしていて、どうしていいのか分からないようだった。
「あの、なんですか?」
「……改めて思ったんだけどさ。椎名さんってめちゃくちゃ可愛いよね」
「え? ありがとうございます……?」
正面から
「こんな近くで見たの初めてなんだけど、やっぱ天使様って言われるくらいに美人なんだよね。顔立ち整ってるしすごく肌白くて綺麗だし
「あ、あの……?」
千歳の悪い
周は、千歳が苦手だ。
嫌いではない、人柄は割と好ましくはあるのだが……どうしても、苦手なところはある。ハイテンションだとかたまに無駄に踏み込んでくる所とか、そういった所が苦手だ。身内に似たような人間がいるから余計に苦手意識が湧くのだろう。
つまるところ、その母親にどこか
千歳は周の母親に性格もそうだが
「やーほんと近くで見るとすっごい美人で可愛いなあ。ねね、髪とか触っていい? というかそんなサラサラなのに
「や、あ、あの……そんなに一気に言われても」
「お肌もぷるぷるだしいったい何したらこんな風に調子を保てるのかなあ」
同じ女性として美容の秘訣が気になっているのと真昼が美人でおさわりしたい欲求があるらしい千歳が矢継ぎ早に質問しながら真昼に手を伸ばす。
流石に止めないと真昼が可哀想な気がしたので、ったくと悪態をつきながら手を伸ばしかけた千歳の頭をぺしりと軽くはたいておいた。
制止と突っ込み目的なので本当に軽くではあったものの、衝撃を受けた千歳は「あいたっ」と小さく声を上げて真昼へ伸びた手を引っ込めた。
真昼はというと、周の静止に
「何もはたく事ないと思うんだけど」
「こいつは人見知りなんだから慣れない内からスキンシップはやめろ」
「慣れたらいいの?」
「それは椎名に聞いてくれ。まずは段階踏め段階」
明らかに真昼は逃げの体勢に入っていたので、止めて正解だっただろう。
ほんのり、というかかなり困っている真昼を見て千歳も止めた理由は納得したらしい。
「ごめんなさい、興奮のあまり触りそうになりました」
「は、はあ……」
いきなり触りそうになったと暴露されても真昼は困っているようで、どうしていいのか分からなさそうにこちらに助けてと視線で求めていた。
「あー。椎名、千歳は勢いのある変人だが悪いやつじゃない……と思う」
「ねえそれ
「今の言動見て否定できるか?」
「できません!」
堂々と自ら否定した千歳はじーっと真昼を見たのち、とても大
今度は、真昼に
「ならばお友達からよろしくおねがいします」
「え? は、はい、よろしくお願いします……?」
握手を求められて、真昼はおろおろとしつつも差し出された掌を握った。
恐らく一度気に入ると仲良くなろうとする千歳の性質上真昼が振り回されそうな気がしなくもなかったが、流石に普通の友達付き合いならこちらが口出しする事でもないだろう。
節度を持った付き合い方をしてほしいものである。
「仲良くなるには自己紹介が大事だよね! 元々知っていたり周から名前聞いていたりするかもしれないけど、私は
「やー、親友だなんて照れるなあ」
「わざとらしく照れるのは気味悪いんだが」
「またそういう言い方する……周、知ってるか? 世間ではそういうのをツンデレって言ってだな」
「まじで追い出すぞ」
「この雪空の下に放り出すなんてひどいわっ」
「男がわざわざしな作って言うな」
うえっ、とこちらもわざとらしく気味悪がってみればけらけらと樹が笑う。
その様子を見て真昼が目を丸くしていたが、樹が「ああ、オレらいつもこんな感じだから」と愉快そうに唇の端を
「んで、改めて。オレは
「お前俺を何だと思ってるんだよ」
「……藤宮さんは私に興味ないそうですし、生活能力はないですが常識的な方なので妙な事はしてこないと思っています」
「生活能力がないは余計だがそれはどうもありがとう」
否定出来ないのが悲しいところではあるが、周を人間として信頼してくれているというのはやはり
樹が「ここまで距離詰めておいて椎名さんに興味ないとか男かどうか疑うぞ」と耳打ちしてきたので軽く樹の背中を
全く興味がないと言えば
真昼にとっても、程よく親しくして
真昼をちらりと見れば、こっちの話は終わったと判断したらしい千歳に質問攻めにされていて、おろおろしている。
しかし、嫌そうな雰囲気はなかったので、その内慣れて打ち解けていくだろう。
困惑しつつも小さな笑顔を浮かべて対応する真昼に、周はひっそり安堵して二人が仲良くするのを眺めた。
「本当にごめんな」
夕方になって樹と千歳が帰ったあと、周はほんのり疲れた様子を見せている真昼に謝った。
いきなり知らない人間に
こんなやり取りを
「いえ、私が
「騒がしかっただろ」
「……
「素直にうるさいって言ってもいいんだぞ」
「ちょっと勢いはありましたが面白い人でしたよ」
「ちょっとどころじゃねえ……。……まあ気にしてないならいいんだけどさ」
あれは確実にうるさいの領域に入ると思うのだが、控えめな真昼は実にマイルドな表現で彼女を評していた。
そこまで嫌がっていないのは幸いだったが、千歳と友達になってよかったのかは分からない。
かなり真昼とは違うタイプなのだが……新鮮さ、という意味ではいいのかも、しれない。
もちろんあまりに真昼が困った時は注意するつもりなので、気を付けて見守りたいところである。
「私の周りにはああいった人は居ませんので、少し楽しかったです」
「まあ千歳みたいなやつはそうそう居ないだろうな……しつこくしてきたらはたいていいからな?」
「ぼ、暴力はしませんので、頑張って言葉でとめます」
二人して彼女の暴走が前提な気がしなくもなかったが、実際千歳は勢い余ってよく変な方向に熱意を走らせるので、注意が必要だった。
あとで千歳に直接注意しておこう、という誓いを心に
この天候でなければ、あのカップルにはばれなかったのだが……恋人達の祝福に降ってくれているのかもしれないので、あまり文句を言えなかった。
真昼も、雪自体は見るのは好きらしく、周の視線の先に気付いて同じように眺めている。
冬だから早く日も落ちて、辺りは暗くなっている。
もう夜と言ってもいい暗さになっており、雪も淡いものなので家の照明でぎりぎり視認出来るといったところだ。「ホワイトクリスマスですね」
「そうだな。まあ、俺らにはあんま関係ないんだけど」
「綺麗だからいいんじゃないでしょうか」
交際関係では全くないので、ホワイトクリスマスとか正直関係はないのだが……真昼が喜んでいるので、雪も悪くないだろう。
小さく舞い落ちる雪が暮れた世界をうっすらと白く化粧していく。このまま降り続いたとしても、さほど積もらなさそうだった。
「まああまり降られると公共交通機関が麻痺するので、ほどほどにしてほしいですが」
「そこは現実的なんだな」
「人はロマンだけでは食べていけませんから」
「ごもっとも」
こんなやり取りが出来るのも、雪ならではなのかもしれない。
お互いに小さく笑い合って、真昼は立ち上がる。
「じゃあ私ご飯持ってきますね」
「え、持ってくる?」
「先に向こうでビーフシチュー作ってたので。流石に七面鳥丸々一羽ローストしても二人じゃ食べきれないかなって……」
「丸々一羽使って丸焼き作ろうという発想が俺にはないわ」
「周くんが料理下手なだけです。明日の昼食はオムライスにビーフシチューかけましょうね」
「なんてうまそうなものを……」
そんなもの食べる前から
「俺卵は堅焼きがいい」
「奇遇ですね、私も昔ながらの方が好きです。じゃ、鍋持ってきますね」
ぱたぱたと周宅から一時的に帰宅していく真昼の背中をぼんやりと見ながら、周は騒がしかった日中を思い出す。
本当に、バレるのは想定外だった。
元々疑われていたし疑念が深まる程度なら想定内だったのだが……まさか、あのタイミングで真昼が顔を出すとは思っていなかったのだ。
結果的に事情は説明出来たし、理解者を得られたのはよかった、のだが……少しだけ、複雑な気持ちでもあった。
もう少しだけ、二人だけの秘密でよかったのではないか、と。
(何考えてるんだ俺)
二人にいちいち隠さなくてもよくなったので、生活が格段と楽になるだろうに、微妙にもやもやとしたものを感じてしまっていて、自分でも訳が分からず困惑した。
結果的に見れば悪くはなかったのに、どこか引っ掛かってすっきりしない。
「どうかしましたか?」
「……なんでもない」
鍋を抱えて帰って来た真昼が周の様子に不思議そうに首をかしげたが、さすがにこんな言葉では表しきれない気持ちを彼女に漏らす訳にもいかないだろう。
取り繕うように普段の表情を浮かべる周に、真昼は訳が分かっていなさそうに終始きょとんとした顔をしていた。
「……はー、うまかった」
相変わらず、真昼の料理はうまかった。
クリスマスという事でいつもより手の込んだ料理が出ていた。
真昼によりじっくり煮込まれたビーフシチューはポットパイにされて、割りながら食べ進める形となっていた。
パイを割る楽しみを味わってからのサクサクの食感にビーフシチューのコクのあるソースを絡めて食べるのは、至福のひとときとしか言えない。
パイ生地をわざわざ仕込んだらしい真昼の
ちなみにケーキまで真昼の手作りである。
ポットパイ用のパイ生地を仕込んだついででもう一つ菓子用の生地を同時に仕込んでいたらしく、ミルフィーユを作ってくれた。最早職人レベルである。
「お粗末様でした。……よく食べましたね」
「ん。美味しかったからな」
「それはありがとうございます」
彼女は美味しいと言うと安堵したような笑みを浮かべるので、それを見るのが日課のようなものだった。
普段の表情よりもずいぶんと柔らかい顔が浮かぶのを見るのは周の特権のようで、なんだかくすぐったさがある。
「……明日はオムライスか……すげえ楽しみ」
「本当に卵好きですよね……だし巻き玉子とかすごい勢いで食べてましたし」
「うまいんだから仕方ないだろ」
いくら好物の卵料理でも、
独り占めしているのはすごく
「……周くんって、ご飯食べてる時はすごく幸せそうですよね」
「事実幸せというか、真昼の料理がうまいからな」
「それはありがたい限りですけど、お安い幸せですね」
「いや割と高いぞ……お前自分の価値を把握しろよ……」
なにせあの天使様の手料理である。一部の男子には
「私にとっては毎日作ってるものですからねえ」
「幸せもんですなあ俺も」
「……そんなにです?」
「そりゃ、うまい料理毎日食えてる訳だし」
基本的には物欲があまりない周にとっては食欲の方が強く、毎日美味しい料理を出来たてで食べられるというのが一番の幸せだ。
「どうやってこんなに料理を作れるようになったんだ」
「お世話してくれていた人が教えてくれました。『必ず幸せにしてくれる人の胃袋
「すまんな俺なんかの胃袋摑ませて」
「予行練習という事で」
くすりと小さく微笑んだ真昼に、不覚にもどきりとした。
「……しかしまあその世話してくれた人もすげえな」
「そうですね、あの人はすごく料理が上手でしたから。まだまだ私はあの人には
微かながらに柔らかな笑みを浮かべて少し遠い目をした真昼に、周はひっそりと安堵した。
この言い方であれば、真昼はその世話役の人間に可愛がられていたであろう。真昼からもその人物を慕っているのがよく分かる。
そんな人が真昼の
「余程うまかったんだろうな。まあ俺にとっちゃお前のが幸せの味なんだが」
母親はさておき、父親の料理もうまいが真昼の方が周の好みの味付けだ。
真昼の料理は、毎日食べても飽きないようなほっとする味がする。心休まる癖に心踊る料理で、全然飽きる気配がないしもっと食べたいとすら思うのだ。
まあ流石に真昼の負担が大きすぎるのでそんな事は言わないが。
うんうんと頷いていたら、真昼が固まっていた。
虚をつかれた、と言えばいいのか。
どこかぽかんとした、幼さを隠さない表情で、こちらを見ている。
「……真昼?」
「え、……なんでもないです」
声をかけられて我に返ったらしい真昼が慌てて首を振って、
お気に入りのクッションをぎゅっと抱き締め、そっと吐息をこぼしている真昼は、先程とは打ってかわって妙に色っぽさを感じた。
「どうかしたのか」
「……単に、私なんかが幸せの味作れていたのかな、って」
「何で卑下してるのか分からんが毎日食いたいくらいにはうまいぞ」
「あ、ありがとうございます」
ちら、とこちらを見上げて少し照れくさそうに眉を下げて小さく微笑んだ真昼に、今度は周が俯いて顔を隠したくなった。
本当に極たまに見せるこんな表情は、異性として好きという訳でなくても心臓を否応なしに跳ねさせる。
いつもの仮面を
じわじわとせり上がってくる熱がばれてしまうのは、嫌だ。お互いに照れていたら、確実に気まずくなる。
「あー、その、……そうだ真昼」
「はい」
「明日は、昼からでいいんだよな?」
この空気に耐えきれず
「はい、そういう約束ですよね? お昼ご飯作って、それから約束のげーむ、する……んでしたよね」
「おう」
「いや……でしたか?」
「違う、確認しただけだ。……本当に、イブを過ぎたとはいえクリスマスにそういう過ごし方でいいんだな?」
「嫌なら言いません。……たのしみに、してます」
また小さくふわっと

翌日家にやって来た
よくある休日に異性の家に遊びに来た時の緊張……な訳もなく、真昼たっての希望でゲームをする事になったため、その興奮が
なんでもテレビゲームなんて初めてらしい。その点では世間知らずのお嬢様と言ってもいいだろう。
「先にお昼ご飯作っちゃいますね」
「ん。堅焼きで頼むぞ」
「分かってますって」
注文の多い客に機嫌を悪くした様子はなく、エプロンを
そんなに楽しみにしていたのか、と思うと妙に気恥ずかしいというか、くすぐったい。
(まあ、ゲームを楽しみにしてるってだけなんだけどな)
決して、こうして二人きりで遊ぶ事が楽しみ、という事ではない。
「……どうやって操作するのですか?」
昼食後、二人でテレビの前のソファに座ってテレビ画面を見つめていた。
何のゲームがしたいのかと聞いてみたら種類すらもよく分かっていなかったので、有名な国民的2Dゲームを起動してコントローラーを渡してみたのだが……やはりどうしていいのか分からずあたふたしていた。
「えーとだな、まあ移動はこのスティック、ジャンプはこのボタンで……」
基本的には冷静沈着なあの真昼がめちゃくちゃ戸惑いながらコントローラーとテレビを交互に見ながら操作していて、なんだかとてもほっこりとしてしまった。
慣れていないとはいえ、こんなにものんびりとしたプレイははじめてである。
「……勝てません」
「ステージクリアはおろか最初の敵すら倒せてないからな」
「うるさいです」
「まあ慣れだ慣れ。こんなの体で覚えていけ」
何事も挑戦だ、と言い聞かせると、真昼は素直にゲームに戻っている。
娯楽であるゲームに真剣な表情で挑んでいる真昼を見ていると
ただまあ、あまりに初手で負け続けているため、いつまで
彼女がこちらを見てくる。
表情にむすっ、と効果音がつきそうなのは気のせいか。
「あーほら、ここはこうしてだな」
流石にこのままだとやる気に
周もこのゲームは幾度となくクリアしているので、彼女がつまる場所も難なく突破出来る。
というか真昼が下手くそすぎるだけで、普通の人間はここではひっかからないのだが……それは黙っておいた。
「ほら、この敵は一定速度で不規則に移動するが、こっちを視認するとキャラクターに向かって速度を上げて近付くんだ。タイミング見計らって跳んで……」
小さな手に重ねるようにしてコントローラーを握って操作、分かりやすく説明しながらお手本を見せる。
画面では、周が説明した通りにキャラクターが動き、敵を
なんて事のない動きなのだが、失敗し続けた真昼には新鮮だったらしく「わあ」と感嘆の声を漏らしていた。
長い
距離が近い
端整な横顔を眺めていると、視線に気付いたのか真昼がこちらを向く。
彼女の手にあったコントローラーに触れるように近付いていたため、思ったよりも距離が近い。というか、二の腕と手が触れ合っているし、なんなら彼女の吐息がほんのりと肌を
「ごめん」
ほぼ真昼の手を包んでいた事に気付いて体ごと慌てて離すと、真昼はぱちりと大きく瞬いた後今更ながらに近かった事に気付いたらしく視線がさ迷い始めた。
「いえ……別に。こちらこそ、すみません」
うっすらと色づき始めた
あまり、真昼は接触が好きではない。いくら大分慣れてきたとはいえ、手を握られるというのは不愉快かもしれない。
やや恥ずかしそうにしているものの、嫌悪感がないとも限らないだろう。
「ほんとごめん」
「あの、そこまで気にしてないですよ?」
「嫌じゃないのか」
「……びっくりはしましたけど、嫌とは。知らない人ではないですし」
寛大な天使様はどうやら無礼を許してくれるようだった。
あっさり水に流してくれた真昼に
今度こそ真昼にゲームを進ませようと画面を見て……やっぱり倒されている真昼の姿に、周はどうしたら彼女がゲームが
結果的に一面をひいひい言いながらも何とかクリアしたところで、
ずぶの初心者に死に覚えをさせ続けると、やる気に著しく関わってくる。他のゲームに目を向けてもらって、ストレスを抜こうという魂胆だ。
「真昼、傾いてる」
という訳で次は現実世界でも
このゲームはジャイロ操作は必要としていないし、コントローラーにもジャイロセンサーなどついていない。

体を傾ける必要は全くないのだが……本人は無意識なのか、コントローラーを持った状態で左右に揺れていた。
本人は、ゲームに集中しているのか、返事はない。
先程のゲームとは違い、車を
大真面目な表情でゆらゆらと揺れながら頑張って車を動かしている。
(なんだこれ
振り子のようにふらふらしている真昼が、妙に可愛らしい。大真面目に、そして一生懸命にやっているから、余計に可愛く見えるのだろう。
大きなカーブを曲がれば、自然と真昼の体も大きく傾く。
ぽてん、と周の
「……別に、体は傾けなくてもいいんだぞ?」
「わ、わざとじゃないです」
「うん知ってる。でも傾いてたから」
唇がぷるぷると震えるのをなんとか抑えつつ、真昼を起こしてやる。
やはりというか、柔らかくて軽い。小柄なのはもちろんなのだが、折れてしまわないか心配なくらいには細くて、触る事を躊躇うほどだ。
周に起こされた真昼は、羞恥からか頰を染めて震えている。
それがまた小動物のようで可愛らしく、とうとう耐えきれなくなって笑ってしまった。
「ば、
「いやいや。微笑ましいなと」
「それが馬鹿にしてるんです」
「
「そうは思いませんけど……」
「だろ? 単に可愛かったなと」
「……その可愛いは確実に子供っぽくて微笑ましいの意です」
どこか
内心でいくら思おうが顔に出なければ問題ないので、心の中でひっそりと思っておくようにしよう。
ほんのり不服そうな表情を浮かべている真昼に小さく笑えば、ぷいとそっぽを向かれた。
天使様が途中拗ねそうになるという事態はあったものの、その天使様もゲームをしていたらすっかり頭から抜けたらしくまた一生懸命な表情に戻っている。
ゲーム自体には大分慣れたのか、たどたどしいながらもプレイは出来ているし、なんとかついていけている。
最初にやったゲームとは違い車を操る、というコンセプトのゲームだからだろう。
本来のコースから外れてダートに突っ込んだり壁にぼこすかぶつかったりしているものの、それでも前進出来ている。
ゲーム下手な真昼の事なので逆走しっぱなしにならないかとか不安に思っていたものの、思っていたより順調に進んでいてほっとした。
ついでなので周も画面分割して一緒にプレイしているが、真昼が無意識の妨害をしてきてちょっと
やはり彼女は自然と体を傾ける
その度にふんわりといい
まあ、それでも最弱CPU相手なので独走するのだが。
「……なんでそんな早いのですか」
「年季と慣れ」
幾度もプレイすればコースは覚えるしコーナリングも自然と上手くなるものだ。相手からの妨害も、慣れればカメラワークや
納得のいかなそうな顔をしている真昼には苦笑を返して、そっと一人プレイに戻してやる。
彼女には経験が足りないので、大きな画面でまず練習させてからだろう。周の腕を見て自分の腕にがっかりするより、CPUに慣れていく方がいい。
幸い彼女はやる気があるらしく、一人プレイに戻っても熱心に画面を見つめていた。
この調子なら、まあ何とかCPU相手になら立ち回れるようになるだろう。
努力家な面をこういう所でも見る事が出来て、やはり微笑ましくてひっそりと笑いをこぼせば気配で分かったらしい真昼がぺちぺちと不服げに
それが面白くて余計に笑えば、真昼が
「勝てました」
苦節二時間強。
画面の端に
長い間テレビに向かって格闘してようやく得た栄光の一位。
何度も何度もビリを経験して、それでも
やりきったと言わんばかりの達成感のある表情に、周は素直に称賛の拍手を送った。
「よかったな。頑張ったの見てたぞ」
「はいっ」
褒められて
にこにこ、といった分かりやすい笑顔ではなくて、ほんのりと嬉しそうに緩んだ淡いはにかみは、いつもの彼女のクールさからは考えられないほど甘い。
最近普段のクールさの合間に
どこか無邪気とも言えるあどけない微笑みは、周の理性の
猫を撫でたいという欲求にも似た、可愛がりたいという衝動はつい腕に指令を出してしまって……思わず手が持ち上がりかけて慌てて下ろした。
「どうかしましたか?」
「ああいや、なんでもない。うまくなったなあと」
「上達しましたか?」
「したした。最初に比べればすごくよくなった」
「ありがとうございます。楽しくて、つい頑張っちゃいました」
ふふ、とまた笑みを浮かべた真昼が見ていられなくて、周は
「一位のごほうびにこれをやろう」
「え、あの、別にそんな」
「ごほうびが嫌なら白い
そう、昨日うっかり渡し忘れていた、クリスマスプレゼントである。
誕生日とクリスマスがそう離れてないので再度プレゼントに困る事になったのだが、今回はまああてがあったので誕生日ほどの苦労はなかった。
クリスマスプレゼント、という言葉に今がクリスマスという事を改めて思い出したらしくぱちりと瞬きをしていた真昼だったが、おずおずと受け取っている。
開けてもいいぞ、と声をかければ、また丁寧に梱包をほどいていった。
(まあ、大したもんじゃないんだけどな)
箱を開いてゆっくりと取り出したのは、レザー製のキーケースだ。
あまり高価なものでも
花と
「ま、
「いえ、ありがたく使わせていただきますよ。周くんって思ったよりもセンスいいですよね」
「思ったよりもって何だよ」
「いえ、普段スウェットとかジャージばかりですし、服装がセンス以前の問題ですし」
「こんな機能性ある服は他にないぞ」
真昼には着飾った姿なんてまず見せる機会がないし、そういうのは面倒でなるべく避けたいので、学生服か緩い部屋着しか見せていない。
なのでセンス
「……ちゃんとしたら、かっこよくなるかもしれませんよ? 中学生の周くん、ちゃんとしてたじゃないですか」
「あれは母さんが無理矢理……待て何で知ってる」
「
「あんにゃろ」
まさか母親の仕事に付き合わされていかにも外行き用の格好をさせられた時の写真が流出しているとは思ってもいなくて、周はここには居ない母親に内心で大量の文句を送りつけておいた。
「……俺はああいうの似合わないから」
「そうですかね。周くん、他人とあまり目を合わせないようにしたり髪形で隠してるだけで、別に目鼻立ちは整ってると思いますけど……」
小さな手が、周の顔に伸びた。
伸びた前髪をかき上げるように白い掌が額に触れ、視界がいつもより広くなる。
別に驚く事はない、不細工でも美形でもない普通の顔だろうに、こちらをじっと見る真昼が不思議でならない。
「……なんだよ」
「いえ。前より瞳が生き生きとしてるな、と」
数ヵ月前は目が死んでましたからね、と非常に失礼ながら否定出来ない言葉を送った真昼は、じいっと周を見上げている。
そんなに見ても楽しいものではないだろうに、静かにこちらを見つめていた。
なんだかこうして異性に、それもとんでもない美少女に凝視されるのは、気恥ずかしい。
ただ、やられてばかりなのはつまらないのでお返しとばかりに頰にかかる真昼の髪に触れて
触るのには
(しかしまあ、ほんと美人なんだよなあ)
改めて見れば分かる、真昼の美貌の
かつて周の部屋に落ちていた雑誌に載った美女とやらより余程彼女の方が綺麗で、魅力的だろう。
そもそも、写真というのはあまり信用ならない。
一瞬を切り抜いて加工出来るそれは、ありのままを写す事も、美しさを
目の前に居る真昼は無加工でも可愛らしく、綺麗だ。
飽きそうにない端整な顔立ちをじっと見つめていれば、真昼が次第に視線をさ迷わせ始める。
何なんだ、と思った瞬間には真昼が周の髪から手を離し、瞳を伏せる。
もぞ、と居心地悪そうにしている真昼は、コントローラーを完全に手放して
「あの。その……そうだ。私からもクリスマスプレゼントがあります」
「お、おう、ありがとう」
一体何なんだと問いかけようとして、真昼が話を
「じゃあ、私夕ご飯の
「え? そ、そうか……?」
それだけ言い残してさっさと席を立った真昼に、周はあまりに早い展開で困惑するしかなかった。
夕食後、食器洗いを終えた周がリビングに戻ると、真昼がそわそわしたような様子を見せていた。
最近慣れてきた隣へ座る事だが、今度は真昼が落ち着いていない。夕食中も微妙に視線が
真昼が自分に意識する事なんて今までなかったし何かあったのかと思ったが、もしかしたらプレゼントを渡したからかもしれない。周も真昼にくまのぬいぐるみを渡した時は居たたまれなさというか落ちつかなさがあったし、反応が不安という事だろうか。
「ちなみにこれ、開けていいのか?」
「ど、どうぞ」
ローテーブルの上に置いてあった真昼からの贈り物を持ち上げると、微妙に
やはり贈り物に緊張していたんだな、という結論を自分の中で出してから、周は袋を縛っていたリボンをほどく。
重さ的にはそう重くなかったし手触りからして布製品だと分かっていたのだが、取り出してモノトーンの千鳥柄の布が出てきた時は想定外だった。
なんだこれ、と思ったが、広げてみてどういう用途のものなのかすぐに分かった。
「マフラーか」
柔らかく滑らかな手触りのそれは、首もとに巻き付けて暖を取る用のものだった。
「……周くんは、おしゃれに無頓着ですし、登下校いつも寒そうなので」
「実用性に
「普段使いするものは質を重視するべきですので」
基本的に質の良いもので
自分で触った限りでも非常に手触りがよく敏感肌でも気にならなそうな柔らかさと滑らかさなので、恐らく非常に着け心地もいいだろう。
真昼が選ぶのも頷ける品質に感心しつつ、こちらの様子をやや硬い雰囲気で見守っている真昼にマフラーを揺らして見せる。
「着けてみてもいいか」
「周くんにあげたので好きにしてください」
「へいよ」
微妙にそっけない返事につい苦笑しつつ、お言葉に甘えていただいたマフラーを首に巻く。
生地のよさは皮膚の薄い首だからこそよく分かる。柔らかく肌を刺激しない、
今は室内だから効果が分かりにくそうだが、恐らく外で巻いてもいい感じに
「ん、すげえあったかい」
「それはよかったです」
周が柔らかい笑みを浮かべると、真昼も安堵したようで淡い微笑みを浮かべる。
最近はよく種類は異なれど笑みを浮かべるようになってきた真昼に、ついその端整な顔を見つめてしまう。
(……こうしてたら、本当の天使様なんだけどな)
学校で浮かべる天使の微笑がそうではないとは言わないが、こうして素の部分で見せる笑みの方が、よっぽど魅力的に見えた。
「な、何ですか」
どうやらじっと見ていた事に気付いたらしく、やや視線が泳いだ後にこちらを見る。
「いや、真昼って初めて会った時に比べて少し表情柔らかくなったなって」
「……そうですか?」
気付かなかった、と言わんばかりに頰を押さえて目を丸くしている真昼に、周は小さく笑う。
「おう。いや前はツンツンしてて可愛げなかったっつーか」
「可愛げなくて悪かったですね」
「怒るなよ。……今は前よりずっと、なんつーか、いいなって思うよ。そうやって笑ってた方がずっと可愛いのに
真昼が並外れた美少女だという事は分かりきっているのだが、表情によって印象は変わってくる。
学校で見せる天使の笑みは鑑賞用というか触れてはならない壊れ物のような美しさ。
周に最初に見せていた冷たい
今の真昼は、年相応のどこかあどけなさのある柔らかさを帯びた笑顔で、触れて可愛がりたくなるような愛らしさがある。
これが少しずつ慣れて打ち解けてきた事による変化だと思うと、なんというかこそばゆさがじわじわと胸を上がり頰にやってくるのだ。
「今みたいに自然に笑ってもらえて、俺としても慣れてもらえたのかって嬉しいし……なんだこの行動」
ただ、言葉は途中で物理的に遮られた。
幸い持ち上げられているだけで締められてないので苦しくはないが、息がこもってやや熱いと感じてしまう。
「……ちょっと黙ってください」
「なんなんだ」
「……何でもです」
訳の分からない理由で視界を
正面から見た微妙に体を震わせた真昼の頰は、内側から色付いていた。
どうしてこんな表情を──と思ったが、思い当たる事は一つくらいだ。
「……もしかして、照れてるのか」
「うるさいです」
周の言葉を肯定するようにそっぽを向いた真昼に、そういうところはやっぱりツンとしてるんだなと、とつい笑ってしまった。
そんな周に真昼は小さく
窓を見れば、昨日と同じように雪がひらひらと舞っていたが、真昼は構わずベランダに出て行った。
ひやりとした空気が周の方にまで流れてくる。
すぐに窓は閉じられて外の空気が遮断されたものの、地味に残るひんやりとした空気は構えていないと身震いしそうなほどに冷えたものだった。
それにもかかわらずベランダに出た真昼に、周はそっとため息をつく。
照れ隠しに逃げるのはいいが、もう少し暖かい格好をしていくべきだろう。ただでさえ真昼の服装は上着を着るか室内に居るという前提の装飾性を優先しているものなので、あれではすぐに
全く、と悪態づきつつ、ソファにかけてあったブランケットを手にする。
雪もちらついているのに薄着で外に長時間居るのは自殺行為だろう。
周も上着を
「外の空気吸うのはいいけど、風邪引くぞ」
「……それは私の
どうやら心は落ち着いたようで普通の様子と表情で返答をした真昼だが、返ってきたものはややひねくれたものだ。
暗に、周が初めて真昼と会話した時の事を言っているのだろう。
「む。……あれはちゃんと風呂に入って温まらなかったからであって、油断しただけだ」
「次
「おかんか」
たまに真昼は母親じみた事を言い出すので笑いつつ、真昼との出会いを思い出す。
あれは秋の寒くなり始めた頃だった。恐らく十月の半ば
真昼に看病される事が、一番の想定外であったが。
「……そういや、ああして話すようになってからもう二ヶ月は
「そうですね。周くんの部屋が汚かったのもいい……いえ、よくはないですけど、思い出です」
「うっせ。今は片付けてるだろ」
「
「真昼様のお陰だな。伏して感謝したいくらいだ」
「要りませんよ、もう」
こうして軽口をたたけるようになったのも、昔では信じられない事だろう。昔というには随分と最近の事なのだが、この二ヶ月は色々ありすぎて時が経つのが早かったのだ。
一度沈黙が降り、一気に静かになる。
昨日から降ったりやんだりを繰り返している雪は、今はふわふわと空から舞い降りて周囲の家屋を白く化粧していた。
住宅街、それもクリスマスの夜なため車の走行音や喧騒はどこか遠い。どこかの家でクリスマスソングをかけているのが
真昼がはぁ、と空気を吐き出して白い息を作っている音の方が、よく聞こえる。
「……何だか、不思議な気分です」
しばらくの沈黙の後に声を上げたのは、真昼の方だった。
「最初は何だこの人って思ってたんですよ」
「まあ真昼からしたらそうだろうな。いきなり傘押し付けられたら疑うだろうよ。……今は?」
「……さあ、どうでしょう。世話の焼ける人なんじゃないですかね」
「違いない」
明確な答えは出さないままそっぽを向いた真昼に笑って、ベランダの手すりによりかかる。
「……俺も、こうして二人でご飯食べるような仲になるとは思ってなかったよ。ぶっちゃけ真昼って鑑賞用って感じで関わりたいとは思ってなかったから」
「ぶっちゃけましたね。知ってましたけど」
だからこそ信用してましたし、と付け足されて体を揺らして笑う。
興味がないからこそ真昼に受け入れられたのは知っているので、お互い様だろう。
「でもまあ、こうして知り合えてよかったと思うよ。生活習慣改善したし、毎日
「……そうですか」
「ほんと、この二ヶ月感謝しきりだよ。ありがとうな」
この感謝の気持ちに
真昼のお陰で生活水準は上がって毎日美味しく幸せな食事時間を過ごしている。それだけでなくて、取り繕わない彼女と話すのは存外心地よく、日々の楽しみになっている。
たまにからかった時の反応も可愛らしいものだし、見ていて飽きない。
(最近は、笑うようになってきたしな)
先程も思ったが、感情表現が豊かになってきていて、なんというか可愛がりたくなるような欲求にかられる。流石に実行は出来ないが、見ているだけで
真昼は周の言葉に目を丸くして、それから僅かに瞳を伏せる。
ほんのりと頰が赤くなっているのは、寒さのせいなのか、照れのせいなのか。
「こちらこそ、ありがとうございます」
「俺なにもしてないけどな」
むしろ周は真昼の世話になりっぱなしで何も彼女に返せていないのだが、真昼はゆるりと首を振って否定する。
「……周くんには分からないところで感謝してますので」
「ふーん……って、なんかお互いに礼言い合ってるのなんか年末っぽいな。明日からは年末ムードだからまあおかしくはないんだけどさ」
年末、という言葉に瞳を瞬かせた真昼は、それからくすっと笑みを浮かべる。
「ふふ、そうですね。……まだ早いですけど、来年もよろしくお願いしますね」
「……ああ、来年もよろしくな」
願ってもない申し出に頷いて同じように笑えば、真昼が「冷えますからそろそろ入りましょうか」と背を向けてリビングへ続く窓を開ける。
ちらりと見えた耳がほんのりと赤くなるくらいには冷えているので、周も風邪を引かない内に撤収した方がいい。
(……何だかんだ、俺もこの生活が気に入ってるんだよな)
だからこんなに胸が温まっているのだろう。
真昼に続いて部屋に戻りながら、周は亜麻色が揺れる様をじっと見つめ、それからそっと口許に弧を描いた。
これからも、まだまだお隣の天使様との付き合いは続いていきそうだ。
あとがき
初めまして、
お隣の天使様、お楽しみいただけたでしょうか。
ほのぼのじれじれなゆるふわラブコメを目指して書いた作品ですが、ちゃんとその目標通りに書けたんじゃないかなと思います。
最初は互いにシビアで素っ気なかったのに、徐々に信頼を寄せていき、いつしか惹かれていく──この感情と関係の移り変わりを描くのがとても楽しかったです。
ゆっくりゆっくり、相手の事を知りながら距離を縮めていく、そんなお話があってもよいと思います。まあ何が言いたいかってじれじれって最高ですよね! というお話です。
こちらの作品はウェブに掲載してあるものを加筆修正して本にした形になるのですが、正直一巻分ではまだまだお互いに矢印が完全には向き合ってない状態です。これから本番です。
これからまたじれじれしつつもお互いに歩み寄っていく予定です。両片想いは最高だぜ。
本作の作中ではヒロインの
実は担当編集さんと打ち合わせをした時にイラストは
ずっと好きだった先生なので感動で……イラストを担当していただき本当にありがとうございます!
和武先生の魅力たっぷりのイラストを見れば分かりますが、どのキャラも可愛いです。イラストをいただく度に悶えておりました。天使様マジ天使です。
素敵に描いていただいて本当に感謝の気持ちで一杯です……!
それでは最後になりますが、お世話になった皆様にお礼を。
この作品を出版するにあたりご尽力いただきました担当編集様、GA文庫編集部の皆様、営業部の皆様、校正様、和武はざの先生、印刷所の皆様、そして本書を手にとっていただいた皆様、誠にありがとうございます。
また次巻で会える事を祈りつつ、筆を置かせていただきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました……!
著者
佐伯さん(さえきさん)
大体ラブコメかラブファンタジーばかり書いてる作家です。ぶっきらぼうとクーデレとの組み合わせが好きすぎてこのお話が生まれました。徐々に甘えを見せてくる天使様を見守っていただけたら幸いです。
イラスト
和武はざの(かずたけ はざの)
北海道在住。猫とじゃがいもとラブコメを愛してやまないイラストレーター・漫画家をやっております。天使様とてもとても可愛いです。とくとご覧ください。
ファンレター、作品の感想をお待ちしています
<送付先はこちら>
ga-info@cr.softbank.co.jp

〈あて先〉
〒106-0032
東京都港区六本木2-4-5
SBクリエイティブ(株)
GA文庫編集部 気付
「佐伯さん先生」係
「はねこと先生」係
https://ga.sbcr.jp/
GA文庫
お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件
佐伯さん
発行人 小川 淳
発行所 SBクリエイティブ株式会社
〒106-0032
東京都港区六本木2-4-5
装 丁 AFTERGLOW
印刷・製本 中央精版印刷株式会社
2019年6月30日 初版第一刷発行
2019年7月15日 電子第一版発行
©Saekisan ISBN 978-4-8156-0248-2